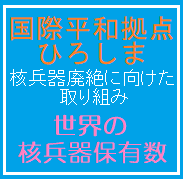昨日は文化の日でした。
1946年に日本国憲法が公布された日、なんですよね。
そして半年後に施行。
日本国憲法の公布と施行
”日本国憲法が平和と文化を重視しているということで、
1948年公布・施行の祝日法で「文化の日」に定められた。”
(Wikipedia)
1946年に公布、1948年に祝日になった。
1947年の11月3日は、何の日だったんだろ?(笑)



非戦を選ぶ演劇人の会の
ピースリーディング
という演劇があることを知りました。
興味深いのは、”台本”を公開していることです。
しかも、出典さえ明らかにすれば、台本をアレンジして、
演劇で自由に使って、メッセージを広めてください、という形をとっているんです。
(詳細はこちら→「台本公開」にあたって)



8月に行われた、
非戦を選ぶ演劇人の会 ピースリーディングvol.10
「9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…」
単純には分けられないのですが、大きく分けると
憲法9条を「変えたくない派」と「変えたい派」、
どちらも「平和を願っている」からややこしいし、
もちろん考え方や価値観はいろいろあるべきだと思いますが、
「言いくるめられたり、ごまかされたり」して、
答えを出すことになってはいけないと思います。
『伊藤真のけんぽう手習い塾』でも学んだ、
憲法は「私たちが国(の権力)に対して歯止めをかけるもの」、
という視点を忘れずに考えていけたらと思います。



「非戦を選ぶ演劇人の会」のサイト上に、
”これらの台本の構成者及び作者は、
多くの人にこの内容を広めたいという意図のもとに、
著作権を放棄しています。”とあるので、
何回かに分けて、台本を元に私なりに
内容を紹介したいと思います。
もちろん直接台本を読んでいただいても(^_^)v
台本→9条を守りたいのに口ベタなあなたへ...(doc.ファイル)
★以下、内容です。エントリーしたらリンクします。
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(11)≪平和への道≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(10)≪9条と外交≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(9)≪テロを引き起こす原因≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(8)≪9条変えて普通の国に?≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(7)≪もし9条がなかったら≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(6)≪9条やめますか?それとも、ビジネスやめますか?≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(5)≪私たちを守ってくれるのは≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(4)≪国際貢献って?≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(3)≪9条と日米安保≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(2)≪日本国憲法はアメリカの押し付け?≫
『9条を守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(1)≪戸締り論≫



余談ですが、ピースマーク「 」の由来を初めて知りました。
」の由来を初めて知りました。
手旗信号をデザインしたものらしいです。
平和のシンボル(「ブログはれ、のちくもり」)
ピースマーク(Wikipedia)
1946年に日本国憲法が公布された日、なんですよね。
そして半年後に施行。
日本国憲法の公布と施行
”日本国憲法が平和と文化を重視しているということで、
1948年公布・施行の祝日法で「文化の日」に定められた。”
(Wikipedia)
1946年に公布、1948年に祝日になった。
1947年の11月3日は、何の日だったんだろ?(笑)



非戦を選ぶ演劇人の会の
ピースリーディング
という演劇があることを知りました。
興味深いのは、”台本”を公開していることです。
しかも、出典さえ明らかにすれば、台本をアレンジして、
演劇で自由に使って、メッセージを広めてください、という形をとっているんです。
(詳細はこちら→「台本公開」にあたって)



8月に行われた、
非戦を選ぶ演劇人の会 ピースリーディングvol.10
「9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…」
単純には分けられないのですが、大きく分けると
憲法9条を「変えたくない派」と「変えたい派」、
どちらも「平和を願っている」からややこしいし、
もちろん考え方や価値観はいろいろあるべきだと思いますが、
「言いくるめられたり、ごまかされたり」して、
答えを出すことになってはいけないと思います。
『伊藤真のけんぽう手習い塾』でも学んだ、
憲法は「私たちが国(の権力)に対して歯止めをかけるもの」、
という視点を忘れずに考えていけたらと思います。



「非戦を選ぶ演劇人の会」のサイト上に、
”これらの台本の構成者及び作者は、
多くの人にこの内容を広めたいという意図のもとに、
著作権を放棄しています。”とあるので、
何回かに分けて、台本を元に私なりに
内容を紹介したいと思います。
もちろん直接台本を読んでいただいても(^_^)v
台本→9条を守りたいのに口ベタなあなたへ...(doc.ファイル)
★以下、内容です。エントリーしたらリンクします。
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(11)≪平和への道≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(10)≪9条と外交≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(9)≪テロを引き起こす原因≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(8)≪9条変えて普通の国に?≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(7)≪もし9条がなかったら≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(6)≪9条やめますか?それとも、ビジネスやめますか?≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(5)≪私たちを守ってくれるのは≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(4)≪国際貢献って?≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(3)≪9条と日米安保≫
『9条は守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(2)≪日本国憲法はアメリカの押し付け?≫
『9条を守りたいのに口ベタなあなたへ…』より(1)≪戸締り論≫



余談ですが、ピースマーク「
 」の由来を初めて知りました。
」の由来を初めて知りました。手旗信号をデザインしたものらしいです。
平和のシンボル(「ブログはれ、のちくもり」)
ピースマーク(Wikipedia)