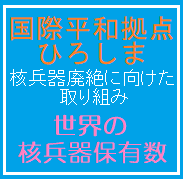中野佳裕氏(国際基督教大学非常勤講師)
マル激トーク・オン・ディマンド 第874回(2018年1月6日)
【ダイジェスト】中野佳裕氏:2018年のテーマは「関係性の豊かさ」
(全部見るには要有料登録)
個人的にすごくすごく興味深い内容だった。
わたしたち人間は、文明が進歩するにつれて、欲が出て、コントロールが効かなくなって、
貧富の差や、様々な差別がどんどん大きくなって、手に負えなくなって、
止めようと思っても止められない、ある意味強迫的になっているのだと思う。
世界全体が精神的な病に侵されている状態っていう気がする。
誰かのせいってことじゃなく、なるべくしてなったのだと思う。
感覚がマヒして、無意識に。
ちょっと絶望的になってしまうけど、そんな中で、
世界が患っている病を回復させようとする動きが確実にあると、中野氏の心強いことば。
「現代の主流なシステムの中では変えていくことは難しいが、
マージナルで小さな現象かもしれないが、
確実にオルタナティブな言葉や、
世界とのオルタナティブな関わり方を実践している動きは現れている!」
ラトゥーシュによる「脱成長8つの再生プログラム
(ローカリゼーションが取り組むべき関係性の再生作業)

中野氏による解説
”セルジュ・ラトゥーシュ・・・フランスの経済学者・哲学者。
もともとアフリカの開発問題の研究者、1960年代、フランス政府によるアフリカの開発の現場を見て、
そのあとアジアの開発の現場を見たときに、
ヨーロッパが押し付けている開発政策が、おかしいなと疑問を持った。
そこからアフリカやアジアの、土着のコミュティが持っている自立・共生的な生き方を
むしろ消費社会に向かっているヨーロッパ人の方が学び直さなければいけないのではないか、
一方的にヨーロッパなどの先進国が途上国に開発を押し付けるのではなく、
先進国が自分たちの行き過ぎた社会システムを変えていくことが
最終的に南北問題の解決につながっていくのだ、というふうに考えるようになった人物。”
* * *
なんと、レオ・レオニの絵本が題材に?

カタツムリの知恵と脱成長: 貧しさと豊かさについての変奏曲
中野 佳裕
コモンズ
マル激トーク・オン・ディマンド 第874回(2018年1月6日)
【ダイジェスト】中野佳裕氏:2018年のテーマは「関係性の豊かさ」
(全部見るには要有料登録)
個人的にすごくすごく興味深い内容だった。
わたしたち人間は、文明が進歩するにつれて、欲が出て、コントロールが効かなくなって、
貧富の差や、様々な差別がどんどん大きくなって、手に負えなくなって、
止めようと思っても止められない、ある意味強迫的になっているのだと思う。
世界全体が精神的な病に侵されている状態っていう気がする。
誰かのせいってことじゃなく、なるべくしてなったのだと思う。
感覚がマヒして、無意識に。
ちょっと絶望的になってしまうけど、そんな中で、
世界が患っている病を回復させようとする動きが確実にあると、中野氏の心強いことば。
「現代の主流なシステムの中では変えていくことは難しいが、
マージナルで小さな現象かもしれないが、
確実にオルタナティブな言葉や、
世界とのオルタナティブな関わり方を実践している動きは現れている!」
ラトゥーシュによる「脱成長8つの再生プログラム
(ローカリゼーションが取り組むべき関係性の再生作業)

中野氏による解説
”セルジュ・ラトゥーシュ・・・フランスの経済学者・哲学者。
もともとアフリカの開発問題の研究者、1960年代、フランス政府によるアフリカの開発の現場を見て、
そのあとアジアの開発の現場を見たときに、
ヨーロッパが押し付けている開発政策が、おかしいなと疑問を持った。
そこからアフリカやアジアの、土着のコミュティが持っている自立・共生的な生き方を
むしろ消費社会に向かっているヨーロッパ人の方が学び直さなければいけないのではないか、
一方的にヨーロッパなどの先進国が途上国に開発を押し付けるのではなく、
先進国が自分たちの行き過ぎた社会システムを変えていくことが
最終的に南北問題の解決につながっていくのだ、というふうに考えるようになった人物。”
* * *
なんと、レオ・レオニの絵本が題材に?

カタツムリの知恵と脱成長: 貧しさと豊かさについての変奏曲
中野 佳裕
コモンズ