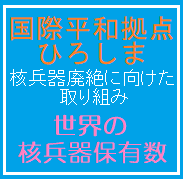参議院インターネット審議中継>
カレンダー2010年11月26日>
「予算委員会」の「会議の経過・発言者等」の3つのアイコンの真ん中(発言者)をクリック→
→発言者の一覧→上から8人目福島瑞穂みずほ(00:25ごろ~)
「障害者自立支援法改正法案について」(要約)
福島:なぜ総合福祉法(仮称)を作ることになっているのに障害者自立支援法改正法案なのか?
総合福祉部会で出されている4つの当面の課題こそ、政省令などで予算化していくことでできる思うが。
菅総理:段階を追って進めている。
福島:障害者自立支援法改正法案に障害当事者の多くの方が反対している。
障害者自立支援法の延命策になるのではないかと考えている。
総合福祉法(仮称)を作ることに全力を挙げるべき。
政省令で今の問題を解決すべきだと強く要請する。
障害者自立支援法の改正法案が成立しないよう社民党は全力を挙げていく。
カレンダー2010年11月26日>
「予算委員会」の「会議の経過・発言者等」の3つのアイコンの真ん中(発言者)をクリック→
→発言者の一覧→上から8人目福島
「障害者自立支援法改正法案について」(要約)
福島:なぜ総合福祉法(仮称)を作ることになっているのに障害者自立支援法改正法案なのか?
総合福祉部会で出されている4つの当面の課題こそ、政省令などで予算化していくことでできる思うが。
菅総理:段階を追って進めている。
福島:障害者自立支援法改正法案に障害当事者の多くの方が反対している。
障害者自立支援法の延命策になるのではないかと考えている。
総合福祉法(仮称)を作ることに全力を挙げるべき。
政省令で今の問題を解決すべきだと強く要請する。
障害者自立支援法の改正法案が成立しないよう社民党は全力を挙げていく。