
快調に更新を重ねこれで7日連続。達成感とともに調べると7日間はこれまでに2度あり、最高記録は9日間でした。こういう記録調べも、ちょっとW杯のようです。
“ワールドカップ実存主義”とは、8年前の98年、フランス大会の終了時にたどり着いた個人史で重要な“感覚”のこと。この時を境に私の毎日は、ほんの少しだけ変わりました。
またとてもくだらない話ですが、おそらく今日が、記すのにもっともふさわしい日ですので。
憶えていてよさそうなのはマリオ・ケンペス大活躍の78年アルゼンチン大会からだが、ディープ関東平野の農村に暮らす中3だった当時、野球や、洋楽ポピュラー、日本のフォーク、『宇宙戦艦ヤマト』などで満ち足りていた私は、地球の裏側でそんなことが行われていたとはまったく知らなかった。
82年スペイン大会は浪人生。ほとんどサッカーはわからなかったが、心ある周囲の者どもが騒ぐので、「レ・ミゼラブル!」の名実況で知られ、史上ベストゲームの呼び声高い西ドイツ:フランス戦はみた記憶があるものの、選手についてはジーコやプラティニくらいしかまだわかっていなかった。
マラドーナのための86年メキシコ大会は大学4年。教育実習で実家に帰っていたダメ学生になっていた私は、毎晩朝まで飲む日々から突然、いつもは寝る時間から中学生の朝練習につき合ったり午後もノックをしたりという一般の子どもまみれの毎日で、とても“神の子”をおがむ余裕などなかった。自転車で田んぼ道を帰りながら、ニュースで少しみただけの地球の裏のビッグイベントについて、中1男子と少し話した記憶だけある。
そして90年イタリア大会。臨時採用教員として中学校に勤めていた私は何もわからぬサッカー部の顧問になっていた。もちろん『サッカーマガジン』などを愛読する者どもと前夜のゲームについて話をしたり彼らにビデオを貸したりすることはあっても、マラドーナの指図にPK戦で敗れたイタリア同様、翌月に控えた自校開催の公式戦に向け、テレビの中の芝とは様子の違うそこらの土のピッチで、後のナカタと同年代で将来のW杯を夢見る坊主頭どもがボールを蹴るのにつき合って笛を吹いたりしていた。
だから、いまのようにW杯が楽しめるようになったのは94年のアメリカ大会が最初である。すでに零細塾自営+編集・執筆生活に入っていたため、昼間“リベロ”という立場と、弟と屋根に登ってマウントしたパラボラアンテナを最大限に利用して、決勝TMはほぼ全ゲームをみるほど。なおある物品雑誌のユニフォーム特集で仕事をやらせてもらったこともあり、この大会ではプレイヤーの名前もずいぶん知るようになっていた。
とはいってもこの頃までサッカーは、私にとってフィギュアスケートや柔道のようなもの。4年に1回の特別な季節だけ燃え上がって、あとは遠い世界だった。
だが、Jリーグやフジ+ジョン・カビラの『セリエAダイジェスト』などが始まり、塾のサッカー少年たちとストイチコフやフリット、バティステュータらの話もする機会も増えてきた。
そして、『ラ・マルセイエーズ』が響き渡った98年フランス大会。ジダン、ロナウドはいうに及ばず、4年越しのPKを決めたバッジョの溜飲、4年後の宿題を自らに課したベッカムのラフプレー、大統領になるのかチラベルト、そして史上屈指のオルテガの狼藉……。忘れられぬマロニエの季節の彩り。
さて、選手たちが次のW杯に向けて動き始めた時、経験したことのなかった愉しさに酔いしれながら35歳になろうとしていた私は、4年後の日韓に思いをめぐらしこう感じた。
「いったいあと何回W杯をみられるのだろう」
マラドーナ大会の前年にくも膜下出血で死んだ母は当時48歳。何の根拠もないが、人生80年時代といわれる中、母と同じくらいで命が終わることは十分考えられる。
では、大雑把に50歳で死ぬとしよう。とすれば63年生まれの私が生きるのは2113年頃まで。2006年のドイツは大丈夫だろうし、当時まだ決定していなかった2010年の南アフリカもOKか、しかしその次はわからないではないか。
その時の驚きといったらなかった。だらだらと続くかと思っていたさえない私の一生も、あとW杯3回か4回でなくなるかも知れない。アメリカからフランスまでの時間を考えると、W杯3、4回なんてあっという間だ。
一生が短く思えたのはこれが初めてである。それまでもポール・マッカートニーよろしく "Life is very short" と歌うことはあっても、それがリアルになったことはなかったと気づいた。
そして思った。こりゃおちおちしてられない。例えば、この本はもっと後になって読もうとかいってると生きている間に読めないかも知れぬ。人生にくだらぬ時間を生きている暇なんかないんだ。うっかりしてた。いやー、気づいてよかった。
とその時、ハイデガーの「時間は投射するものであり、同時に投射されるもの」という一節が頭に浮かんだ。そうかこれだったのか、80歳までと思って生きるより、50歳で終わると思って生きる方がずっといい。実存主義とはこういうことだったのか。
まったくの誤読かも知れないがそれはそれ。この時まで実存主義にしても、ただわかったような気がしていただけだったのだ。
マルティン・ハイデガーもドイツ人、今回のドイツ代表キャプテン、ミヒャエル・バラックもハイデガーも、何と偶然にも私と同じ誕生日である。もっともこっちは日本人だが。
はっきりいってこの時までの私は、自分がいつまでも死なないでいると思っている子ども同然だった。もちろんいつか死ぬと知ってはいたが、からだで実感はしていなかったのだ。最近小浜逸郎が「大人とは自分がそのうち死ぬことをわかっている存在」と書いているのを読んだが、その通りだと思う。
この、あとW杯3、4回という考えは自分のものとなり、古い友人と酒を飲む時に話したり、わけのわからぬことを抜かす若人どもに時々、「おめえら、自分がずっと生きてると思ってんだろう」とまくしたてたりしている。やつらもそんなことをいわれて困るだろうが、こういうことはいわないよりいっておいた方がずっといい。
そして、学生時代にK君がいっていたのの影響で老後にと思っていた三島の『豊穣の海』四部作をすぐ買いに行ったし、映画はその作家の重要な作品からみるようになった。そんな小さなことだが、私にとっては大きな変化だ。
いよいよ日本時間の今夜、フランス以降2回目のW杯が始まる。
詳しいことはまた後ほど。この地上最大の祭典を彩る神々の恵みについて、書きたいことは山ほどある。
今はまず、無事06年ドイツ大会をテレビの前で迎えられることを喜びたい。
そしてこの1ヶ月、本当はいつまでもいてほしいチームがピッチを去っていくのを、感謝の気持ちとともに見送る愛しき日々をじっくりと味わいたい。
生きることは愛するものを失うことであり、つまり私の“ワールドカップ実存主義”とは、失いつつ愛することを愛し生きることである。
(BGMは98年の発表のものを探し、私にとって97年の radiohead "OK, computer" と並ぶ90年代最重要アルバム、ブラジル・バイーヤ出身 carlinhos brown "omelete man"。これをきいた時の衝撃からもう8年とまた驚く。radiohead の英との決勝がみたい。カテゴリーは「身のまわり」のような気もするが、W杯なので「スポーツ」に)
“ワールドカップ実存主義”とは、8年前の98年、フランス大会の終了時にたどり着いた個人史で重要な“感覚”のこと。この時を境に私の毎日は、ほんの少しだけ変わりました。
またとてもくだらない話ですが、おそらく今日が、記すのにもっともふさわしい日ですので。
憶えていてよさそうなのはマリオ・ケンペス大活躍の78年アルゼンチン大会からだが、ディープ関東平野の農村に暮らす中3だった当時、野球や、洋楽ポピュラー、日本のフォーク、『宇宙戦艦ヤマト』などで満ち足りていた私は、地球の裏側でそんなことが行われていたとはまったく知らなかった。
82年スペイン大会は浪人生。ほとんどサッカーはわからなかったが、心ある周囲の者どもが騒ぐので、「レ・ミゼラブル!」の名実況で知られ、史上ベストゲームの呼び声高い西ドイツ:フランス戦はみた記憶があるものの、選手についてはジーコやプラティニくらいしかまだわかっていなかった。
マラドーナのための86年メキシコ大会は大学4年。教育実習で実家に帰っていたダメ学生になっていた私は、毎晩朝まで飲む日々から突然、いつもは寝る時間から中学生の朝練習につき合ったり午後もノックをしたりという一般の子どもまみれの毎日で、とても“神の子”をおがむ余裕などなかった。自転車で田んぼ道を帰りながら、ニュースで少しみただけの地球の裏のビッグイベントについて、中1男子と少し話した記憶だけある。
そして90年イタリア大会。臨時採用教員として中学校に勤めていた私は何もわからぬサッカー部の顧問になっていた。もちろん『サッカーマガジン』などを愛読する者どもと前夜のゲームについて話をしたり彼らにビデオを貸したりすることはあっても、マラドーナの指図にPK戦で敗れたイタリア同様、翌月に控えた自校開催の公式戦に向け、テレビの中の芝とは様子の違うそこらの土のピッチで、後のナカタと同年代で将来のW杯を夢見る坊主頭どもがボールを蹴るのにつき合って笛を吹いたりしていた。
だから、いまのようにW杯が楽しめるようになったのは94年のアメリカ大会が最初である。すでに零細塾自営+編集・執筆生活に入っていたため、昼間“リベロ”という立場と、弟と屋根に登ってマウントしたパラボラアンテナを最大限に利用して、決勝TMはほぼ全ゲームをみるほど。なおある物品雑誌のユニフォーム特集で仕事をやらせてもらったこともあり、この大会ではプレイヤーの名前もずいぶん知るようになっていた。
とはいってもこの頃までサッカーは、私にとってフィギュアスケートや柔道のようなもの。4年に1回の特別な季節だけ燃え上がって、あとは遠い世界だった。
だが、Jリーグやフジ+ジョン・カビラの『セリエAダイジェスト』などが始まり、塾のサッカー少年たちとストイチコフやフリット、バティステュータらの話もする機会も増えてきた。
そして、『ラ・マルセイエーズ』が響き渡った98年フランス大会。ジダン、ロナウドはいうに及ばず、4年越しのPKを決めたバッジョの溜飲、4年後の宿題を自らに課したベッカムのラフプレー、大統領になるのかチラベルト、そして史上屈指のオルテガの狼藉……。忘れられぬマロニエの季節の彩り。
さて、選手たちが次のW杯に向けて動き始めた時、経験したことのなかった愉しさに酔いしれながら35歳になろうとしていた私は、4年後の日韓に思いをめぐらしこう感じた。
「いったいあと何回W杯をみられるのだろう」
マラドーナ大会の前年にくも膜下出血で死んだ母は当時48歳。何の根拠もないが、人生80年時代といわれる中、母と同じくらいで命が終わることは十分考えられる。
では、大雑把に50歳で死ぬとしよう。とすれば63年生まれの私が生きるのは2113年頃まで。2006年のドイツは大丈夫だろうし、当時まだ決定していなかった2010年の南アフリカもOKか、しかしその次はわからないではないか。
その時の驚きといったらなかった。だらだらと続くかと思っていたさえない私の一生も、あとW杯3回か4回でなくなるかも知れない。アメリカからフランスまでの時間を考えると、W杯3、4回なんてあっという間だ。
一生が短く思えたのはこれが初めてである。それまでもポール・マッカートニーよろしく "Life is very short" と歌うことはあっても、それがリアルになったことはなかったと気づいた。
そして思った。こりゃおちおちしてられない。例えば、この本はもっと後になって読もうとかいってると生きている間に読めないかも知れぬ。人生にくだらぬ時間を生きている暇なんかないんだ。うっかりしてた。いやー、気づいてよかった。
とその時、ハイデガーの「時間は投射するものであり、同時に投射されるもの」という一節が頭に浮かんだ。そうかこれだったのか、80歳までと思って生きるより、50歳で終わると思って生きる方がずっといい。実存主義とはこういうことだったのか。
まったくの誤読かも知れないがそれはそれ。この時まで実存主義にしても、ただわかったような気がしていただけだったのだ。
マルティン・ハイデガーもドイツ人、今回のドイツ代表キャプテン、ミヒャエル・バラックもハイデガーも、何と偶然にも私と同じ誕生日である。もっともこっちは日本人だが。
はっきりいってこの時までの私は、自分がいつまでも死なないでいると思っている子ども同然だった。もちろんいつか死ぬと知ってはいたが、からだで実感はしていなかったのだ。最近小浜逸郎が「大人とは自分がそのうち死ぬことをわかっている存在」と書いているのを読んだが、その通りだと思う。
この、あとW杯3、4回という考えは自分のものとなり、古い友人と酒を飲む時に話したり、わけのわからぬことを抜かす若人どもに時々、「おめえら、自分がずっと生きてると思ってんだろう」とまくしたてたりしている。やつらもそんなことをいわれて困るだろうが、こういうことはいわないよりいっておいた方がずっといい。
そして、学生時代にK君がいっていたのの影響で老後にと思っていた三島の『豊穣の海』四部作をすぐ買いに行ったし、映画はその作家の重要な作品からみるようになった。そんな小さなことだが、私にとっては大きな変化だ。
いよいよ日本時間の今夜、フランス以降2回目のW杯が始まる。
詳しいことはまた後ほど。この地上最大の祭典を彩る神々の恵みについて、書きたいことは山ほどある。
今はまず、無事06年ドイツ大会をテレビの前で迎えられることを喜びたい。
そしてこの1ヶ月、本当はいつまでもいてほしいチームがピッチを去っていくのを、感謝の気持ちとともに見送る愛しき日々をじっくりと味わいたい。
生きることは愛するものを失うことであり、つまり私の“ワールドカップ実存主義”とは、失いつつ愛することを愛し生きることである。
(BGMは98年の発表のものを探し、私にとって97年の radiohead "OK, computer" と並ぶ90年代最重要アルバム、ブラジル・バイーヤ出身 carlinhos brown "omelete man"。これをきいた時の衝撃からもう8年とまた驚く。radiohead の英との決勝がみたい。カテゴリーは「身のまわり」のような気もするが、W杯なので「スポーツ」に)

















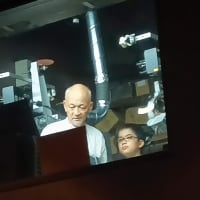








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます