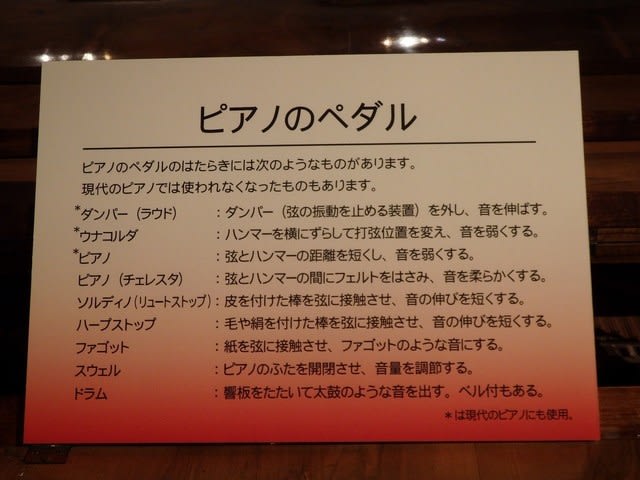いよいよ今週の土曜日です。
佼成ウィンドオーケストラ第144回定期演奏会!
https://www.tkwo.jp/concert/subscription/144.html
当日は4曲演奏されますが、リハ順では自分が最後なので朝はあわてずに出かれられます。アリガタイ(^^)
それでも余裕を持って到着し、控え室でのんびりしてましたが、折角なので1つ前のR・ジェイガーという人の「壁」という曲を見学させてもらいました。
いやあさすが佼成ウィンド、上手い!
そしてそれ以上に、ムズイ!!
おそらく各楽器の限界レベルで譜面が描かれているようです。
ちなみにこの曲は、グラスハープに人の声まで入っています。
聴き応えがあって通しで聴いてみたいですね!
いよいよ自分の参加する「トーンプレロマス55」。
リハは緊張する~!(笑)
指揮者の大井さんは穏やかに勧めながらも明確なビジョンを持っているので、分かりやすく的確な指示を出されます。
指示後の演奏もハッキリと良くなります。
そして解釈も岩城さんとは全然違う感じで(実際のところは良く覚えてないけど・・・)、今まで聴いたことないような「トーンプレロマス55」になるのではないでしょうか。
ちなみにV.ネリベルのシンフォニック・レクイエムが当日のトリですが、これも相当凄そうですよー!!
6月15日、まだ予定が決まってない方はぜひ池袋芸術劇場へ。
13時開場。14時開演です。
佼成ウィンドオーケストラ第144回定期演奏会!
https://www.tkwo.jp/concert/subscription/144.html
当日は4曲演奏されますが、リハ順では自分が最後なので朝はあわてずに出かれられます。アリガタイ(^^)
それでも余裕を持って到着し、控え室でのんびりしてましたが、折角なので1つ前のR・ジェイガーという人の「壁」という曲を見学させてもらいました。
いやあさすが佼成ウィンド、上手い!
そしてそれ以上に、ムズイ!!
おそらく各楽器の限界レベルで譜面が描かれているようです。
ちなみにこの曲は、グラスハープに人の声まで入っています。
聴き応えがあって通しで聴いてみたいですね!
いよいよ自分の参加する「トーンプレロマス55」。
リハは緊張する~!(笑)
指揮者の大井さんは穏やかに勧めながらも明確なビジョンを持っているので、分かりやすく的確な指示を出されます。
指示後の演奏もハッキリと良くなります。
そして解釈も岩城さんとは全然違う感じで(実際のところは良く覚えてないけど・・・)、今まで聴いたことないような「トーンプレロマス55」になるのではないでしょうか。
ちなみにV.ネリベルのシンフォニック・レクイエムが当日のトリですが、これも相当凄そうですよー!!
6月15日、まだ予定が決まってない方はぜひ池袋芸術劇場へ。
13時開場。14時開演です。