沖縄が好き、歌が好き、文化が好きというかたがきっと多く集まる
「沖縄の風」。
その上で歴史を知ることで、より一層深みが増すかと思うので、また皆
さんと今回も時間をさかのぼってみたいと思います。
私もたくさんの参考書に囲まれ、勉強できるので嬉しいさぁ~!
☆第三回目の旅 「ウチナーんちゅのDNA」☆
生きる・食べられる=「幸せ」だった古代の人々は、それが叶
えられるよう、
月、星、太陽に、
そして大地に海に神に、祈りを歌で捧げて生きてきました。
その時の「古謡」は、神人(かみんちゅ)達の歌から次第に住人へと歌
い継がれ、
歴史と共に上流階層の教養人によって創造された「古典音楽」と、
庶民の心から生み出された「民謡」へと芽吹き、カタチを変え増えて行
きます。
そして皆さんもよくご存知の通り沖縄は、『琉球』というひとつの王国
を築き、
主に中国・アジアとの交易が盛んになる王朝時代へと時を進めて行きま
す。
私が知る多くの歴史書の中に書かれているのが、その王朝時代
(14世紀以降~17・18世紀頃)交易の中で、三線は
中国より、そして舞はバリ・インドネシアから伝わったとされ、
そして島では古代の祭祀歌謡をあつめた「おもろさうし」が編纂され、
それらをミックスさせた琉球独特の、オリジナリティ溢れる古典芸能が
たくさん誕生していきました。
またこの時代には、守礼の門ができるなど、琉球文化は最盛期を迎えま
す。
その交易時に大活躍したのが、そうなんです!
歌三線、そして舞。
よく考えると現代ではありえないかも知れません。
なぜなら沖縄は、音楽と芸能を交易の重要なツールとして活用し、
いわゆる芸能ができる人は「国家公務員」だったからです。
音楽家からすれば、ステキすぎるお話ではありませんか?
だって、音楽で他国との交流を深め重要な役割を果たしてきたのですか
ら。。。。
誇りに思いますね~。
ということで、なぜにウチナーんちゅがこんなにも歌がそして踊ること
が好きなのか、
分かりましたよね。
そうです。私達のDNAには、しっかり組み込まれているようです
(笑)。
ちなみに余談ですが、中国から伝わってきた当初の三線は、
今ある三線よりもう少し大きかったようですよ。
当時のウチナーんちゅはきっと、小柄だったので、
現在のようなサイズに改良されていったのでしょうね。
text:しゃかりちあき
しゃかりオフィシャルサイト(言葉のかわりに心の歌を)
http://www.syakari.jp/

「沖縄の風」。
その上で歴史を知ることで、より一層深みが増すかと思うので、また皆
さんと今回も時間をさかのぼってみたいと思います。
私もたくさんの参考書に囲まれ、勉強できるので嬉しいさぁ~!
☆第三回目の旅 「ウチナーんちゅのDNA」☆
生きる・食べられる=「幸せ」だった古代の人々は、それが叶
えられるよう、
月、星、太陽に、
そして大地に海に神に、祈りを歌で捧げて生きてきました。
その時の「古謡」は、神人(かみんちゅ)達の歌から次第に住人へと歌
い継がれ、
歴史と共に上流階層の教養人によって創造された「古典音楽」と、
庶民の心から生み出された「民謡」へと芽吹き、カタチを変え増えて行
きます。
そして皆さんもよくご存知の通り沖縄は、『琉球』というひとつの王国
を築き、
主に中国・アジアとの交易が盛んになる王朝時代へと時を進めて行きま
す。
私が知る多くの歴史書の中に書かれているのが、その王朝時代
(14世紀以降~17・18世紀頃)交易の中で、三線は
中国より、そして舞はバリ・インドネシアから伝わったとされ、
そして島では古代の祭祀歌謡をあつめた「おもろさうし」が編纂され、
それらをミックスさせた琉球独特の、オリジナリティ溢れる古典芸能が
たくさん誕生していきました。
またこの時代には、守礼の門ができるなど、琉球文化は最盛期を迎えま
す。
その交易時に大活躍したのが、そうなんです!
歌三線、そして舞。
よく考えると現代ではありえないかも知れません。
なぜなら沖縄は、音楽と芸能を交易の重要なツールとして活用し、
いわゆる芸能ができる人は「国家公務員」だったからです。
音楽家からすれば、ステキすぎるお話ではありませんか?
だって、音楽で他国との交流を深め重要な役割を果たしてきたのですか
ら。。。。
誇りに思いますね~。
ということで、なぜにウチナーんちゅがこんなにも歌がそして踊ること
が好きなのか、
分かりましたよね。
そうです。私達のDNAには、しっかり組み込まれているようです
(笑)。
ちなみに余談ですが、中国から伝わってきた当初の三線は、
今ある三線よりもう少し大きかったようですよ。
当時のウチナーんちゅはきっと、小柄だったので、
現在のようなサイズに改良されていったのでしょうね。
text:しゃかりちあき
しゃかりオフィシャルサイト(言葉のかわりに心の歌を)
http://www.syakari.jp/










































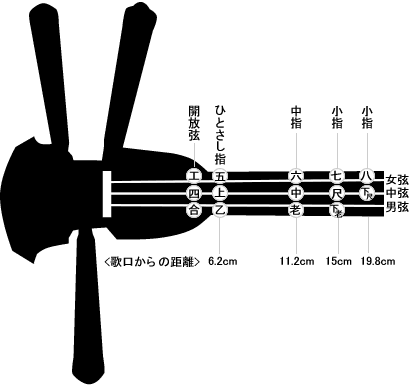




 )
)





 「すげー」
「すげー」

 」
」




 常連さんに聞いた正しい(?)肉そばの食べ方
常連さんに聞いた正しい(?)肉そばの食べ方






