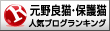また自省の意味を込めて、ハナとお別れしたときの話をさせて下さい。

ハナ17才の頃、家前の道路にて
それはハナが脳溢血の病魔から奇跡の復活を遂げた1年後のことでした。その日は夫婦で家に帰ったのが当時としては少し早めの19時。揃って帰宅したときは大抵3匹のお出迎えがあるのですが、それがないと、何となく胸騒ぎが走るものです。そのときも誰も(玄関まで)出てこない。そして胸騒ぎが的中、居間の窓側に倒れていたハナを発見したのです。
ハナは嘔吐物にまみれて横たわっていました。後でわかったのは、嘔吐物は当時絶不調だったテツのものだった。ハナは半分仰向けに倒れて、静かだったが目がうつろになって。でも脳溢血のときとは少し違う。いずれにしても、何か重大なことが起こっていることは明らかだった。

嘔吐物を拭き取ったが手足が動かず
テツも心配そう
しかし行きつけの病院は19時までで電話が繋がらず。何件か調べて、19時半まで受け付けていた少し遠くの病院に何とか診察をお願いしました。とりあえず抱いて行こうとハナを毛布に包んでいるときだった。ほんの一瞬だったけど、ハナがひきつけを起こしたのです。全身が力んで、白目を剥いて。本当に一瞬の出来事、直ぐに治まりました。
病院までの間、ハナは腕の中で少し元気を取り戻したようでした。病院に着いて診察のときは頭を上げるほどに。先生の診断は"低体温症"、「とにかく温めてあげて下さい」と。 重大に思っていた割には薬も何も出ないので、いろいろと状況を先生を伺っているとき、ほんの一瞬、診察台のハナがまたひきつけを起こしたのです。
ほんの一瞬だったけど、間違いなく先生も見た。だが妻も看護師も他の人間は気付かなかった。「先生今の・・・」と言いかけたとき、いやあ、大丈夫でしょう、と軽い一言が返ってきました。とにかく一晩温めて、様子を見て翌日にかかりつけの先生に診てもらってください、と。
自宅に戻るとハナはまた少し元気になって、いつものレトルトと牛乳を少しだけど自ら口に含みました。(結果的にこれが最後の食事となった。) それからはコタツで温めたり、抱いて温めたり。良くなれ良くなれと祈りながら。しかしハナは、無情にもまたあの痙攣に襲われたのです。今度は長く、4,5秒は続いたでしょうか。

自宅に戻ったハナ
テツが付き添って離れなかった

少しだけ自分で食べたけど・・
その晩ほど切ない思いをしたことはなかった。初めは温めれば治ると信じていた。しかし4,5秒だった痙攣はどんどん長くしかも頻繁になって、未明には15分毎に20秒も続くほどに。ハナは頑張って、痙攣に負けまいと意識を保っていました。撫でたり声をかけると安心したように目を細めて・・。 夜間の救急病院を調べると遠いがあることはある。でもどれほどのことをしてもらえるのか。一見診察への不信感、ハナに負担をかけたくない、いろいろな思いが錯綜して、結局いつもの先生の開院を待ったのです。

ハナを抱き続けた一晩、しかし様態は悪くなる一方で
病院はその日に限って混んでいました。アサイチのつもりが1時間も待たされて。ハナは、順番待ちの車内でついに意識を失ったようだった。窮状を聞いた先生が迎えに来てくれてようやく診察が始まったのは朝の10時、倒れたハナを発見してから15時間後のことでした。

順番待ちで抱き続ける中、ついにハナの意識がなくなった
診断は「敗血症」。白血球の値が8万を超えていた。即入院で抗生物質の投与開始。先生は言いました、「敗血症は時間との勝負、早く処置すればだいたい治ります。」

ハナ入院の前夜と朝
ご飯を催促するようであげても食べなかったテツとくも
**後編に続きます**
書き始めるといろいろな想いが蘇ってきて、またしても予定をはるかに上回る長さとなってしまいました。作文力のなさを痛感しています。この記事は後編(入院後のハナの闘病と保護者の反省)に続きます。

ハナ17才の頃、家前の道路にて
それはハナが脳溢血の病魔から奇跡の復活を遂げた1年後のことでした。その日は夫婦で家に帰ったのが当時としては少し早めの19時。揃って帰宅したときは大抵3匹のお出迎えがあるのですが、それがないと、何となく胸騒ぎが走るものです。そのときも誰も(玄関まで)出てこない。そして胸騒ぎが的中、居間の窓側に倒れていたハナを発見したのです。
ハナは嘔吐物にまみれて横たわっていました。後でわかったのは、嘔吐物は当時絶不調だったテツのものだった。ハナは半分仰向けに倒れて、静かだったが目がうつろになって。でも脳溢血のときとは少し違う。いずれにしても、何か重大なことが起こっていることは明らかだった。

嘔吐物を拭き取ったが手足が動かず
テツも心配そう
しかし行きつけの病院は19時までで電話が繋がらず。何件か調べて、19時半まで受け付けていた少し遠くの病院に何とか診察をお願いしました。とりあえず抱いて行こうとハナを毛布に包んでいるときだった。ほんの一瞬だったけど、ハナがひきつけを起こしたのです。全身が力んで、白目を剥いて。本当に一瞬の出来事、直ぐに治まりました。
病院までの間、ハナは腕の中で少し元気を取り戻したようでした。病院に着いて診察のときは頭を上げるほどに。先生の診断は"低体温症"、「とにかく温めてあげて下さい」と。 重大に思っていた割には薬も何も出ないので、いろいろと状況を先生を伺っているとき、ほんの一瞬、診察台のハナがまたひきつけを起こしたのです。
ほんの一瞬だったけど、間違いなく先生も見た。だが妻も看護師も他の人間は気付かなかった。「先生今の・・・」と言いかけたとき、いやあ、大丈夫でしょう、と軽い一言が返ってきました。とにかく一晩温めて、様子を見て翌日にかかりつけの先生に診てもらってください、と。
自宅に戻るとハナはまた少し元気になって、いつものレトルトと牛乳を少しだけど自ら口に含みました。(結果的にこれが最後の食事となった。) それからはコタツで温めたり、抱いて温めたり。良くなれ良くなれと祈りながら。しかしハナは、無情にもまたあの痙攣に襲われたのです。今度は長く、4,5秒は続いたでしょうか。

自宅に戻ったハナ
テツが付き添って離れなかった

少しだけ自分で食べたけど・・
その晩ほど切ない思いをしたことはなかった。初めは温めれば治ると信じていた。しかし4,5秒だった痙攣はどんどん長くしかも頻繁になって、未明には15分毎に20秒も続くほどに。ハナは頑張って、痙攣に負けまいと意識を保っていました。撫でたり声をかけると安心したように目を細めて・・。 夜間の救急病院を調べると遠いがあることはある。でもどれほどのことをしてもらえるのか。一見診察への不信感、ハナに負担をかけたくない、いろいろな思いが錯綜して、結局いつもの先生の開院を待ったのです。

ハナを抱き続けた一晩、しかし様態は悪くなる一方で
病院はその日に限って混んでいました。アサイチのつもりが1時間も待たされて。ハナは、順番待ちの車内でついに意識を失ったようだった。窮状を聞いた先生が迎えに来てくれてようやく診察が始まったのは朝の10時、倒れたハナを発見してから15時間後のことでした。

順番待ちで抱き続ける中、ついにハナの意識がなくなった
診断は「敗血症」。白血球の値が8万を超えていた。即入院で抗生物質の投与開始。先生は言いました、「敗血症は時間との勝負、早く処置すればだいたい治ります。」

ハナ入院の前夜と朝
ご飯を催促するようであげても食べなかったテツとくも
**後編に続きます**
書き始めるといろいろな想いが蘇ってきて、またしても予定をはるかに上回る長さとなってしまいました。作文力のなさを痛感しています。この記事は後編(入院後のハナの闘病と保護者の反省)に続きます。