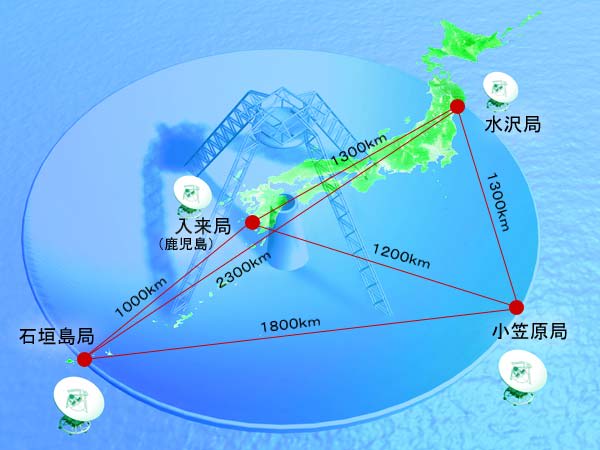NASAの冥王星探査機“ニューホライズンズ”の
望遠撮像装置“LORRI”による観測データから、
もっとも大きな謎のひとつ、冥王星の大きさが明らかにされたんですねー
その直径は2370キロで、
これまでの推定値より、やや大きな数値になったようです。
実は、この結果は推測されていたことだそうです。
今回の観測で分かったことは、
冥王星が、海王星以遠の天体の中で一番大きいこと。
これまで冥王星の大きさについては、議論が続いていたのですが、
やっと終止符が打たれたことになります。
大きくなるとどうなる
冥王星が少し「大きくなった」ことで、
これまでの想定よりも密度は少し低くなり、内部の氷の割合は高くなりました。
冥王星の大きさが数十年間も謎になっていた理由は、
大気という複雑な要素のためでした。
一方で、最大の衛星カロンには大気がないので、
地上の望遠鏡からでも簡単に直径が分かったんですねー
“ニューホライズンズ”の観測により、
これまでの値(直径1208キロ)が再確認することができました。
近づいて分かってきた冥王星の衛星たち
望遠撮像装置“LORRI”は、
冥王星の小さな衛星ニクスとヒドラにも焦点を合わせています。
ハッブル宇宙望遠鏡によって2005年に発見されたニクスとヒドラは、
ハッブルの能力を持ってしても、小さな光点にしか見えませんでした。
なので“ニューホライズンズ”が、
冥王星最接近を迎える最終週に行われる観測が待たれていたんですねー
ニクスの大きさは約35キロ、ヒドラは約45キロで、
表面がひじょうに明るいので、氷が存在しているのかもしれません。
また、さらに小さい衛星ケルベロスとステュクスの大きさについては、
今後送信されてくるデータを待つことになります。
カロンについては、さらに新しい画像が公開されています。
広く深い谷のような地形が明らかになっていて、
これはグランドキャニオンよりも大きいんだとか。
周囲に明るい物質が飛び散ったように見える、
衝突クレーターと思われる地形や、北極領域の暗く不思議な模様も見えています。
ライブ・コンピュータ・シミュレーション
NASAは“ニューホライズンズ”のライブ・コンピュータ・シミュレーション
“Eyes on Piuto”(英語のみ)をウェブ上で公開しています。
LIVEモードを選ぶと、
冥王星までの距離や“ニューホライズンズ”の速度、最接近までの時間などが、
リアルタイムで変化するようすを見ることができたそうです。
他にも、探査機がどの搭載機器を使用して、どの天体を観測しているかも分かるようですよ。
こちらの記事もどうぞ ⇒ 冥王星に氷の山脈を発見! 探査機“ニューホライズンズ”が最接近直前に撮影
望遠撮像装置“LORRI”による観測データから、
もっとも大きな謎のひとつ、冥王星の大きさが明らかにされたんですねー
その直径は2370キロで、
これまでの推定値より、やや大きな数値になったようです。
 |
| 冥王星と衛星カロン。望遠撮像装置“LORRI”による白黒の観測データに、 可視光・赤外線撮像装置“Ralph”によるカラーデータを合成したもの。 2つの天体の明るさや色の違いがハッキリと分かる。 |
実は、この結果は推測されていたことだそうです。
今回の観測で分かったことは、
冥王星が、海王星以遠の天体の中で一番大きいこと。
これまで冥王星の大きさについては、議論が続いていたのですが、
やっと終止符が打たれたことになります。
大きくなるとどうなる
冥王星が少し「大きくなった」ことで、
これまでの想定よりも密度は少し低くなり、内部の氷の割合は高くなりました。
冥王星の大きさが数十年間も謎になっていた理由は、
大気という複雑な要素のためでした。
一方で、最大の衛星カロンには大気がないので、
地上の望遠鏡からでも簡単に直径が分かったんですねー
“ニューホライズンズ”の観測により、
これまでの値(直径1208キロ)が再確認することができました。
 |
| 地球、冥王星、カロンの大きさの比較。冥王星は地球の18.5%、カロンは9.5%。 |
近づいて分かってきた冥王星の衛星たち
望遠撮像装置“LORRI”は、
冥王星の小さな衛星ニクスとヒドラにも焦点を合わせています。
ハッブル宇宙望遠鏡によって2005年に発見されたニクスとヒドラは、
ハッブルの能力を持ってしても、小さな光点にしか見えませんでした。
なので“ニューホライズンズ”が、
冥王星最接近を迎える最終週に行われる観測が待たれていたんですねー
ニクスの大きさは約35キロ、ヒドラは約45キロで、
表面がひじょうに明るいので、氷が存在しているのかもしれません。
また、さらに小さい衛星ケルベロスとステュクスの大きさについては、
今後送信されてくるデータを待つことになります。
カロンについては、さらに新しい画像が公開されています。
広く深い谷のような地形が明らかになっていて、
これはグランドキャニオンよりも大きいんだとか。
周囲に明るい物質が飛び散ったように見える、
衝突クレーターと思われる地形や、北極領域の暗く不思議な模様も見えています。
 |
| 7月12日に250万キロから撮影された衛星カロン。 |
ライブ・コンピュータ・シミュレーション
NASAは“ニューホライズンズ”のライブ・コンピュータ・シミュレーション
“Eyes on Piuto”(英語のみ)をウェブ上で公開しています。
 |
| “Eyes on Piuto”のトップページ。 冥王星とその背景にある衛星カロンに最接近する“ニューホライズンズ”(イメージ図)。 |
LIVEモードを選ぶと、
冥王星までの距離や“ニューホライズンズ”の速度、最接近までの時間などが、
リアルタイムで変化するようすを見ることができたそうです。
他にも、探査機がどの搭載機器を使用して、どの天体を観測しているかも分かるようですよ。
こちらの記事もどうぞ ⇒ 冥王星に氷の山脈を発見! 探査機“ニューホライズンズ”が最接近直前に撮影