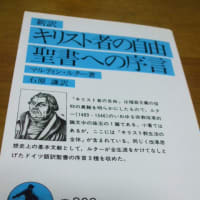つづき
新約聖書注解 日本基督教団出版局 を、まとめて。
『この部分は、文章の流れからすれば14節に結びつき、ローマ行きの願いとその必要を内容とする「感謝」の力強い締め括りをなす。
しかし同時にこれは、それに続く本論の主題の提示でもある。
したがって、この箇所の解釈は本書全体から最終的には明らかになるわけだが、またこれをどう読むかが本書全体の解釈に重大な意味を持ってくるともいえる。
「わたしは福音を恥としない」は、告白の響きを持つ宣言である。
1コリント書で語られているように、福音は「十字架の言葉」であり、「ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなもの」なのである。
しかし信仰は奴隷のみせしめの刑罰である磔刑に「神の力」を見る。
「神の力」は、ギリシアの世界では人間の力を越えた奇跡的な力を、ヘレニズムのユダヤ教では旧約の歴史の中に働く神の救いのわざを指すが、ここでは終末の時に世界(宇宙)に実現する神の支配を意味する。
この終末時に実現する神の支配は、恐れではなく「救いをもたらす」。
「救い」は個人的、内面的救済ではなく、最後の審判の際に断罪されることから免れることである。
これは信じる者すべて」に約束され与えられるものである。
「すべて」は文字通り救いが全人類に及ぶという救いの普遍性を語っている。
「信じる者」はこの普遍性を限定しない。
なぜなら信仰は律法遵守と対比され、いかなる意味においても人間側の救いの条件とはなり得ないからである。
救いは律法のわざや自己の功績に頼らない、それゆえ、ただ信じるすべての人間に与えられる。
それゆえ「信じる」とは、信仰箇条の受容に終わらず、終末時における神の支配の下に身をおく態度を言う。
パウロはすべての人間を、14節とは異なった二分法で「ユダヤ人をはじめ、ギリシア人」と表現する。
彼は明らかにユダヤ人を上位においている。
これを彼の民族的偏見と片付けることは簡単だが、ここには信仰義認という彼の福音理解と、神の救い歴史に連なるというユダヤ人としての救済理解との関連の問題が存在する。
信仰によって義とされるという福音が強調されればされるだけ、イスラエルに対してなされた神の救いの約束が揺らいでくるという否定し難い矛盾が出てくる。
神の契約に対する信義の問題である。
彼は三章と九章以下においてこの問題を直接扱っているが、ユダヤ人を上位におくのは、この神の救いのわざの連続性を真剣に受け止めているからである。
この福音によって全世界に啓示されているのは「神の義」である。
「義」はこなれた日本語ではない。
ディカイオシュネーというギリシャ語の置き換えである。
「義」には、正しい、正義あんどのほかに代用の意味があるが原語にはない。
逆に原語にが含意する、神の、また神とのあるべき関係というニュアンスは日本語の義にはない。
ディカイオシュネーは本書においては特別な鍵言葉であり、パウロ自身がこの言葉に一貫性を持たせているわけであるから、「新共同訳」ではほぼ一貫して「義」と訳している。
「神の義」は「神の救いの働き」とも訳し得るように、単に神の属性の一つとして憐れみ、愛、聖と同列に扱われたり、倫理的な意味での正義などと混同されてはならない。
それは神の救いのわざ、人間に対する賜物であり、その力を指す。
「義」は元来、法廷用語であったが、黙示文学的終末論においては神の契約に対する誠実を意味する。
この神の誠実が、神の民イスラエルの背信、さらには律法を守ることによって己の義をたてようとする人間の無知に対して、いずれも契約破棄となる断罪や黙認によってではなく、福音において貫かれるというのがこの宣言の語るところである。
神の義は本書の主題であり、本書の構造を成しており、その意味では本書全体から最終的には知られる。
パウロ自身の定義は3・21以下に展開されている。
それによれば、神の義は、神ご自身が義となり、信じる者を義とするという二重の構造を持っていることになる。
この神の力ある働きは、「初めから終わりまで信仰を通して実現される」。
信仰の原語はピスティスであるが、「義」の場合と同様に、本書の鍵言葉であるとともに訳し方についても注意を要する。
人間が主語の場合、信仰と訳しえるが、神が主語の場合、真実、誠実と訳すべきである。
原文は「ピスティスからピスティスへ」で、徹頭徹尾ピスティスによる、ということなのだが、これを神の真実と解する可能性が全くないわけではない。
カール・バルトはそのように訳している。
ルードルフ・ブルトマンはこれを実存的人間の決断にひきつけて解釈する。
いすれにせよ、問題は二者択一ではない。
パウロは両者を含み持つピスティスという語で考えている。
「信仰」は、単に神の存在を容認することや特定の教義を受容することではない。
それは、人間を救うという神の不変の決意であり、その神に全存在を賭けて信頼し続けることである。
パウロはディカイオシュネーとピスティスが最も簡潔な形で出てくる「正しい者は信仰によって生きる」をハバ2・4から引用する。
「新共同訳」の「神に従う人は信仰によって生きる」という旧約の訳は参考になる。
そもそも神との関係を抜きにして正とか聖など語れないからである。』
お祈りしますm(_ _)m
恵み深い天の父なる神さま
律法を守ることによってのみ己の義を立てようとする人間の無知を、
断罪や黙認によってではなく、
神さまの愛である恵みと赦しによって、
神さまの誠実が福音において貫かれるということに、心から感謝します。
こころから、ありがとうございます。
信じることによってのみ、義とされることを感謝します。
主イエス・キリストの御名によって、お祈りします。
アーメン
新約聖書注解 日本基督教団出版局 を、まとめて。
『この部分は、文章の流れからすれば14節に結びつき、ローマ行きの願いとその必要を内容とする「感謝」の力強い締め括りをなす。
しかし同時にこれは、それに続く本論の主題の提示でもある。
したがって、この箇所の解釈は本書全体から最終的には明らかになるわけだが、またこれをどう読むかが本書全体の解釈に重大な意味を持ってくるともいえる。
「わたしは福音を恥としない」は、告白の響きを持つ宣言である。
1コリント書で語られているように、福音は「十字架の言葉」であり、「ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなもの」なのである。
しかし信仰は奴隷のみせしめの刑罰である磔刑に「神の力」を見る。
「神の力」は、ギリシアの世界では人間の力を越えた奇跡的な力を、ヘレニズムのユダヤ教では旧約の歴史の中に働く神の救いのわざを指すが、ここでは終末の時に世界(宇宙)に実現する神の支配を意味する。
この終末時に実現する神の支配は、恐れではなく「救いをもたらす」。
「救い」は個人的、内面的救済ではなく、最後の審判の際に断罪されることから免れることである。
これは信じる者すべて」に約束され与えられるものである。
「すべて」は文字通り救いが全人類に及ぶという救いの普遍性を語っている。
「信じる者」はこの普遍性を限定しない。
なぜなら信仰は律法遵守と対比され、いかなる意味においても人間側の救いの条件とはなり得ないからである。
救いは律法のわざや自己の功績に頼らない、それゆえ、ただ信じるすべての人間に与えられる。
それゆえ「信じる」とは、信仰箇条の受容に終わらず、終末時における神の支配の下に身をおく態度を言う。
パウロはすべての人間を、14節とは異なった二分法で「ユダヤ人をはじめ、ギリシア人」と表現する。
彼は明らかにユダヤ人を上位においている。
これを彼の民族的偏見と片付けることは簡単だが、ここには信仰義認という彼の福音理解と、神の救い歴史に連なるというユダヤ人としての救済理解との関連の問題が存在する。
信仰によって義とされるという福音が強調されればされるだけ、イスラエルに対してなされた神の救いの約束が揺らいでくるという否定し難い矛盾が出てくる。
神の契約に対する信義の問題である。
彼は三章と九章以下においてこの問題を直接扱っているが、ユダヤ人を上位におくのは、この神の救いのわざの連続性を真剣に受け止めているからである。
この福音によって全世界に啓示されているのは「神の義」である。
「義」はこなれた日本語ではない。
ディカイオシュネーというギリシャ語の置き換えである。
「義」には、正しい、正義あんどのほかに代用の意味があるが原語にはない。
逆に原語にが含意する、神の、また神とのあるべき関係というニュアンスは日本語の義にはない。
ディカイオシュネーは本書においては特別な鍵言葉であり、パウロ自身がこの言葉に一貫性を持たせているわけであるから、「新共同訳」ではほぼ一貫して「義」と訳している。
「神の義」は「神の救いの働き」とも訳し得るように、単に神の属性の一つとして憐れみ、愛、聖と同列に扱われたり、倫理的な意味での正義などと混同されてはならない。
それは神の救いのわざ、人間に対する賜物であり、その力を指す。
「義」は元来、法廷用語であったが、黙示文学的終末論においては神の契約に対する誠実を意味する。
この神の誠実が、神の民イスラエルの背信、さらには律法を守ることによって己の義をたてようとする人間の無知に対して、いずれも契約破棄となる断罪や黙認によってではなく、福音において貫かれるというのがこの宣言の語るところである。
神の義は本書の主題であり、本書の構造を成しており、その意味では本書全体から最終的には知られる。
パウロ自身の定義は3・21以下に展開されている。
それによれば、神の義は、神ご自身が義となり、信じる者を義とするという二重の構造を持っていることになる。
この神の力ある働きは、「初めから終わりまで信仰を通して実現される」。
信仰の原語はピスティスであるが、「義」の場合と同様に、本書の鍵言葉であるとともに訳し方についても注意を要する。
人間が主語の場合、信仰と訳しえるが、神が主語の場合、真実、誠実と訳すべきである。
原文は「ピスティスからピスティスへ」で、徹頭徹尾ピスティスによる、ということなのだが、これを神の真実と解する可能性が全くないわけではない。
カール・バルトはそのように訳している。
ルードルフ・ブルトマンはこれを実存的人間の決断にひきつけて解釈する。
いすれにせよ、問題は二者択一ではない。
パウロは両者を含み持つピスティスという語で考えている。
「信仰」は、単に神の存在を容認することや特定の教義を受容することではない。
それは、人間を救うという神の不変の決意であり、その神に全存在を賭けて信頼し続けることである。
パウロはディカイオシュネーとピスティスが最も簡潔な形で出てくる「正しい者は信仰によって生きる」をハバ2・4から引用する。
「新共同訳」の「神に従う人は信仰によって生きる」という旧約の訳は参考になる。
そもそも神との関係を抜きにして正とか聖など語れないからである。』
お祈りしますm(_ _)m
恵み深い天の父なる神さま
律法を守ることによってのみ己の義を立てようとする人間の無知を、
断罪や黙認によってではなく、
神さまの愛である恵みと赦しによって、
神さまの誠実が福音において貫かれるということに、心から感謝します。
こころから、ありがとうございます。
信じることによってのみ、義とされることを感謝します。
主イエス・キリストの御名によって、お祈りします。
アーメン