ネット上の検索で、「山手線内回り外回りの名称を変えてもらう会」というグループがTwitter開設していることを知りました。
一番最近にツイート(発言)されたのが、2012年ですので、ここ数年は主だった活動をされていないようですが、このグループを含めて、山手線などの環状線の案内表記「内回り」「外回り」が分かりにくいので、何とかならないのか、という主張が多いようです。
そんなものなのですかねぇ。名古屋市の地下鉄名城線が環状化するにあたって、「内回り」「外回り」の案内表記をせずに、「右回り」「左回り」としているのは御存知の通りで、内・外は分かり難いから、と言う理由で、市バスの循環系統で用いられている「右(左)回り」としました。
私は、昔から山手線に慣れてますので、直感的に「内回り」「外回り」が分かりよく、「右(左)回り」と言われると、先ず頭の中で○を書き、その最高部となる地点を左へ行く方向を左回り、逆に右へ行くのが右回り。と脳内を整理しています。
なので、名城線の環状運転が始まった時も今もこの「左(右)回り」の表記が不満でいます。
しかるにこんな考えは私ぐらいで、名古屋の方は殆どが「左(右)回り」の方で納得されているそうです。
東京の山手線、東京駅から渋谷駅へ行こうとすれば、どちら回りがいいのか、私はすかさず「外回り!」と言えますが、この「外回り」が難しく、最近は電車の方向幕にも「品川・渋谷方面」と出るそうですね。LEDですので、走行地点で表示をどんどん変えて行きます。
これも最初の経験が後々まで残るの例で、東京の場合、国電と中距離電車を厳格に分けるのは、私が昭和40年代から50年代にかけて最初に触れた経験で、最近の方はJRの場合、国電と中距離電車の区別をされないらしい。
ところで、「内回り」「外回り」は環状線の複線で左側通行の場合はこうなるので、右側通行ですと当然逆になります。
韓国ソウルの地下鉄2号線は環状線。日本の山手線で言う左回りは「内線(ネソン)」、外回りは「外線(ウェソン)」とされています。
山手線の回り方の名称は、「ややこしい」と仰らずに、ローカルルールでこうだと認識していただくしかないと思います。
そんなに「内回り」「外回り」はややこしいのかなぁ。。。
ところで余談ですが、東京では「左回り」を「内回り」、「右回り」を「外回り」と呼ぶ倣ったおか、東急バスのある地区の循環系統で、一方通行の関係から、左回りなのに、外回りを大きくはみ出る内回りの系統がありました。
一番最近にツイート(発言)されたのが、2012年ですので、ここ数年は主だった活動をされていないようですが、このグループを含めて、山手線などの環状線の案内表記「内回り」「外回り」が分かりにくいので、何とかならないのか、という主張が多いようです。
そんなものなのですかねぇ。名古屋市の地下鉄名城線が環状化するにあたって、「内回り」「外回り」の案内表記をせずに、「右回り」「左回り」としているのは御存知の通りで、内・外は分かり難いから、と言う理由で、市バスの循環系統で用いられている「右(左)回り」としました。
私は、昔から山手線に慣れてますので、直感的に「内回り」「外回り」が分かりよく、「右(左)回り」と言われると、先ず頭の中で○を書き、その最高部となる地点を左へ行く方向を左回り、逆に右へ行くのが右回り。と脳内を整理しています。
なので、名城線の環状運転が始まった時も今もこの「左(右)回り」の表記が不満でいます。
しかるにこんな考えは私ぐらいで、名古屋の方は殆どが「左(右)回り」の方で納得されているそうです。
東京の山手線、東京駅から渋谷駅へ行こうとすれば、どちら回りがいいのか、私はすかさず「外回り!」と言えますが、この「外回り」が難しく、最近は電車の方向幕にも「品川・渋谷方面」と出るそうですね。LEDですので、走行地点で表示をどんどん変えて行きます。
これも最初の経験が後々まで残るの例で、東京の場合、国電と中距離電車を厳格に分けるのは、私が昭和40年代から50年代にかけて最初に触れた経験で、最近の方はJRの場合、国電と中距離電車の区別をされないらしい。
ところで、「内回り」「外回り」は環状線の複線で左側通行の場合はこうなるので、右側通行ですと当然逆になります。
韓国ソウルの地下鉄2号線は環状線。日本の山手線で言う左回りは「内線(ネソン)」、外回りは「外線(ウェソン)」とされています。
山手線の回り方の名称は、「ややこしい」と仰らずに、ローカルルールでこうだと認識していただくしかないと思います。
そんなに「内回り」「外回り」はややこしいのかなぁ。。。
ところで余談ですが、東京では「左回り」を「内回り」、「右回り」を「外回り」と呼ぶ倣ったおか、東急バスのある地区の循環系統で、一方通行の関係から、左回りなのに、外回りを大きくはみ出る内回りの系統がありました。













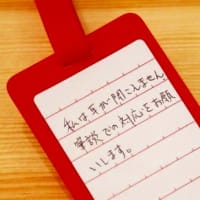
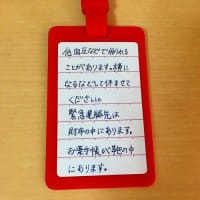





内回り、左回りとしか云い様がないじゃ無いですか。
品川、渋谷方面行と案内するのは良いですが、乗り場案内版はどう書くのかなァ。
いずれにしても、”イチャモン”としか思えません。
私は、内(外)回りの方が分かり良いので、名古屋の名城線でも個人的には使っています。
勿論人にいう時は、案内の通り右(左)回りにしていますが。
内(外)は、左側通行と右側通行とでは動きが逆になるので、そこが分かり難いという主張だそうです。
言うなれば、国際標準ではない。
国際的には、時計回り(反時計回り)という表現をするそうです。
「慣れ」のせいか、私にはそれはピンときません。
京阪沿線や学研都市線(片町線)や近鉄奈良線・近鉄大阪線といった大阪東郊の沿線から大阪駅や天王寺駅へは環状線に乗りますから
(兵庫県の阪神沿線から天王寺駅へ、南海沿線から大阪駅へ向かう場合も)。
大阪環状線の場合、東側・北側だと内回りは
ゆめ咲線(桜島線)直通の桜島行、
大和路線(関西本線)直通の加茂行、
阪和線直通の関空・和歌山行
があります。
大阪環状線・ゆめ咲線は来年から3ドア通勤型323系が投入されますが、323系投入後が気になります(103・201系の例から区快運用で大和路線の今宮~奈良~加茂も走ると思いますが)。
このようなものは、最初の取り掛かりが後々まで影響していると思います。
原体験として「内回り・外回り」で育った方はすんなりと理解できますが、他所から移られた方や、地元の方でも普段乗らない方だと「内回り・外回り」は理解し難いのではないかと考えます。
私は、子どもの頃から山手線を何度か乗り、「内・外回り」は当然のモノとして受け入れています。
2004年に名古屋市地下鉄の名城線が環状運転になった時、日本流の「内・外回り」、か名古屋市流の「左・右回り」にするか論議がありました。
結局は「左・右まわり」になり、山手線で育った私としては不満が残る結果に。
大阪環状線も山手線の経験がありますので、「内・外回り」は当然のものという感覚です。
その大阪環状線は、4扉ロングシートの車両から3扉、クロスシートの車両に変わるそうですね。
また「国電」の雰囲気が一つ消えます。
車体構造は3ドアとあって225系・521系第3次車・227系に準じますが、通勤型ということでトイレはなくロングシートです。
あくまでも都心を走り地下鉄的な近距離しか乗らない大阪環状線・ゆめ咲線の車両であり、
大和路線で運用される予定の時間帯は朝と夕方以降だけですから。
3ドアにしたのは221・223・225系とドア位置を合わせるからで、ホームドア設置対応ということです。
大阪環状線は全19駅、
ドアは1編成あたり24枚となるため1駅あたり往復48枚、
ホームドアは19×48=912枚は設置されると思います。
103系は全廃、201系は一部が6両化され大和路線普通・おおさか東線へ転出(放出~新大阪延長や103系の置き換えで)を除けば廃車予定でおそらく新興国へ輸出されるかも知れません。
4扉ロングシート国電好きな私としては残念なニュースでしたが、環状線にもホームドア設置ですか。
JR西日本は、本線での使用を想定して、3扉-4扉の双方に対応できるホームドアを検討していたのでは。
花博があったころ、帰りの京橋→大阪で乗った列車が、関西線用の黄緑色の103系。
天王寺発大阪行きでした。
黄緑色で、つかの間の山手線の雰囲気でした。