このところ、ラジオやテレビで話題が多くなっておりますが、歴史教科書の内容に変更があるそうです。
文部科学省が2月14日に公表した次期学習指導要領の改定案において、小中学校の社会科歴史教科書改定案で、歴史的な新事実が判明したことなどから、これまでの内容にあった「鎖国」、「聖徳太子」などの表記が消えるそうです。
livedoorNEWS:歴史教科書から「鎖国」が消されていた!「江戸時代=鎖国」はデタラメだった?
この鎖国と聖徳太子は、まさに日本人の誰もが認識されている常識となっています。
明治政府以前の徳川幕府政治では、鎖国制度を敷いていた、とされ幕末のペリー来航によって開国を迫られた、というもの。
聖徳太子は、いわずもがな以前の五千円と一万円紙幣に描かれた人物。
しかし徳川幕府では長崎に外国貿易を行う窓口を置き、後の明治新政府における外国人居留地に相当する「出島」の設置で外国との接点はありました。
そこで今日言われているような(常識とされる)鎖国というものではなかった。
聖徳太子も実際にはそんな名では呼ばれておらず、今後は「厩戸王(うまやどのおう)」だそうです。
「聖徳太子」の名は没後に称された名称である上、お札に描かれた人物像も本人のものではないらしいです。
他に、大化の改新とされる645年も、645年は「乙巳の変(いつしのへん)」で、この変によって基盤が整備され制度改革、すなわち「大化の改新」に至ったのだそうです。
なので、大化の改新は、645年の翌年、646年だそうです。
さらに、鎌倉幕府の成立も1192年ではないとされ、1185年とする教科書もあるそうです。
1192年は源頼朝が征夷大将軍に就いた年。
1185年頃から幕府の制度を整え始めたとのことです。
これらは既に発行されている教科書では改訂されており、早い話がこの教科書で教わった世代と、それより上の世代とでは常識感が違っています。
そもそも歴史というものは過去の事実の流れのようですが、実際には為政者の都合のいい内容に変えられてしまいます。
つまり、歴史は作るもの。
社会制度が変わると、変わった後の為政者によって変えられたりします。それは前政権の否定の内容になり、江戸時代の鎖国も誤った認識が現在まで続いているものです。
明治維新などという近世の出来事でもこんな感じなので、もっと古い、平安とかもっと前の出来事Hはどんなものか怪しいです。
これまで常識とされていることを、今後は「こうだ」とされても理解ができなかったり、ついていけないそうです。
歴史的新事実は時が経るにつれ、研究が進み、新たに分かってくるもので、有難いことに私は、柔軟なのか十分理解出来たり、ついていかれます。
文部科学省が2月14日に公表した次期学習指導要領の改定案において、小中学校の社会科歴史教科書改定案で、歴史的な新事実が判明したことなどから、これまでの内容にあった「鎖国」、「聖徳太子」などの表記が消えるそうです。
livedoorNEWS:歴史教科書から「鎖国」が消されていた!「江戸時代=鎖国」はデタラメだった?
この鎖国と聖徳太子は、まさに日本人の誰もが認識されている常識となっています。
明治政府以前の徳川幕府政治では、鎖国制度を敷いていた、とされ幕末のペリー来航によって開国を迫られた、というもの。
聖徳太子は、いわずもがな以前の五千円と一万円紙幣に描かれた人物。
しかし徳川幕府では長崎に外国貿易を行う窓口を置き、後の明治新政府における外国人居留地に相当する「出島」の設置で外国との接点はありました。
そこで今日言われているような(常識とされる)鎖国というものではなかった。
聖徳太子も実際にはそんな名では呼ばれておらず、今後は「厩戸王(うまやどのおう)」だそうです。
「聖徳太子」の名は没後に称された名称である上、お札に描かれた人物像も本人のものではないらしいです。
他に、大化の改新とされる645年も、645年は「乙巳の変(いつしのへん)」で、この変によって基盤が整備され制度改革、すなわち「大化の改新」に至ったのだそうです。
なので、大化の改新は、645年の翌年、646年だそうです。
さらに、鎌倉幕府の成立も1192年ではないとされ、1185年とする教科書もあるそうです。
1192年は源頼朝が征夷大将軍に就いた年。
1185年頃から幕府の制度を整え始めたとのことです。
これらは既に発行されている教科書では改訂されており、早い話がこの教科書で教わった世代と、それより上の世代とでは常識感が違っています。
そもそも歴史というものは過去の事実の流れのようですが、実際には為政者の都合のいい内容に変えられてしまいます。
つまり、歴史は作るもの。
社会制度が変わると、変わった後の為政者によって変えられたりします。それは前政権の否定の内容になり、江戸時代の鎖国も誤った認識が現在まで続いているものです。
明治維新などという近世の出来事でもこんな感じなので、もっと古い、平安とかもっと前の出来事Hはどんなものか怪しいです。
これまで常識とされていることを、今後は「こうだ」とされても理解ができなかったり、ついていけないそうです。
歴史的新事実は時が経るにつれ、研究が進み、新たに分かってくるもので、有難いことに私は、柔軟なのか十分理解出来たり、ついていかれます。













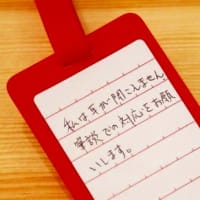
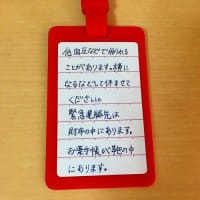





>「聖徳太子」の名は没後に称された名称である上、お札に描かれた人物像も本人のものではないらしいです。
>聖徳太子も実際にはそんな名では呼ばれておらず、今後は「厩戸王(うまやどのおう)」だそうです。
ネット辞書で調べりゃ分かることですが、「厩戸王」というのは創作上の名前ですよ。
法起寺塔露盤銘(706) 上宮太子聖徳皇
古事記(712) 上宮之厩戸豊聡耳命
日本書紀(720) 厩戸皇子
懐風藻(751) 聖徳太子
ロジックを考えれば分かることですが、日本史はいわゆる記紀をベースにして発展してきました(つまり日本史の歴史)。
現在の歴史学者の歴史思想(歴史観)として日本書紀や日本書紀の中心である「ミカド」を強烈に否定したい、という思想があるだけです。
聖徳太子はもちろん、この人物の死後29年後に送られた諡号です。今上陛下を「平成天皇」と呼ばないのと同じです。
その頃、そんな風には呼んでなかったはずだ!
一瞬、正しいように思います。では「厩戸王」はいつが初出なのですか?という問題になります。実態としてはごく最近、20世紀に入ってからの呼び方でしょう。
日本書紀のミカド、皇位を否定的に見る思想の流れからこの呼び方が「開発」されたに過ぎません。
もう一度書きますね。
「厩戸王」という表現はいつが初出なのですか?ごく最近、20世紀に入ってからの表現です。
こういうのは他にもあって
大和朝廷。ヤマト王権。ヤマト政権。
こういう言い換えを進めています。「王権」「政権」なんて単語が当時無かったことは明らかです。でもそう呼びたい、という思想がそう書かせています。飽くまでそれは執筆者の思想が現れたものに過ぎません。
その頃、そう呼んでなかった筈だ!
(そしてこう呼んでいた筈だ!)
一文目には説得力があります。しかし、二文目は完全な想像です。「彼」の死後、729年の諡号を否定して
彼の死後、20世紀に発明された「呼び方」が正しいというおのは随分おかしなロジックです。
王、大王、治天下大王、天子、帝、天皇。
いろんな呼び方はあろうが、そこには思想があるだけです。
ちなみに調べりゃ分かることですが「鎖国」という言葉はドイツ人の論文から取っているものです。明治維新云々という話とどう結びつくのか理解しかねる話です。
歴史書物の執筆者(歴史学者)は為政者ではありません。もちろん、文科省の制約の中で決めていることですから、その影響は受けるでしょう。