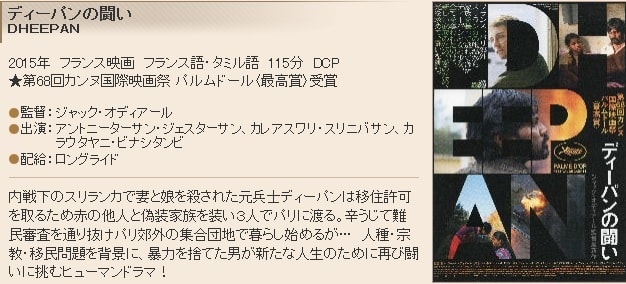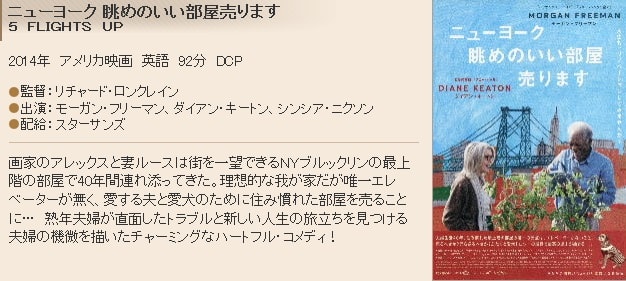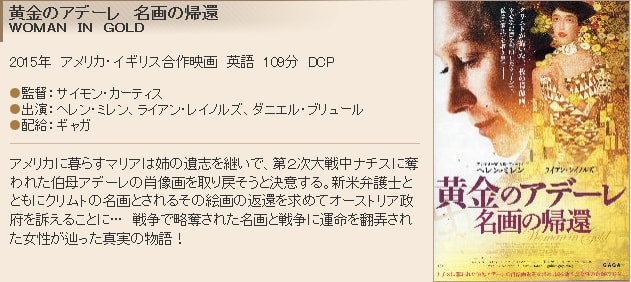秀作です。

映画の出だしの制作は難しいものです。
この映画は、ちょっと「いかがわしく」、「妖しい」雰囲気で始まります。
舞台が、デンマーク・コペンハーゲンのニューハウンなのに言葉が英語、何とも不自然で大なる違和感でした。

ニューハウンは、デンマーク・コペンハーゲンの中心、港町で一大観光地です。[私が撮りました]
若い画家夫婦のアイナーとゲルダは、まさにこのニューハウンのアパートに住んでいます。
ある日、女性のモデルが都合でその日は休んだので妻は夫にモデルの代わりを頼みます。
夫は、ストッキングをはき、ドレスを足に掛けます。その時彼に、不思議な感情がこみ上げます。
夫婦は、すっかりゲーム感覚で夫の女装を楽しみ、ついにそのままパーティーに出かけます。
LGBT(性的少数者)の名称が使われ始めたのはほんの最近です。
心と体の性の不一致(Gender Identity Disorder, GID)が社会的に認められるようになったのも最近のことです。
それらの定義や意味合いや使われ方はまだ一定=確立されていませんし、それらへの偏見と差別は現在も根強く、
容認されているとは到底言えません。
映画の舞台は、第一次世界大戦の傷跡もまだ癒えない1920年代、十数年後にはナチスが台頭し始める時代、
そうした人々は全く排除されました。
夫は、次第に自分の心の奥底から自分の本当の"女の性"(感情、精神、性意識)が彷彿とわき上がるのを感じます。
ゲーム感覚で夫の女装を楽しんだ妻は、次第に夫の変容に苦しみます。
夫(アイナー、リリー)を演じるエディ・レッドメインは『博士と彼女のセオリー』でアカデミー賞主演男優賞を受賞しました。
ぞっくとするほど美しいです。そして内面の苦しみ、女性の仕草、嬉しさ、恍惚感を見事に演じました。

妻(ゲルダ)は、夫のその変化、内面を初めは全く理解できませんでした。
しかし、彼女はその後もアイナーを支え続けます。
アイナーは世界で初めて男性器を切除し、膣を作る手術を選んだ人と言われます。
彼は、リリーとなって、膣成形手術を受けるのですが術後が悪くしばらくして亡くなります。
彼は、リリーの名前で日記を残し、この映画となりました。
妻を演じたアリシア・ヴィキャンデルはデンマーク人で2015年アカデミー助演女優賞を受賞しました。
アカデミー賞に冷淡な私ですが、エディ・レッドメインは主演男優賞、アリシア・ヴィキャンデルは主演女優賞と思います。
しかし、アイナーが映画のように美男美女でない、を考えると彼の苦しさ・どうしようも無さ・絶望感を感じます。
とても重いテーマですが、映画は「説教せず」、「極端な反対者を登場させず」、「啓蒙にならず」に描きました。
【8月29日鑑賞、併映は先日のブログ『キャロル』】















 引用
引用
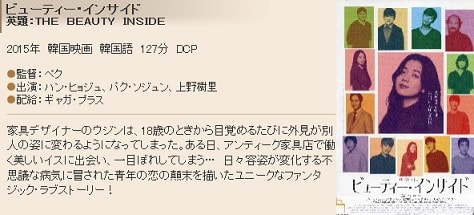




 【7月4日鑑賞】
【7月4日鑑賞】