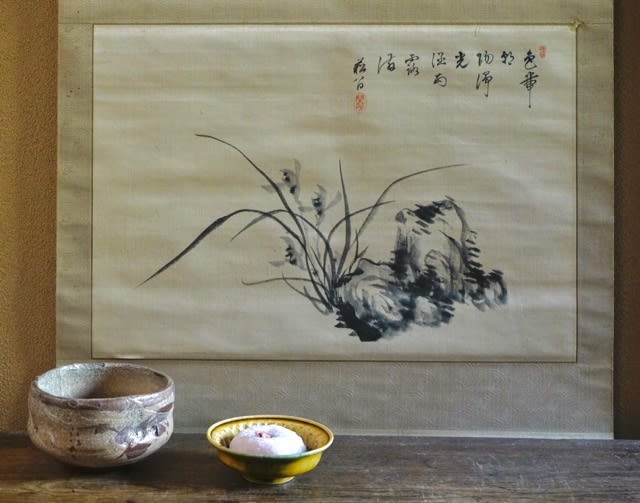花の盛りにも関わらず今週は生憎の雨続きで、いっその事雨を題にして吟行に出ようと思う。
BGMにブラームスのドイツレクイエムでも聴きながら花散り時の雨情に浸りたい。
我が庭を長く彩ってくれた種々の椿も終りに近く、最も遅咲きの乙女椿も雨中に散り始めた。
ーーーうす紅は紅より傷み易き色 雨降りがちな荒庭の花ーーー

庭も4月になれば椿桜に代わって山吹や藤が咲き出す。
その頃の庭を荒らす一番の懸念は筍で、あたり構わず出てあっという間に伸びるから油断出来ない。
食べるにも隠者は精々2〜3本で飽きるのだ。
我家と違って丹念に手入れされているご近所の花の山。

春の明るさの中にも小雨に濡れて深みのある山の色合いだ。
この奥に住んでいた顔見知りの老歌人ももう亡くなり、風情のあった庵も壊されてしまった。
ーーー花の色芽吹の色を宿したる 雨粒の降る世隠れの谷戸ーーー
鎌倉宮の参道脇の小流れのある路地。
紫木蓮の花の終りの朽ち色は耽美頽春の趣きで隠者好みだ。

その鎌倉宮の前を北に行くと新体詩の大詩人蒲原有明の旧居がある。
有明も行く春を惜しみながら、この辺の路地を散歩していただろう。
ーーー花屑の七種十色散り敷きて 惜春の路地詩人の旧居ーーー
八幡宮を抜けて若宮大路に出る頃には夕暮れて、段葛の桜並木にも灯が点る。

10年ほど前に段葛の老木と石垣を撤去し今風の舗装路に変えてからしばらくは花見にも行かなかったが、そこそこ若木が育って来てあと10年もすればまあ見られるようになるだろう。
だが現代風のLEDの灯籠は色も形も全く頂けない。
それだけでも昔の篝火か提灯に戻せない物か。
ーーー降る雨も散り行く花も金に染め 篝火猛る春の名残にーーー
子供達学生達に取ってのこの3年の自粛閉塞生活は心から気の毒に思う。
せめて本来の世界は遥かに明るく自由で美しくあるべきだと言う事を伝えてやりたい。
鎌倉もようやく息苦しいマスクが取れて、街並みも人々も麗しき春の彩りを取り戻して欲しい。
ーーー時満ちぬ善男善女こぞり出よ 花散る大路巫女舞ふ大社ーーー
©️甲士三郎