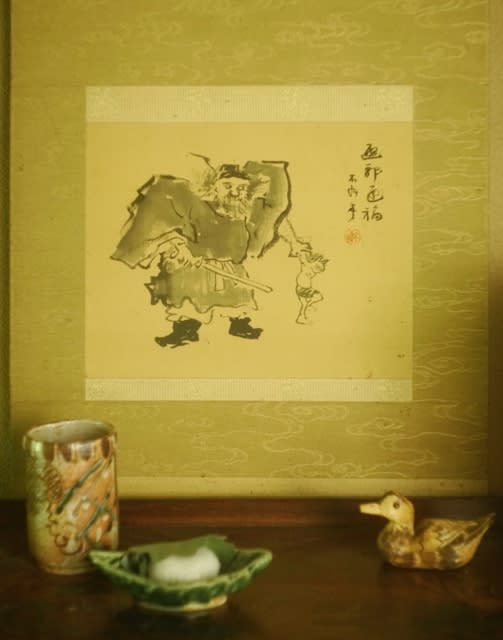鎌倉は今週から走り梅雨の気配だ。
長雨の時期は散歩の機会も減るので、せめて床飾の花を色々楽しみたい。
隠者流投入れ花は本来花入では無い物も色々使っている。
今年も6月に入る前から荒庭の紫陽花が咲き出している。

(炉鈞窯緑釉水差 清朝時代 古上野焼珈琲器 大正〜昭和頃)
咲き始めの白紫陽花は清々しく、小雨の中で重そうに首を垂れている姿にも風情がある。
紫陽花の品種は100種以上もあるようで、鎌倉でも多様な色や形が見られる。
他の色も含めて紫陽花には緑釉の花入が花の多彩な色を邪魔せずに良いと思う。
緑釉や青磁系統の花入はそれ自体の色が涼しげなので夏場には適している。
荒庭に咲いた金銀花を雨に散る前に摘んで来た。

(瀬戸井戸型花入 昭和初期)
金銀花を雨を思わせる井戸型の花入の取手に絡ませてみた。
取手の右にある小さな釣部も面白く、写真では雨中に打ち捨てられた井戸側の雰囲気が出た。
この花は先始めは白く散り際に黄色くなり、衆目を楽しませてくれる。
我が庭や近所のあちこちに咲いて、卯の花の後の谷戸を彩っている。
花首が弱いようで雨が当るとすぐ散ってしまうのだ。
花屋にまた梅花宇津木があったので、別の花入に合わせてみた。

(青磁徳利 李朝時代)
同じ宇津木も瓢箪型の李朝粉青器に入れると、先週の織部花入とは違う涼しげな姿になった。
少しひしゃげて傾いた徳利が如何にも幽陰の趣きだ。
こう言った所が何種か凝って活ける流派花とは正反対の、簡素な投入花の良さだろう。
古来から不教不伝、創意工夫の投入花は色々な花の楽しみ方が出来る。
その無技巧の工夫を考えている時間もまた花情の深まる時となろう。
他に夏の花器と言えば硝子器や染付が清涼感があって良いが、それらを使うのは梅雨明け以後のもっと暑い時期に取っておきたい。
©️甲士三郎