今週は山辺の緑が瑞々しく、朝の散歩が気持ち良い。
大きな山躑躅の咲く先から少し山に入る小径は、疫病の世から離れて清澄な気に満ちている。

草木は蒼然とした朝の大気に潤い、隠者は天霊地気を身に充満し、世界の安寧はかく保たれる。
今回の写真で使用したレンズはヘクトール7.3cm(以前紹介した90年前のエルンストライツ製)。
幻視に入り易く作られた製造数のごく少ないレンズで、隠者にとってはアーティファクト(聖遺物)だ。
どこかの庭から溢れた洋花が自生しているのも、鎌倉らしく頽廃的な美だと思う。
この辺に20年ほど前まで建っていた古い洋館の花だったかも知れない。
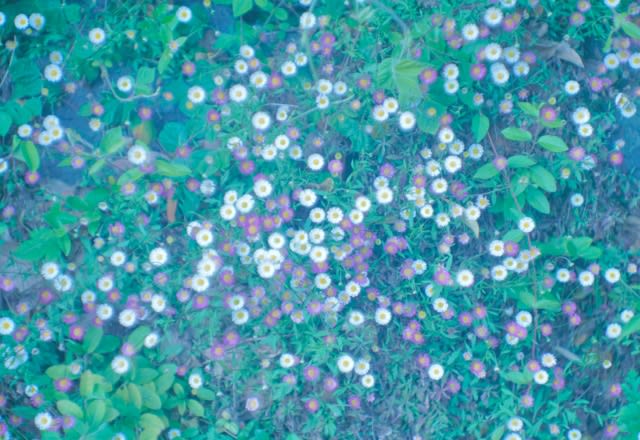
花も外来種園芸種は詳しくない(覚える気が無い)ので、名前は御勘弁願おう。
日本画家は和花さえ知っていれば務まるのだ。
本来西洋庭園を彩る華麗な花のはずが、異国の崩れた石垣の隙間に細々と咲いた風情が如何にも隠者好みだ。
これも多分卯の花に似た洋種の花だと思う。

今年も初夏の花が咲くのが、昔より2週間ほど早い。
10〜15日ほど春が短く夏が長くなり、私にとっては嫌な世界になっている。
その分短くなった春を惜しむ気持ちが深まったようだ。
ーーー春惜しむ舞の終りの急拍子ーーー(旧作)
山際の石段を登ると島津家の奥津城に出る。

昨年はここに一面の春紫苑が咲いていたのを茎立時に全部刈られてしまい、隠者の意識は否応無く夢幻界から濁世へ引き戻される。
それでも若草はまた伸びて来て、いつかまた一面の白花を咲かせる事だろう。
©️甲士三郎

























