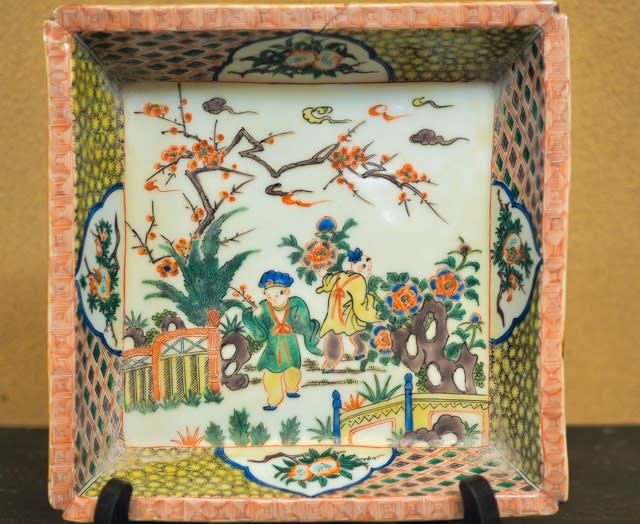春の花と言えば梅桜を思う人が多いだろうが、1月から4月まで三春に渡り楽しめるのは木偏に春と書く椿である。
鎌倉の山には野生の椿が多く自生していて、その蜜は鳥獣達の春窮の時期に貴重な栄養となっている。
山際の道などで急に頭上から花が落ちて来たら、大抵が鳥か栗鼠の仕業だ。
近所の家々の庭も多種の椿が咲き継ぎ、早春の探索者の眼を飽きさせない。
---鳥獣に舐め尽くされる椿山---

鎌倉も奥まった谷戸の小径に散り敷く椿は行く春の標となり、小流れに溜まる散花を眺めしばし佇むなら、流水の音と光はすでに夢幻界からの物だと知れるだろう。
夢幻の楽園の扉は望む者には随所に開いているのだが、残念ながら見えない人には一生見えはしない。
まあ余計な話になるが、隠者流では夢幻界の扉の発見は「観応」と言い初学に当たる。
中級の「観想」は扉を入ってから自分なりの楽園を想い描き建立する部分となるだろう。
上級の「観自在」は不教不伝、不立文字なので、一応上級隠者の私でも語れない。

前述のように椿は花期が長く夏の木槿や冬の山茶花と共に庭の花木として、また花持ちが良く投入れ花として、古来より日本人の生活文化と共にあった。
隠者ならこの三種の花木に加えて牡丹、菊、長春花(薔薇)で後庭の四季を完結させたい。
昔の茶庭(露地)には花物を植えず寒中三友(松竹梅)や桜紅葉は前庭門脇に配し、床に活ける花は客に見えぬ後庭に配置するのが基本で、席入りで始めてその花を見せる趣向だったのだ。
今では自宅で茶会を開くような家は絶滅し殆どの庭は洋風に作っているが、古人達の努力の結晶である伝統様式美を凌駕するような庭はあまりに少ない。
我が荒庭の土地は歴とした鎌倉時代の永福寺僧房跡なので、幻視するまでもなく数百年の荒廃の中を生き残った古い種の椿が息づいている。
椿は首から落ちるから縁起が悪いとか言うのは江戸末期からの俗信で、武家や公家に椿を嫌った由縁などは無く、武士の故地である鎌倉にも至る所に咲いている。

(宝戒寺裏の草庵)
こんな家に暮らすのが日本の文化を満喫するには最適だろうが、ひと昔ならどこにでもあったような普通の日本家屋と庭が現代では貴重になってしまった。
この春陽遍く花咲き鳥歌う谷戸の散歩道は、観光ルートからは少し外れているので静かで良い。
古び行く谷戸の小径は決して古びない花鳥達の新たな命によって、また今年も隠者の耳目を楽しませてくれる。
©️甲士三郎