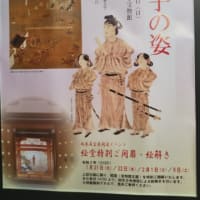今日はいじめシンポジウムを聴講に行きました。
講演は大阪樟蔭女子大学学長の森田洋司先生で、内容はとてもいいものだったと思います。
今では一般的に知られるようになったいじめの構造-たとえば傍観者の存在がいじめを増幅させるというようなことも、この先生が提唱者で、この分野の学者さんとしては第一人者であるということでした。
いじめはどこの国でもありえる現象ですが、欧米では中学生になると傍観者より仲裁者が増えるのに対し、日本においてはその逆であるため、いじめは長期・陰湿になっていくとのこと。
いじめは力関係バランスをうしなったときに人や地位とは関係なく起き、当事者同士の関係修復だけでなく目には見えない被害者の心の回復にもっとも心を割くべきだと主張されていました。
また、個人においては家庭や社会での役割意識を持たせることで自己肯定感を養い、コミュニケーション能力や社会性を培い、社会においては市民性意識を持って地域や集団が一体となっていじめのない社会を作り出していかなければならないと言われていました。
いじめは社会病理の一面を表しているものです。
最近起きるいじめの質の悪さが現代社会をそのまま反映しているといえるかもしれません。
講演やその後のパネルディスカッションの中で何度も出てきた【自己肯定感】という言葉。
これ、糖尿病医療の心理的問題の中でもよく出てくる言葉です。
結局は、医療の現場であっても教育の現場であっても、共通の課題があるということですね。
今、スクールカウンセラー設置が義務づけられたり、相談システムも充実し、社会資源は豊富になってきて、いろいろと配慮をされるようになりました。
でも子どもたちの心はそれとは反比例するかのように病んでいきます。
表情のない子どもたち、感情を持たない子どもたち、感情を表現できない子どもたちが増えています。
本来子どもが持っている子どもらしさを取り戻して欲しいといつも思います。
(これもまたエンパワメントでしょうか?)
今日のシンポジウム、内容はよかったと思うのですが、4時間半のうち半分は講演、半分がパネルディスカッションでした。
同じような構成で定例会を行っている立場として、もう少し構成やプログラムを考えてほしいと思いました。
長すぎる講演は、演者が最も言いたかったことは何なのかがよくわからなくて、パネルディスカッションも保護者、教師、行政それぞれの立場で意見を言われていたようなのですが、家庭、学校現場、行政、それぞれに取り組むべき課題があるというのは理解できますが、今回のような総論的な話の中で一緒に議論してまとめることが難しい気がしました。
本当は事例検討などを盛り込んだ方が聴講者にはよりわかりやすいのではないかなあと思ったりしました。
そうしてみるとVOXでお話をされる先生はコンパクトにまとめられてとてもわかりやすい。
時間もちょうどいいのかもしれませんが(40分程度)、いつも質の高い講演を聴かさせてもらっているのだなあと改めて思いました。
…でも森田先生はホンマにお年の割にはきれいな聞きやすい声で、しかも熱血漢で、いい先生だなあと思いました。
いつか本を読んでみたいと思いました。
(でも本はちっとも進まない人なので…)
せっかく取得した社会福祉士の資格なので、ボランティアでもいいから地域で子どもたちとかかわれる機会があればいいなあと思うのですが…そういうチャンスも勉強の場も見つけるのはなかなか難しいですね。
今日、ポストに精神保健福祉士の受験資格を取るための通信課程の入学案内が届いていました。
来年はこっちの受験資格取得に向けてがんばるぞ~!
講演は大阪樟蔭女子大学学長の森田洋司先生で、内容はとてもいいものだったと思います。
今では一般的に知られるようになったいじめの構造-たとえば傍観者の存在がいじめを増幅させるというようなことも、この先生が提唱者で、この分野の学者さんとしては第一人者であるということでした。
いじめはどこの国でもありえる現象ですが、欧米では中学生になると傍観者より仲裁者が増えるのに対し、日本においてはその逆であるため、いじめは長期・陰湿になっていくとのこと。
いじめは力関係バランスをうしなったときに人や地位とは関係なく起き、当事者同士の関係修復だけでなく目には見えない被害者の心の回復にもっとも心を割くべきだと主張されていました。
また、個人においては家庭や社会での役割意識を持たせることで自己肯定感を養い、コミュニケーション能力や社会性を培い、社会においては市民性意識を持って地域や集団が一体となっていじめのない社会を作り出していかなければならないと言われていました。
いじめは社会病理の一面を表しているものです。
最近起きるいじめの質の悪さが現代社会をそのまま反映しているといえるかもしれません。
講演やその後のパネルディスカッションの中で何度も出てきた【自己肯定感】という言葉。
これ、糖尿病医療の心理的問題の中でもよく出てくる言葉です。
結局は、医療の現場であっても教育の現場であっても、共通の課題があるということですね。
今、スクールカウンセラー設置が義務づけられたり、相談システムも充実し、社会資源は豊富になってきて、いろいろと配慮をされるようになりました。
でも子どもたちの心はそれとは反比例するかのように病んでいきます。
表情のない子どもたち、感情を持たない子どもたち、感情を表現できない子どもたちが増えています。
本来子どもが持っている子どもらしさを取り戻して欲しいといつも思います。
(これもまたエンパワメントでしょうか?)
今日のシンポジウム、内容はよかったと思うのですが、4時間半のうち半分は講演、半分がパネルディスカッションでした。
同じような構成で定例会を行っている立場として、もう少し構成やプログラムを考えてほしいと思いました。
長すぎる講演は、演者が最も言いたかったことは何なのかがよくわからなくて、パネルディスカッションも保護者、教師、行政それぞれの立場で意見を言われていたようなのですが、家庭、学校現場、行政、それぞれに取り組むべき課題があるというのは理解できますが、今回のような総論的な話の中で一緒に議論してまとめることが難しい気がしました。
本当は事例検討などを盛り込んだ方が聴講者にはよりわかりやすいのではないかなあと思ったりしました。
そうしてみるとVOXでお話をされる先生はコンパクトにまとめられてとてもわかりやすい。
時間もちょうどいいのかもしれませんが(40分程度)、いつも質の高い講演を聴かさせてもらっているのだなあと改めて思いました。
…でも森田先生はホンマにお年の割にはきれいな聞きやすい声で、しかも熱血漢で、いい先生だなあと思いました。
いつか本を読んでみたいと思いました。
(でも本はちっとも進まない人なので…)
せっかく取得した社会福祉士の資格なので、ボランティアでもいいから地域で子どもたちとかかわれる機会があればいいなあと思うのですが…そういうチャンスも勉強の場も見つけるのはなかなか難しいですね。
今日、ポストに精神保健福祉士の受験資格を取るための通信課程の入学案内が届いていました。
来年はこっちの受験資格取得に向けてがんばるぞ~!