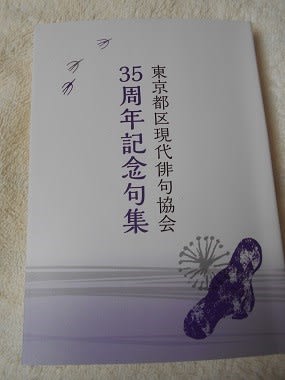
『東京都区現代俳句協会35周年記念句集』
編集人:佐怒賀正美、発行人:松澤雅世
平成30年3月1日発行 頒価2000円
この句集は187人が12句ずつ載せているから合計2244句を収録。読みごたえがある。小生がおもしろいと思った句にコメントをつける。
草踏んで夏のはじめが柔かい 白石みずき
初夏の草を踏んで柔かく感じたのであるが、そのように通り一篇に書かなかったことで風合を得た。この技を極端につかうと嫌味が出るがこの句は節度がある。
寂光の寺の雀と福寿草 進藤清能
「寂光」なる歯の浮きそうな語彙を絶好の場面で使った。雀と福寿草の取り合せがいいことが危ない言葉を生かした。
蒲の穂の圧倒的な現実よ すずき小柚子
「蒲の穂」はフランクフルトソーセージのような形で熟すとぼろぼろ崩れる。羽毛というか種が飛び立つ。飛ばないものは崩れて綿と見紛うほど散乱する。「圧倒的な現実」という措辞はこの不可思議な物ゆえ決まっている。この措辞が俳句で可能とはこの句を見るまで考えもしなかった。
あちらからも霧で見えぬかもしれぬ すずき小柚子
飯島晴子の「さつきから夕立の端にいるらしき」を思った。両者とも霧を大きな塊のように見ていることがおもしろい。この作者の感性には脱帽。
冬仕度庭先の椅子折りたたむ 鈴木淳一
庭に芝がありそこに出ていた椅子か。そこに注目したことで向こうに広がる野ないし森の蕭条としたさまを感じる。凝らずに滋味を出している。
蝶に鱗粉セシウムに着る防護服 鈴木光子
蝶の鱗粉は手に白く残るし匂いもあるが、セシウムは見えないし匂いもなく怖い。蝶が鱗粉を持つのは必須であるが防護服はセシウムを撥ね付ける意図。これぞ二句一章の妙味。
着ぶくれてマンハッタンの灯に噎ぶ 鈴木光子
「灯に噎ぶ」はオーバーな表現なのだがこの文脈の中でそう突出しているように思えない。それはマンハッタンという語感のリズムと季語の効き目ゆえか。
跳び箱を跳ぶ夏山を越えて跳ぶ 関戸信治
子供が跳び箱を跳ぶさまをローアングルで撮影している感じ。「跳ぶ」が3回に「越え」があり子供の活力をいきいきと出した。読んでうきうきする。
鉛筆を置けば木の音山眠る 関根瑶華
置いたとことも木の机か。山は木々の生えているところであり鉛筆の出どころ、郷愁が背後にある。
朝寒や猫背で降りる螺旋階 曽我部東子
実際は猫背でなく自嘲かもしれぬがいかにも階段を下りるさま。「朝寒」ゆえ「猫背」が見えるのである。
冬蝶の裂けたる羽の吹かれをり 高橋透水
羽が吹かれているだけなら凡百の句に紛れるところを「裂けたる羽」と言ったことで抜きん出た句になった。踏み込んで見ることで自分の世界を獲得した好例。
外人墓地石の聖書に蜥蜴這ふ 髙原信子
前の句もそうだが一句の要は中七にあることが多い。「石の聖書」ゆえ「蜥蜴」が見えるのである。ただし「石の聖書を蜥蜴這ふ」のほうがいいと思うが。
木の実降るシベリア俘虜記書棚から 竹内實昭
本棚からシベリア俘虜記を手に取った。戸外は木の実が降っている。当地の木の実もこんなものだったか、いや、違うだろう、もっと凄まじいだろうと思いを馳せている。
棚田ただ風の穭となりしまま 田中靖人
稲がなくなってしまった棚田はさびしい。平地の田んぼよりわびしい。それをうまく言葉にした。
島小春プレス一瞬たこせんべい 近田吉幸
「プレス一瞬たこせんべい」には手を打った。簡潔にあれができるさまを活写している。「島小春」は季語を説明しすぎている。もっとゆっくり季語を配すればさらにいい。
産声や桜の幹に噴く一花 次山和子
上五を季語以外の物のや切れで作るのは至難だがこの「産声や」は大胆にしてところを得ている。「桜の幹に噴く一花」の精度のよさによる。桜の精気を得て産まれた子である。
生涯を群れず泰山木の花 次山和子
独りで吟行に行くという作者なのだろう。飯島晴子を彷彿とさせる。この季語に対して「生涯を群れず」はユニーク。泰山木の花は大きくて桜と違って孤高なたたずまい。
白服の胸を開いて干されけり 対馬康子
この白服は海軍軍人のものではないかと思うとぞくぞくする。肉体のない衣服の胸に着目するのは恋情であり方恋の雰囲気も濃厚で胸を締め付けられる。
菜畑の奥に廃業ラブホテル 土屋秀夫
菜の花に飛ぶ蝶のように男女が睦んだ施設が廃墟。性は命を謳歌することであるがこちらの菜の花はいきいきとしている。対比の妙。
なんだ坂こんな坂神楽坂秋 角田晴俊
坂がそう急でない神楽坂ゆえおもしろい。したがって言葉遊びと思った「なんだ坂こんな坂」がしっくり来る。地元を愛する気分をよく出している。
父と子と無口な酒やだだ茶豆 寺内由美
上五中七はよく書かれるところかもしれないが季語の「だだ茶豆」が秀逸。これは枝豆用の大豆のことだがこの音感ゆえに俄然華やぐ。
神仏混然とあり田水沸く 寺町志津子
たとえば埼玉県飯能市の「竹寺」は鳥居や注連縄があり神仏習合。このように日本各地に神仏分離を免れた寺(神社)が存在する。寺と神社を当然のように使い分けるわれらの心性の曖昧さを絶妙の季語で浮彫にした。
男坂下り夜店に紛れけり 戸田徳子
下ったのが作者でなく異性と読んでおもしろい内容。作者が女坂をゆっくり下っていて見逃してしまった。せっかくもっと仲良くなれるチャンスだったのに。
大阿蘇の闇の底なる草泊り 戸田徳子
いま「草泊り」が行われているかどうか、懐かしい習わしである。阿蘇ゆえに「闇の底なる」を実感する。
川下りしてもう一度花の中 富田敏子
花見の句としてユニーク。舟に乗る前地上で桜を見たのだろう。舟で下って行くと両岸に桜がせり出すようなところを通る。豪華である。
綿虫の体温が集まっている 富田敏子
綿虫が集まっているのを「体温が」と言った。一匹一匹の熱量がさほどとは思わないがこう書くことで一匹一匹のはかない命が見えるのである。綿虫の一物俳句として出色。
夕焼やばあば出来たよ二十跳 長尾幸子
俳句で孫を書くのは御法度だがこれは孫という言葉を使わずに書いて成功。子供の言葉としたのは巧い。
きんつば十個箱にぴったり昭和の日 中内火星
まずこの季語に「きんつば」はぴったり。おまけに箱に「ぴったり」入っている。過不足ない出来。
白靴やジャズの流れる港町 中川枕流
横浜か神戸か、函館か。ジャズという軽快な音楽にこの季語はどんぴしゃ。うまいハーモニーである。
降る雪も障りもかすか湯を沸かす 長久保通繒
人により閉経の歳はさまざまであろうが「障りもかすか」で五十を越えている感じ。若干の寂しさにかすかな雪が降る。うまく心境を出している。「湯を沸かす」も巧い。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます