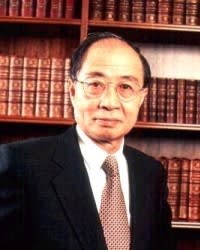オーサ・イェークストロムさんと彼女の著作
今朝NHKの7時からのニュースで「外国人の見た日本」を話題にした。
そこでアナウンサーが当然のように「目線」「目線」を連発しテロップも「目線」と出た。
NHKだけでなく信頼できると思っていた作家さえも「目線」と書くようなありさまである。
外国人の一人として登場したスウェーデン出身のオーサ・イェークストロムさん(31)がきちんと「視線」と言ったとき全身に涼しい風が吹いたような気がした。
北欧美人漫画家をかのジャンヌ・ダルクのように思った。
「目線」が流行りはじめたころ藤田湘子はこの言葉をことのほか嫌った。湘子のあと鷹を継いだ小川軽舟も当時、違和感があり自分からは使いたくない、と言った。
鷹は正しい言語感覚で主宰のバトンタッチが行われたと深く満足したのだが、われら視線派はどんどん劣勢になっている。
外国から来て日本文化を学ぼうとする優秀な人に正しい日本語を引き継いでいってほしい。大相撲も強さの核はモンゴル勢である。
大相撲も日本人が軟弱で、日本語(和語)もまた下手をするとわれわれ日本ネイティヴが損ねているようなありまさまだ。
NHKは日本代表放送みたいな顔をして新手の妙な言葉に飛びついて悪貨が良貨を駆逐するようなことをやっている。
俳句の読みではときどき変なところで切って気になる。
こんど鷹主宰にお目にかかったらまだ視線派であることを確認したい。
「いや、私も目線でいいと思いますよ」などといった発言を聞いたら鷹を辞めるかもしれない。
主宰と湘子と視線についてなつかしみたいなあと思った朝である。
オーサ・イェークストロムさん、正しい和語を学んでいってください。