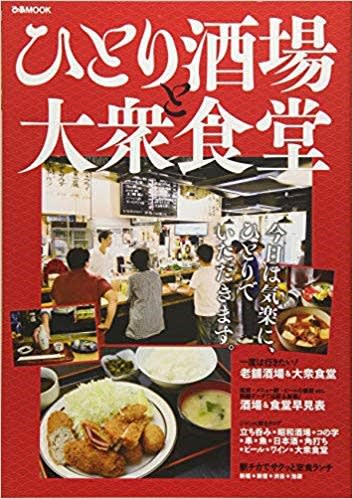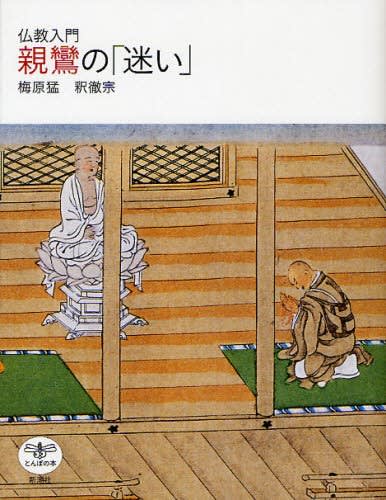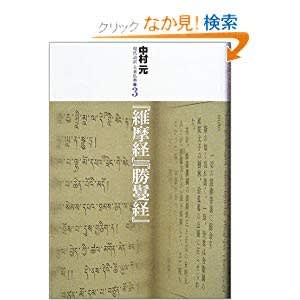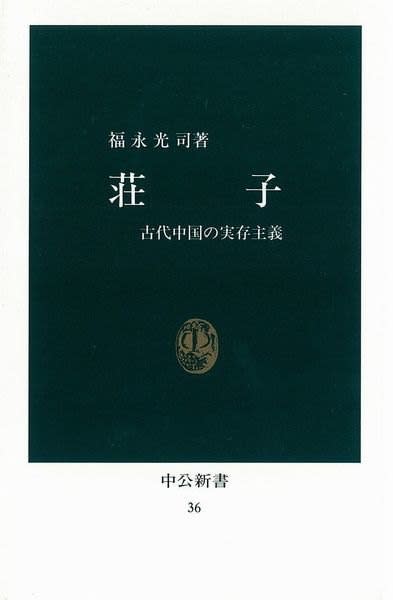おひとり様ブームの昨今、酒場や食堂にもその波はやってきています。
好きな店で、好きな酒と肴、食事を頼み、好きなように時間を過ごし、好きな時に帰る。
自分ならではの時間を愉しむことができるのが醍醐味。
本誌では、そんな“ひとり時間"を過ごすのにぴったりのお店100軒を
ピックアップしてご紹介。
いざという時、知っているときっと役に立つお店ばかり。
保存版として是非ご活用ください。
[企画内容]
・一度は行きたい! 老舗酒場&大衆食堂
・詳しいデータで比較&検索! ひとり酒場&大衆食堂早見表
・ジャンル別 ひとり酒場と大衆食堂案内
立ち呑み/昭和酒場/コの字/串/魚/日本酒/角打ち/ビール/ワイン/大衆食堂
・エリア別 駅チカでサクッと定食ランチ
新橋/新宿/渋谷/池袋
好きな店で、好きな酒と肴、食事を頼み、好きなように時間を過ごし、好きな時に帰る。
自分ならではの時間を愉しむことができるのが醍醐味。
本誌では、そんな“ひとり時間"を過ごすのにぴったりのお店100軒を
ピックアップしてご紹介。
いざという時、知っているときっと役に立つお店ばかり。
保存版として是非ご活用ください。
[企画内容]
・一度は行きたい! 老舗酒場&大衆食堂
・詳しいデータで比較&検索! ひとり酒場&大衆食堂早見表
・ジャンル別 ひとり酒場と大衆食堂案内
立ち呑み/昭和酒場/コの字/串/魚/日本酒/角打ち/ビール/ワイン/大衆食堂
・エリア別 駅チカでサクッと定食ランチ
新橋/新宿/渋谷/池袋