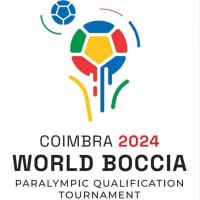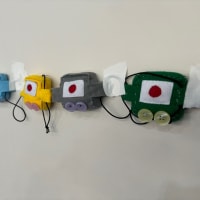映画『聲の形』を観てきた。
レディースデイの夕方ということもあり下校途中の女子高校生や20才前後の女性比率が高くオッサンは一人浮いた存在だった。それはともかくこの映画を観に行ったのは『聞こえない聞こえにくい人』に関する映画だから。もちろん原作である漫画も読んでいる。
(漫画の感想は以前書き込んでいるので良かったらどうぞ)
http://blog.goo.ne.jp/kazuhiko-nakamura/e/e4a8cb73159732effc738312c8699c00
http://blog.goo.ne.jp/kazuhiko-nakamura/e/5458045089e308a1ceec8ae0088a5c4c
http://blog.goo.ne.jp/kazuhiko-nakamura/e/c1665545f9e01f5b36ab76eb2fba87ec
とまあそういう流れなので映画の感想というより主として『聴覚障害』『聞こえない聞こえにくい人』や『日本語字幕』という観点から書き込みたい。
原作では、聴覚障害者である西宮硝子(しょうこ)をいじめ、後には周囲からいじめられる側に回った石田翔也の一人称で物語は進められる。原作では硝子からの視点も多少はあるものの映画では石田翔也目線以外の硝子を描くことはほぼ放棄されている。そういったこともあり(原作でもわかりにくかった)『聴覚障害者』である面や彼女の心情もさらにわかりにくい構造になっている。
そして映画では2人を掘り下げるのではなく、より群像劇になっており『聴覚障害』はより物語の装置に、極端に言えば硝子が『聴覚障害者』でなくともいい作りになっている。もちろんそのこと自体が悪いわけではない。
硝子と入力するときに『しょうこ』ではなく『がらす』と入力し変換しているのだが、彼女は写し鏡のような存在に近いのかもしれない。例えば知的障害者が写し鏡のような存在として物語に動員されることもある。
2人を掘り下げるという選択肢は作り手側には当初からなかったと思うが、実写化であれば掘り下げざるを得ない面はあったと思う。
あらためて彼女を『聴覚障害』の面から見てみると、一人の人間には思えないところがある。そのあたりは前述した以前の記事にも書き込んだ。
http://blog.goo.ne.jp/kazuhiko-nakamura/e/c1665545f9e01f5b36ab76eb2fba87ec
聴覚障害者、ろう者といっても様々だ。聴力レベルや補聴器活用の違い、手話ができるできない、日本語発語の得意不得意、文章の得意不得意、通った学校等々。だがその組み合わせが無限にあるというよりは、聴覚障害児童の最大の問題である“言語獲得”をどのようにしておこなったか、おこなえたかによって組み合わせもある程度限定されてくるわけだ。シナリオ、あるいは漫画を描く場合、それぞれの“履歴書”から描いていくということも多いだろうが、硝子の場合はかなり矛盾した履歴書、あるいは相当に苦しい履歴書になっている。原作自体がそうなので映画はさらにそういった印象が強い。むしろ翔也や他の登場人物のほうが履歴書に忠実に書き起こされている印象がある。
硝子は等身大の聞こえない聞こえにくい人というよりは、寄せ集めの集合体のような存在というか物語の要請からのキャラクター設定になっている印象である。漫画も映画も細かなディテールはしっかりしていてリアリティはあったりするのだが、一人の人間として考えると整合性がうまくとれていないというか、かなり無茶苦茶だということだ。
そういった意味では、聞こえない聞こえにくい人の理解につながるというよりは誤解につながる面もあるのかとも思う。しかしそもそも漫画も映画も聞こえない聞こえにくい人の理解につなげようとすることがメインテーマではないわけで、こんなことを書いていること自体が野暮かもしれない。またタイトルで『聞こえない世界の一部のみを描いた映画』と書き込んでいるが特に批判的な意味は込めていない。
ただ一つ一つのディティールに、聞こえない聞こえにくい人が同調し共感することは大いにあると思う。しかしその反応がさらに聴者の誤解を生むこともあるのかもしれない。
聞こえない聞こえにくいことに関して、映画化に際して新たに付け加えられた点はほぼないが、肉声をどう聞かせるかという点には直面せざるを得なかった。発音の明瞭度に関しては原作にも吹き出しの文字を半分消したりなどの工夫が施されており踏襲した形だが、声のトーンだけは映画独自に作り込まなくてはならない。
聞こえない聞こえにくい人のしゃべりのトーンは“平板”だったりすることが多い。補聴器活用の影響で機械的なトーンになったり、トーンの違いでニュアンスを使い分けられなかったりするからだと思われる。こういった聞こえない聞こえにくい人のトーンに久しぶりに触れた時など、私などはまるで故郷に帰ってきたかのような感覚を覚えることもある。映画ではそのあたりは巧妙に避けようという判断だったのだろうか。
もう一つの『日本語字幕』というテーマに移ることにする。
日本語字幕は耳の聞こえない聞こえにくい人向けのもの。もちろん老人性難聴の方々にも有効だろうし、録音状態が不明瞭だったり、むずかしい言葉が飛び交う場面などには聞こえる人にも有効だろう。
この映画は9月17日に公開、翌週9月24日からの1週間に限り、1日1回だけ全国の映画館で日本語字幕版が上映されるようだ。つまり今週は日本語字幕版も上映されている。
この映画は聞こえない人が主要な登場人物であるにも関わらず日本語字幕版の上映回数が少な過ぎるという意見があがっているようだ。確かに1週間に限らずもっと日本語字幕版の回数は増えていったほうが良いと思う。
例えば川崎チネチッタは翌週以降も日本語字幕の上映を継続するらしい。知人である手話通訳者やろう者の尽力もあったようだ。今週も5回の上映のうち、3回が日本語字幕付きで上映されているようだ。
http://cinecitta.co.jp/movies/detail/05161.html
その他の映画館でもそういった取り組みがあるのかもしれないし、要望に応えてくれるところもあるのかもしれない。
ただこの映画に限らず邦画すべてが日本語字幕になればよい、全てに上映は日本語字幕付きで行われるべきである。それがバリアフリーだという意見には猛反対である。
聞こえない聞こえにくい人には日本語字幕が必要なように、聞こえる人にも聞こえる人向けのバージョンが必要だ。少なくとも作り手の立場からは強く思う。
例えば登場人物が言葉を一言一言絞りだすように話している場合、日本語字幕では先に言葉を表示してしまうことになる。聞こえる人にはその肉声こそを聞いてほしい。ドキュメンタリーにしてもフィクションにしても。
場所によっては車椅子の通れるスロープだけではなく健常者向けの階段もあったほうがいいように、日本語字幕も必要だが聴者向けの字幕無しバージョンも必要だ。もちろん眼鏡に字幕が出るなど新たな技術が導入され上映される場合は別だ。これなどはバリアフリーというよりユニバーサルデザインということになるだろうか。
視覚障害を含んだバリアフリー上映にも少し触れておく。以前とある映画祭に呼ばれ、バリアフリー上映、つまり日本語字幕、音声ガイド付きで上映したいということがあった。
上映した私の作品(ろう者サッカー女子日本代表を描いた『アイ・コンタクト』)は全面的に聴覚障害者を描いた映画だったので、その作品は字幕付き無しの区別はなく字幕有バージョンだけだった。字幕は聞こえない聞こえにくい人向けのみならず手話に対する字幕(つまり手話がわからない聞こえる人あるいは難聴者向け)も含まれていた。その点は問題なかったが、音声ガイドをFMなどの受信機に飛ばすクローズドの方式ではなく場内に流すとのことだった。しかし私の映画には長い無音の場面があり、場内に音声ガイドが流れたら台無しになってしまう。聞こえる人には“無音”を聴いてもらいたい。そのためには音声ガイドを受信機に飛ばす方式にしてほしい。資金がないのなら私を呼ばずにそのお金を充ててほしいと強く要望した。結果としては私も招待していただきバリアフリー上映というか万人向け上映が実現した。
また9月1日に開館したバリアフリー上映専門館『シネマ・チュプキ・タバタ』の取り組みなど、もっと注目されるべきだろう。
http://chupki.petit.cc/
日本語字幕に話を戻すと、題材によって、つまり全面的に聞こえない聞こえにくい世界を描いた映画などはすべて日本語字幕上映でも良いかとは思う。
『聲の形』は聞こえない聞こえにくい世界の“一部”のみを描いた映画なのですべての上映が日本語字幕になるべきだとは思わないが、1日のうち1度や2度は日本語字幕上映があってよいかと思う。あるいはそのこととプラスして終日日本語字幕で上映する日や曜日があっても良いのではないか。