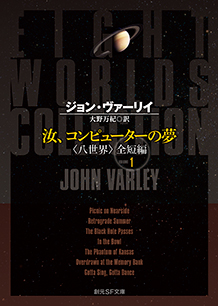『汝、コンピューターの夢』 ジョン・ヴァーリイ (創元SF文庫)
ジョン・ヴァーリイの〈八世界〉シリーズ全短編集の1巻目。SFが読みたい! BEST SF 2015の海外篇第11位。
収録全作品が、新訳、もしくは改訳。いくつか以前に読んでいるものがあるはずなのだが、記憶に引っかかるものはなかったのは訳のせいか、記憶力のせいか。
今さらヴァーリイかよという感じではあり、実際にいくつかの短編の設定や雰囲気は古臭く、懐かしさを感じるものもある。しかし、小説として今でも面白く読めるのは、結局のところヴァーリイが描いているのが人間だからということなのかもしれない。
70年代に彼が登場した当時は、新しいハードSFとか、スタイリッシュな未来描写なんて評判が立ち、人体改造や仮想現実をネタとした多彩なSFガジェットの扱いが注目されていたが、それだけの作家だったのであれば、この時代には既に古びたレトロ・フューチャーの仲間入りだったかもしれない。
しかし、ガジェットそのものではなく、それに翻弄される人間を描くことによって、2010年代にも通用する作品として再評価されることになった。
特に、性別をころころと変えることが常識化した社会は、世界的にジェンダーフリーの思想が盛り上がっている昨今から見れば、実に先験的なシリーズであったと言えるだろう。
「ピクニック・オン・ニアサイド」
これがなんとデビュー作。いきなりの性転換で驚くものの、実は郷愁と孤独がテーマという二段構え。収録は発表順なのだが、シリーズの背景を説明するのにもってこい。
「逆行の夏」
身体改造が生み出す新たな家族の形。親子の葛藤なんて、どんな社会になろうとも普遍的なものだが、こういう親子にとってはどうなんだろう。
「ブラックホール通過」
skypeでいつでもつながっている恋人同士というのも珍しくなくなったが、その状態における鬱陶しさと孤独感がブランコのように揺れ動く様子が良い。あと、恋人に救われるダメ男というパターンが多いのだけれど、ヴァーリイの願望なのか?
「鉢の底」
凄腕技術者の幼女が登場するという、現代日本に最適な作品。しかも、やっぱり幼女に救われるダメ男。
「カンザスの幽霊」
なんと、冒頭作品と同じ主人公だが、話はほとんど無関係。記憶の保存とクローンによる復活が可能となった社会での殺人の意味と、重大犯罪の結末。価値観の違いが衝撃的。気象操作を利用した芸術というのもおもしろい。
「汝、コンピューターの夢」
格好のいいタイトルにくらべて、いささかおまぬけな話。よく考えると、いろいろと必然性がなくておかしいのだが、仮想世界へのジャックインが引き起こす問題と、それに直面した時の混乱は普遍的なネタかもしれない。
「歌えや踊れ」
植物と共生する改造人間が生み出す音楽。ここまで来ると、もはや人間なのかとも思えるが、やはり人間の心や感情は変わらない。だから美しいし苦しい。