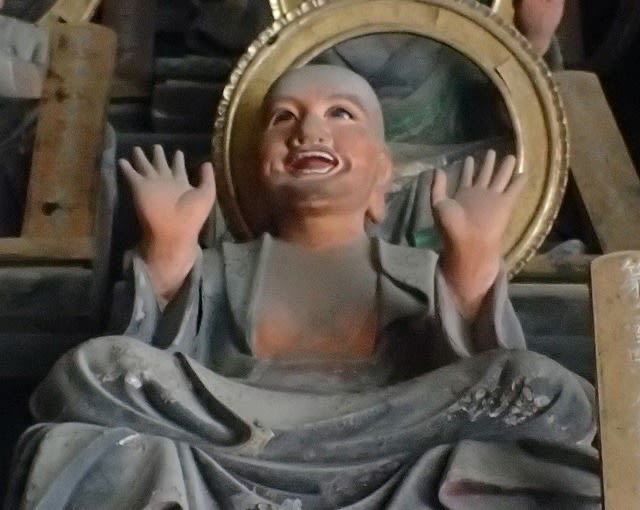羽島市に大賀ハスを育てているところがあるというので行って来ました。
大賀ハスは、昭和26年、大賀一郎という人が縄文遺跡から古代ハスの種を発見、翌年発芽に成功し、それが広まったものです。
羽島市には、昭和54年に植えられました。
ハスの種は、堅い堅いからに守られていて、栽培するときは、人の手でからを一部割らないとなかなか発芽しません。
だからこそ、2000年以上も地中にあって、腐敗することなく、命を保つことができたのでしょう。

一時は、この看板のように薄紅の花がいくつも咲いて、目を楽しませてくれたのですが、近年はあまり咲かなくなったと聞いていました。

行ってみると、花は一つも開いていませんでした。土壌を入れ替えたり、新しいハス根を植え付けたりしているそうですが、なかなか元に戻らないようです。ハスに限らず植物の栽培は、むずかしいですね。

近くでひまわり祭りをやっているということなので行ってきました。

こちらは満開。ひまわりは、すべての花が同じ方を向いて咲くようです。

反対側に回ると、全部の花にそっぽを向かれてしまいます。

帰り道、満開の蓮田を見つけました。
その話は、次回。