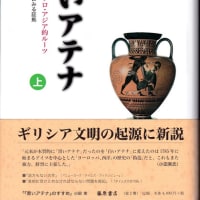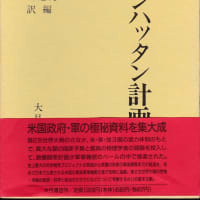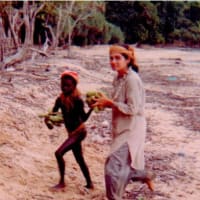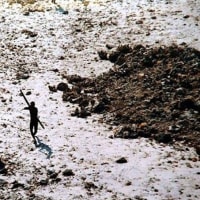▲ティム・ワイナー著 藤田博司・山田侑平・佐藤信行訳 『CIA秘録』 文藝春秋 2008年 上巻・下巻とも1857円+税
ウクライナ危機の中で『CIA秘録』を再読・再々読する
ティム・ワイナーの『CIA秘録』が文藝春秋より日本語訳で出版されてから5年以上が経つ。
ドイツ降伏による連合国の祝勝気分は束の間で終わり、直ちに、冷戦への道を歩み出していく。それにはアメリカ中央情報局の設置が急務となった。トルーマン大統領が署名してCIA法が強引に議会を通過した1949年5月27日、その日、特別工作室のワイマン少将は移民局の担当官に、ウクライナ人ミコラ・レベットが「ヨーロッパで当組織(CIA)のために貴重な支援を提供してくれていると告げた」
このウクライナ人ミコラ・レベットとは何者だったのか?
以下ティム・ワイナー著 藤田博司・山田侑平・佐藤信行訳 『CIA秘録』 文藝春秋 2008年刊より、第一部 第5章 「盲目のお金持ち」 鉄のカーテンから
今世界から焦点が当たっているウクライナの1949年の状況を抄出する。
「この法律(1949年CIA法案)によって、CIAは議会が1年ごとにどんぶり勘定で、予算をつけてくれる限り、したいことは、ほとんどなんでもできた。秘密予算に関して少人数の軍事分科委員会で承認を得さえすれば、事情を知る人たちの間では、あらゆる秘密工作について規則に従った承認を得たものと理解されていた。この法律に賛成票を投じた下院議員の一人は、後年、大統領になったとき、こう、述懐した。もしそれが秘密なら、それは合法だということだーそう語ったのは、リチャード・M・ニクソンである。 CIAはこれで一切の制約から解放された。使途を問われない資金があるということは、天下御免のやりたい放題を意味していた。こうした資金は、国防総省予算のなかで偽の項目の中に巧妙に隠され、アシのつかない仕組みになっていた。」 ティム・ワイナー 『CIA秘録』 文藝春秋 2008年 上巻 69頁
「この1949年CIA法の重要条項の一つは、CIAが年間百人まで、外国人を国家安全保障の名目のもとにアメリカに入国させることを認めていた。「それは移民法ないしその他の関連諸法では入国を認められない場合でも、永住を認める」というものだった。ティム・ワイナー 『CIA秘録』 文藝春秋 2008年 上巻 69頁
「トルーマンが署名して1949年CIA法に署名したのと同じ日に、特別工作室を取り仕切っていたワイマン少将は移民局の担当官に、ウクライナ人ミコラ・レベットが「ヨーロッパで当組織(CIA)のために貴重な支援を提供してくれていると告げていた。」 ティム・ワイナー 『CIA秘録』 文藝春秋 2008年 上巻 69頁
「CIAは新たに成立したばかりの法律の下で、レベットをアメリカに密入国させたのである。」
「CIAの資料では、レベットが率いていたウクライナのグループは「テロ組織」とされていた。レベット自身は1936年にポーランドの内相を殺害したかどで投獄されていたが、三年後にドイツがポーランドを攻撃した際、逃亡していた。」 ティム・ワイナー 『CIA秘録』 文藝春秋 2008年 上巻 69ー70頁
「レベットは、ナチを当然の味方と考えていた。ナチスドイツは、レベットの部下を二つの大隊に組み込んだ。そのうちの一つは「ナイチンゲール」と呼ばれ。カルパチア山系で、戦闘に従事し、戦争終結後もウクライナの森林地帯に留まって、フォレスタル国防長官を悩ませることになる。レベット自身は自分を自称ミュンヘンの外相に仕立て上げ、ウクライナのゲリラ隊員をCIAに提供して、対ソ連の任務に従事させようとした。」 ティム・ワイナー『CIA秘録』 文藝春秋 2008年 上巻 70頁
「司法省はレベットを、ウクライナ人やポーランド人、ユダヤ人を殺害した戦争犯罪人と見なしていた。しかしレベットを国外追放しようとするさまざま動きも、アレン・ダレスが、連邦移民コミッショナーに、レベットは「当CIAにとって計り知れない価値があり」「最重要作戦」を支援している、と書き送った後、ぴたりと沙汰やみになった。ウクライナ作戦に関するCIAの歴史によると、CIAは、「ソ連に「ついての情報収集の手段をほとんど持っていなかった。そのため、どれほど成功の可能性が低くても、あるいはいかがわしい工作員が関わっていても、あらゆる機会を活用せざるを得なかった」。「胡散臭い過去のある人間でも、移民グループはしばしば、無為・無策にとってかわる唯一の手段だった」。したがって、「多くの移民グループに関わる戦時中の残虐行為の記録も、彼らがCIAにとって重要な人材となるにつれ、あいまいになっていった」。1949年までにアメリカは、スターリンに反対するものなら、相当にいかがわしい人間とも手を携える用意ができていた。レベットはそうした部類の男だった。」 ティム・ワイナー 『CIA秘録』 文藝春秋 2008年 上巻 70頁
2014年冬の、「ウクライナクーデター」は、スターリンがプーチンに変わっただけで何か既視感のある 光景ではないだろうか。
「プーチン・ロシアに対抗するものなら、いかがわしい勢力とも手を携える用意ができている
それも、EU・NATOを抱き込んで」 変奏されているが、構造は同じ。
2014年2月に起きたクーデターによるウクライナ暫定政権の軍事的側面を担当する勢力に、CIAが1949年に工作する前から存在していた、ファシズム、民族・国家主義者の残党の人物が、いかがわしい工作員の系譜が読み取れようというものである。
5月25日のウクライナ大統領選挙を前に、見え隠れする怪しげな人物の出自と系譜を細心の注意をはらいながら監視する必要がある。
監視を監視することだ。
今から10年前の2003~2004年にかけての バラ革命・オレンジ革命・ジャスミン革命などなども、あやしげな民主化運動であったのだが、今回は、CIA長官が直々に指令塔となって、ウクライナを隠密訪問しているところをみると・・・・・・
『CIA秘録』は特別に日本版のために日本の章を追加してくれていて、この章も興味深かったのだが、今回は中央情報局の立ち上げ前後の頃のギリシア・イタリア・東欧などの章を再び読み返してみると、改めて、ファシズムと・スターリン・ロシアと戦う中で、見境がつかなくなっていく大義なきアメリカが印象に残った。
それにしても、ウクライナは、「国民国家」を豊かに培う間もなく、さまざまな・冷酷な大国に数百年にわたり翻弄され続けている。EUも当初の構想の時期とは違ったグローバル・新自由主義・ファシズムの臭いがたちこめてきた。先入観はここではっきり止めて直視することを余儀なくされている。
この項 続く