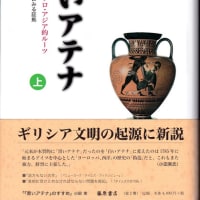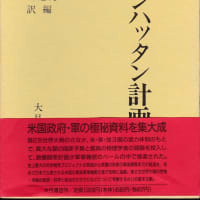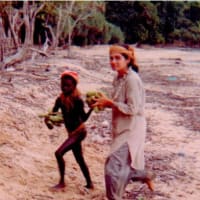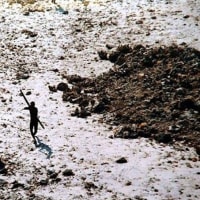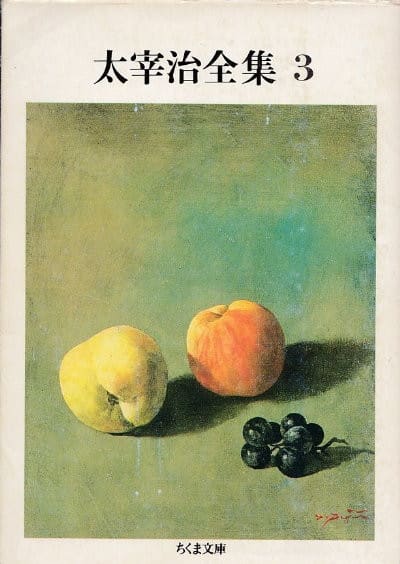
▲筑摩文庫版 『太宰治全集3』 1988年10月 筑摩書房
ユリイカ 特集 太宰治 私とは何か』 所収
寺山修司 「歩け、メロス・・・・太宰治のための俳優術入門」
ユリイカ 特集 太宰治 私とは何か』 所収 寺山修司 「歩け、メロス・・・・太宰治のための俳優術入門」
子供の転勤にともなって、我が家から持ち出していた本が、戻ってきた。
大学のゼミで、太宰治の小品をめぐって、その評価を発表する聴取者に表現の力を伝えるレッスンのようなものだったらしい。
太宰治の文庫版全集なので、久しぶりに我が家に本が戻ったついでに手の届くところに置いていた。
ある日、この文庫本の全集のカバー絵の「桃とブドウ」に目がいき、「走れメロス」が掲載されていたので、寝ころびながら、読んでみた。
最初に読んだ頃と比べて、何かすっと理解した、すがすがしい気分とは違って、なにやら文章に引っかかるものを感じたのだ。
年をとり、いろいろな経験をすると、あることに関しては理解が深まるが、あることには、どうしても自分の感覚とあわない異質な感情に襲われることもある。長編小説ならば、そこで読むことをやめてしまうのだが、詩や短編の場合はそうはいかず、読み終わってから、違和感を残すことになる。
太宰治の小説は、教科書に採用されているものもあり、比較的多くの人が青春時代に読んでいるらしい。
感覚に合わないものは、何も無理矢理好きになることもない。貴族身分なら感情教育のようなことも子供のうちに施されてバランスのよい人格と感性が形成されるのかもしれない。
しかし、私のように野生のまま育てば、言葉遣いには、方言も残れば、友との語らいの間合いだって、地域性が刻印されたりする。昔のことばでいえば「風土性」のようなものが感性に刻まれたりする。
これは、良い・悪いとか、優劣の基準とかの後天的に学んで獲得できるものとは違うように思われる。
べつな文化で長期に育った身体に書き込まれた経験というようなものはその人にどんな意味を与えるのだろう。
人の経験知がDNAに書き込まれるというのは非科学的なはずと思うが、同じ経験でも、子供の時に経験するものと、大人になってから経験するのとでは、その経験についての意味とその人に与えるものは、全く違ったものになることがある。
20歳代で、読んだ本が、ある日、別のものになるということがある。
太宰治の熱烈なファンのようには私は好きにはなれなかった太宰治だが、「走れメロス」は最初に読んだときには、あれ、これはちょっと変だなと思いつつ、一気に読み終わっていた。
小説家は、このように断片的な史実からでも短編小説は書けるんだ。という不思議な羨望をそのとき持ったのだ。
・
・
家の雑誌を整理していると古い『ユリイカ』という詩の雑誌が出てきた。1975年に刊行された太宰治の特集号である。筑摩書房の文庫版太宰治の全集も家に戻ってきたこともあって、太宰治の「走れメロス」を読んだ後、寺山修司の「歩けメロス・・・・太宰治のための俳優術入門」を読んでみた。
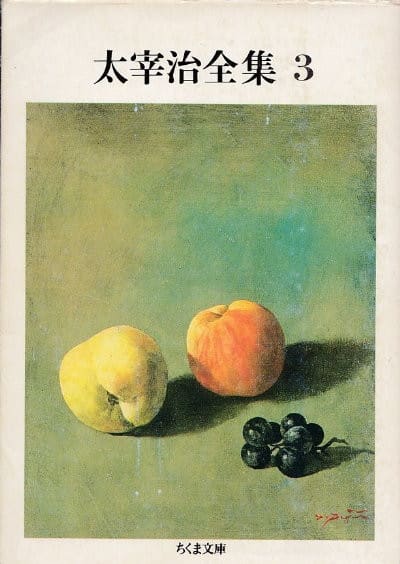
▲筑摩文庫版 『太宰治全集3』 1988年10月 1975ー1976年刊行の筑摩全集類聚版太宰治全集底本

▲ 『ユリイカ 特集 太宰治 私とは何か』 1975年3-4月 青土社

▲『ユリイカ 特集 太宰治 私とは何か』 1975年3-4月 青土社 目次
この特集で、異彩を放っていたのが、寺山修司の「歩け、メロス・・・・・・・太宰治のための俳優術入門」
熱烈なる太宰治ファンには極めて迷惑な話だが、太宰治が小説で食えなくなり、、時代もまるで違った世界に迷い込んで、なぜか寺山修司の演劇塾に入門し、短編小説を実入りの多い脚本に作り替えるという荒技を披露したものと考えてもいい。
寺山の文章はそれほど長いものではないので、全文引用したい誘惑に駆られるが、そうもいかないので、冒頭の部分からまず始める。
「笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた牧人のメロスが、たった一人の老人の、
「王様は、人殺しです」
という言葉をまにうけて、王を「生かしておけぬ」と のそのそ入ってゆく。
メロスは「政治のわからぬ」単純な男だ」と、作者もことわっているが、それにして見も知らぬ老人の一言で、殺人を決心してしまうような「あかるい性格の」「のんきな男」というのは。私には耐え難い。第一、かかわりあいになる方が迷惑というものである。
たぶん、都の大路を歩いているときに出会ったのが、老人ではなく、最近、将官に出世したばかりの兵士の母親だったとしたら、事情は一変していただろう。
「王様は、思いやりのある人です」
という母親の言葉をまにうけて、花でも買って王城を訪ねていったかも知れない。」
と最初から、太宰をこき下ろす。
もちろん滑稽譚、道化としての様相をたぶんに含むものなので、それを理解した上で、寺山修司はこういう。
「この短刀で何をするつもりであったか。言え!」
と言われると、メロスは胸を張って、
「市を暴君から救うのだ」
「メロスの盲動は「反革命」的でさえあったと言わなければならないのだ。」
「こんな男を、無知さ純粋さによって「愛すべきやつ」と考えてやるほど、政治的現実はゆるやかではない。ディオニス王の場合も、彼の圧政下にあったシラクスの市民たちの場合も生きることにシノギを削っていたに違いないからだ。」
王に命乞いをする理由にも寺山は注文をつける。
「妹の結婚に兄がいなけらばならぬというのも、説得力の乏しい理由である。だまっていても妹は自力で、結婚位できるはずだし、それができぬほど過保護な妹に育てあげてしまっているのならば、そのメロスにデォオニスの政治を批判することなどできるものだろうか。」
「一人の王を殺すということは、結婚制度を内包する行政の構造そのものをも根底からくつがえすことである。」
私は、このへんでいいかげんにメロスに愛想がつきてくる。」
ということで、寺山修司はこの論考のタイトルのようなことばを太宰に向かって放ち、叱正する。
戯曲にならない、書き換えろ!
「歩け、メロス」
1975年3-4月の雑誌に発表された寺山修司が太宰治に放った言葉
「歩け、メロス!」
それは
今になると、1960年代末から1970年代の学生に向けられた、「革命ごっこ」への叱正のことばのようにも聞こえてくるから不思議である。
寺山修司は歴史を展望できる男だった。と思う。
「王を殺す(革命)」ということは、大変なことなんだとね。
寺山修司の本にはこの「歩け、メロス」は入っているのだろうか。
世直しの気運が急速に失われていく1970年代中頃の日本、寺山修司は、太宰治論に仮託して、一人激しくアジテーションをしていたのではないか。
つづく