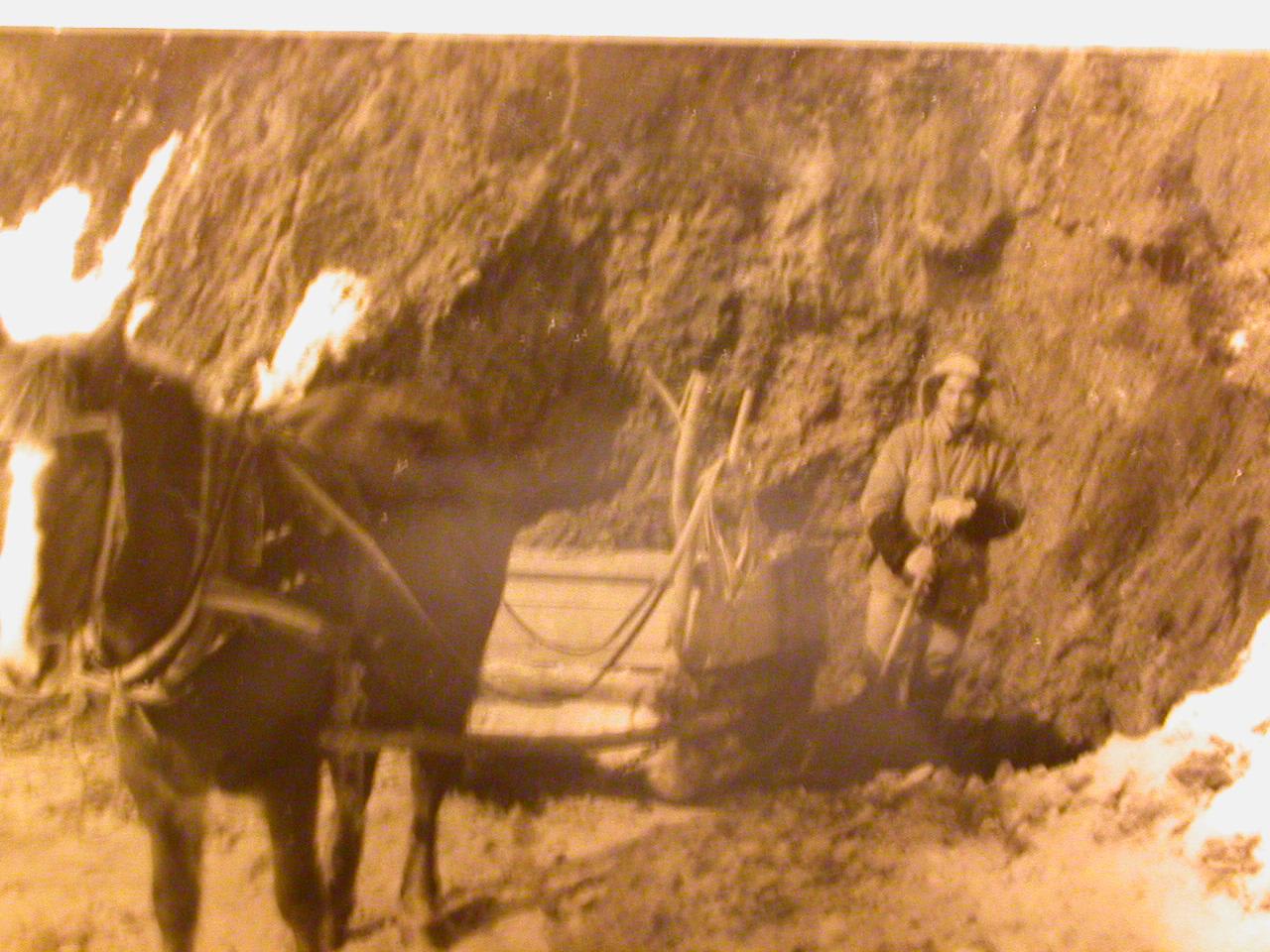埼玉では教師の娘として厳しい躾をうけ、卒業後は銀座で働いていたこともあったば~ちゃん。
近所に住むじ~ちゃんと知り合い結婚。三男のじ~ちゃんは、ある日、役場で北海道開拓民募集の記事を見て移住を決心。
ば~ちゃんの親は大反対だった。〝嫌だったら連いて来なくてもいい、ひとりで行くから〟とじ~ちゃんの意思は固く、一家での北海道移住が決まった。
とは言うものの渡航費や一年間は食べていける位のお金が必要だった。
1953年4月1日、汽車で埼玉から青森まで、青森から青函連絡船(洞爺丸)に乗船し津軽海峡を渡り、函館で降船。函館から汽車で追分まで。

長い長い道のりを経て、4月2日、じ~ちゃん(32歳)ば~ちゃんは(27歳)4歳(義兄)と2歳(夫)の4人は、埼玉から他の4家族と共にここ追分に開拓民として入植した。
4月だというのに、肌をさす、痛いような風が身を突き抜けていった。
道らしき道はなく、木々の中をぬってたどり着いた、自分達がこれから開墾する土地を見たときの驚き。
〝ここです。〟と言われた場所は木にロープで囲いがしてあるだけの、見渡す限り未開の原生林。
話には聞いていたがここまでとは・・・・・
不安と恐怖に見舞われました。
4家族は町の労働会館で、自分達の住まいが出来るまで共に暮らしていました。
子供を連れ、毎日毎日、日が暮れるまで真っ黒になって、せめて自分達の家をと、必死で鋸で大木を切り倒し、一鍬一鍬、大きな根っこを掘り出し、開墾していきました。
やがてそれぞれの家族は自分の土地に落ち着きました。
出来上がった我が家。
それは左右から柱を斜めに立て屋根を作り、その上に、葦や笹などの草木で屋根を覆い周囲も草木で囲った拝み小屋(おがみごや)で、出入り口はムシロを2枚ぶら下げただけの粗末なものでした。もちろん電気なんかないランプ生活。
床は土のままで、野草や笹を敷き、さらにその上にムシロを敷き、台所は流し台と水桶と、食器などを置く粗末な戸棚があるだけでした。暖房は炉で大木の根を燃やし、煙突がないので、煙がいつも部屋に充満していました。
それが待ちに待った家族4人の住む家でした。
ついこの間までは親の元で身の不自由なく暮らしていたのに、なぜこのような思いをしているのか、思えば思うほど涙がこみ上げ、仕事も手につかず大きな木の下で泣いていました。
親の反対を押し切ってここに来た。でもほんとうに厳しい。もうだめだ!内地に帰りたい!
母の顔が何度も浮かび、〝お母さん~!〟大きな声で叫びました。
戻れない・・・・・
今更泣き言を言っても、もう遅い。頑張れ!と自分の心を叱りつけ、一日も早く安定した生活ができる様に、畑を作って家族が食べていけるようにと、来る日も来る日も開墾に明け暮れました。
割り当てられた土地は5町(この数字は記憶が定かではない。15000坪)、一畝(いっせ)(30坪)を開墾すると役場から測量に来て、お金がもらえるのだが、利子がつくのでお金がある人は一年後にまとめてもらっていた。
町までの買い物。
狭い道路(これも開拓の人達で作ったもの)、険しい坂道を登り降りし、側には川が流れ、大きな丸太が横たわりその上をやっと渡り、町に出るが、帰りが遅くなると何時熊が出るかそればかりが心配だった。
開墾には夫婦ふたりだけの労働では到底叶うものではなく、
親子馬を買った。よく働いてくれた。
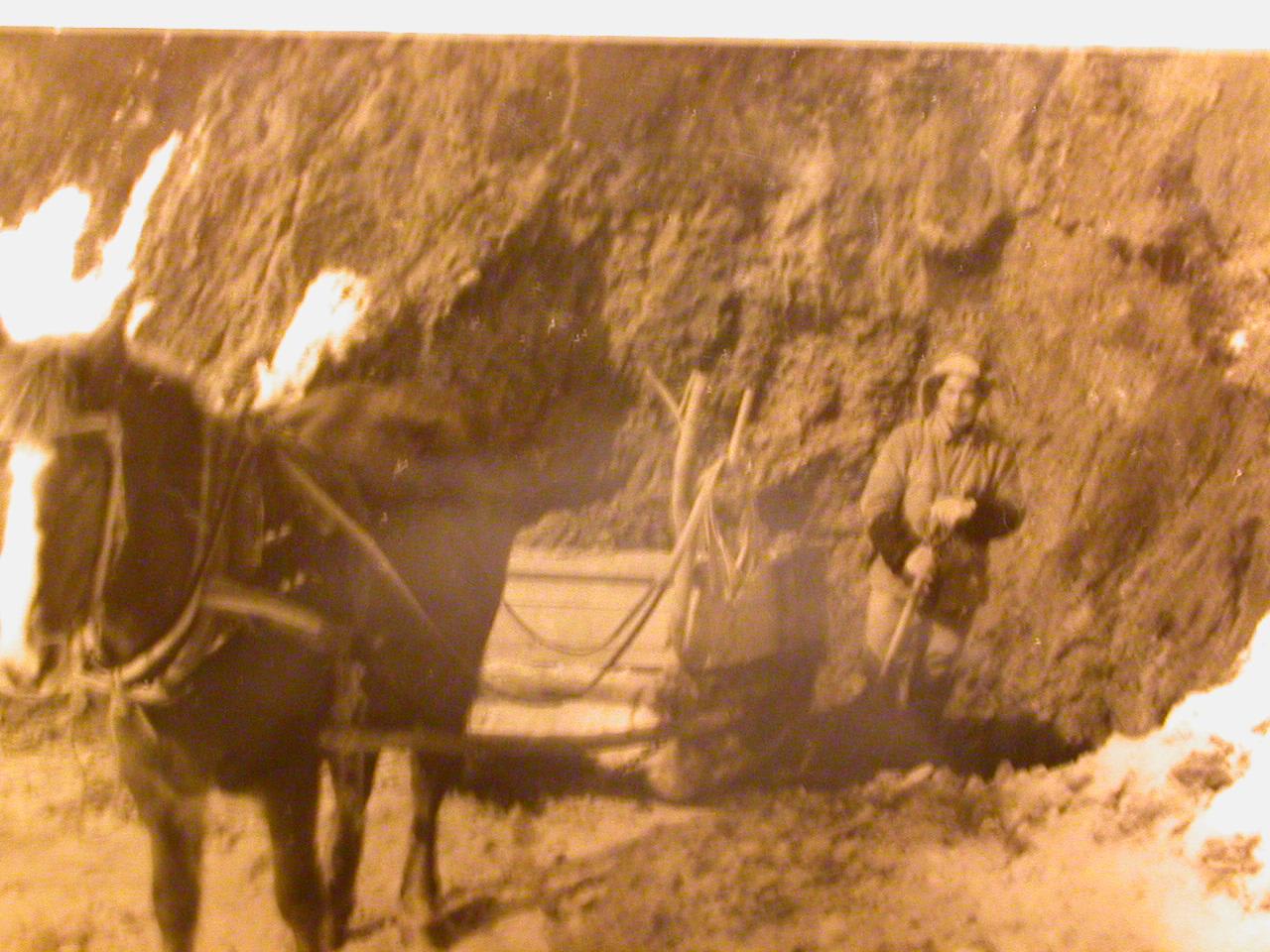
せめて子供達には暖かいセーターをと綿羊も買い、
豚も買い、大きくして売ったもんだ。
鶏も買い、町に卵を売りに行った。
お金が掛かることばかりだったが、少しでも安定した生活をと必死で働いた。
開墾で疲れた足を休むことなく、あちらの草こちらの草とつなぎ替えて食べさせていたのに・・・・
ある日熊が出て綿羊2頭が食われてしまい、
ある年は大冷害に見舞われ一夜にして豆が全滅。
大事な働き手の馬も伝貧にかかって、親子共々連れて行かれてしまった。
どうして! なんでなの!
根気を失ってしまいそうでした。
今ここで弱音を吐いてはいられない。内地の親に逢わす顔がない。立派な農家にならなければと心に言い聞かせながら、つらいこと、悲しいこと、寂しいことをじっと我慢してこらえました
すべてを開墾するのにどれだけの年月を費やしただろうか。
開墾が終わると今度は土地代を払わなくてはいけない。
払うお金が無いと、土地を売って払う。
血の滲むような思いで必死で開墾した土地を・・・・
今、長男は開墾した土地で園芸農家を、次男はサラリーマンを辞め、メロン作りを継ぎ、北海道で生まれ育った娘も農家に嫁ぎ、子供達全員が農業にたずさわっている。
言葉では言い尽くせない辛苦の毎日。
今ではすっかり昔話になっている。
ボタンひとつで自由になる文化生活、なにかいたましく感じるのは私だけでしょうか。
※ば~ちゃんたちが乗ってきた「洞爺丸」は翌年9月26日、函館湾七重浜近くで横転転覆座礁し、1,331名の内、死者1,172名の大惨事となった。
北海道への移住が推奨されたのは本土での余剰人口の受け入れ先としてとも聞く。北海道は寒冷地、山地、火山灰地、低湿地、泥炭地などで農耕には不向きの土地。冬の寒さも厳しく、獣害もあり、農業経営に失敗し、冬の寒さに耐え切れずに夜逃げをする移住者も後を絶たず、北海道の開拓の歴史は極めて過酷なものだったようだ。今日、食の北海道と呼ばれるまでになったのは先人の苦労があったからこそ。労働力さえつぎ込めば開拓できるほど甘い状況では無かった。
辛苦をなめ尽くし、開拓に人生を賭けたじ~ちゃんとば~ちゃん。私もこの追分で人生を全うしたいと思うよ。