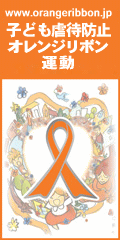派遣村で入村者が生活費2万円を渡された途端に逃げたという報道がありました。また、2万円を持って近くのコンビニに行き、ビールや焼き鳥を買っている者もいたそうです。
一昨年末、私たちは白河市にあるハローワーク前で仕事を探しに来た方々を対象にアンケート調査をしました。その時、ハローワークは休みでしたが、1時間ほどの間にたくさんの人が現れました。その中には、アパート暮らしという人も何人かいましたし、寮を出なければならないという人もいました。その方は、白河を出るという話をしていました。やはり都会へ向かう傾向があるようです。
花里は失業し生活が困窮した方を支援したことがあります。失業中という人の中にもいろいろなタイプがあります。派遣社員として働いていた方々と土木作業員などをしてきた方々とは少しタイプが違うかもしれませんね。
皆、同じ人間であり人は皆平等です。しかし、同じ対応や支援で良いのでしょうか。山谷で活動をする方々に聞きましたが、路上生活者には児童養護施設出身者が少なからずいるそうです。もし、施設で嫌な体験をしているとすれば施設的な場所は嫌でしょう。管理されることには抵抗があるでしょう。食事や宿を提供するからといって、人権がなくなるわけではないはずですが、「強制的」というイメージはあります。長年路上生活をしてきた人たちが一番苦手とすることではないでしょうか。
以前、段ボールハウスが強制撤去となり、収容施設への入居を勧められるというニュースをテレビで見ました。入居を拒んだ男性は、4匹の犬を連れ茫然としていました。今までは犬をつないで空き缶を拾う仕事をしていたそうですが、犬の居場所がなくなったしまったのです。公園などにつなげばすぐに保健所に捕獲されるでしょう。4匹と男性の姿に「福祉」の文字はかけらも見えなかった。本当に人間として扱うならば、連れていた「友」犬のことも相談に乗るでしょう。ボランティア団体に連絡するとか何とか考えるでしょう。「処分」して「入居」を突き付ける日本の福祉に非情を感じました。この何年か前の報道を今でも忘れることができません。
この寒空の中、空腹で路上に寝ている人を放置する国は心の貧しい国です。しかし、屋根と食事と2万円を与えればいいのでしょうか。逃げた人たちは、行政の無駄を嫌ったのかもしれません。行政側は、無駄でも形式通りに物事を進めます。ハローワークに通い、それがダメなら生保。それも家族や親族などについて聞かれる。実際、今の時期に仕事は探せないだろうと思う人にも「無駄」な行為をさせます。その間に心身共に疲れきる。何度も緊張し、何度も頭を下げ、何度も断られる。この繰り返しは誰でも心が折れるのではないでしょうか。派遣社員だった方々と土木作業員などの方は求める仕事も違うでしょう。土木作業員だった人は、履歴書も何もなく必要とされ働いてきた人が多いわけです。あ~だこ~だではなく、これやれる?と働けたら働く人もいるのではないでしょうか。このような事情から、花里は軽作業が必要だと考えています。コンクリートから人へ。コンクリートは要りませんが、緑はあってもいい。私たちは、バザーの収益金やカンパを財源として仕事を創ったので限界がありました。今、行政が同じ仕事を失業者を対象に行っています。行政も花里レベル?なんて笑いながら、財源があれば継続できたのにと悔やまれます。
支給された2万円でビールを買い、コンビニの裏で飲んでいた人たち。本当は、自分の労働で得たお金で堂々とお酒を飲みたいはずです。貧困と飲酒は密接な関係がありますので要注意ですが、寒い場所でコッソリ飲むビールの味は多くの国民が思う味とは違うのではないかと思います。彼らが堂々と暖かい場所でお酒を飲める世の中にしたいものです。