
漸く雷雨無しの予報が出たので霧積から鼻曲山へでもと思ったが三角点タッチ
遊びの途中なのでぐっと我慢。榛名南麓中腹以上でタッチしてないのは
巌山・滝ノ平・宮沢の三点のみになったので今日はその内の二つを狙う。
設置場所は榛名神社西側を南北に走る岩稜帯の北端と南端。
通勤時間帯の渋滞を避けて榛名神社無料駐車場、第一目標の三角点・巌山の
ある筈の岩稜突端を見上げながら出発。

神社への参道途中から西の稜線ヘ登らなくてはならないので左手を注視しながら
進むと斜面に赤鳥居発見、踏み跡もある。

右手に大黒様の像や千本杉の看板のある所。

踏み跡は秋葉神社の掲額のある鳥居を潜りジグザク゛に蛇行しながら急斜面を
登っていく。
途中に石宮がひっそり、銘は「延亨五」とあるが延亨は四年までだから
「寛延元年」だろう。丁度、九代家重の時代、この三年後に吉宗が
68歳で相棒の大岡越前が75歳で亡くなっている。

更に登ると遥かの彼方にチラッと鳥居が見えた。やがて前面のコブは
終了して一登りで鳥居前の広場(9.56)。
が、社殿は無く多分これが残骸。

石宮六体が並ぶが銘は読めない。その前面に赤白ダンダラポールと三角点。

これが第一目標の四等三角点・巌山 940.28m N-36-27-20-8 E-138-50-58-3。

さて、一服の後、稜線の縦走に出発。地形図を見る限りこの尾根が県道33号線と
クロスする地点まで直線距離は僅かに1.2K程、さしたる高低差も見られない。
だが、懸念されるのは終点までに壁岩の摺り抜け2箇所、稜線が極度に狭い
所が一箇所、小ピークが五個。特に小ピークの等高線が小さな丸状で厭だ。
頂上が細長い等高線で囲まれていれば「台地」なので楽だが、小さい丸状の
ものは等高線一本でもトンガリの岩隗の事が多いから。
稜線には明瞭な踏み跡がありこんなリボンの目印や

黄色・赤色の杭が間断無く付けられている。6cm角の黄色のものは「保損調査」
とか「国調多角」、4cm角の赤杭はお馴染みの「地籍調査」

壁岩の付近はかなり厳しい急登で摺りぬけていく。

途中にこんなお化けキノコ、勿論種類などは判らない。

やがて第一ポイントの双耳ピークの東嶺に取り掛かるがいやはや凄いところ。

丁度、榛名神社本殿の西に相当するが下は樹葉が邪魔して社殿は見えず
直立した巨岩が杉林の中に微かに望めるだけ。錐の先のような頂点に
達してギョッとする。心配していた通りその先は断崖で前進不能。
回り道を探すため100㍍後退して西に見えた窪に降りそこから改めて
双耳ピークの鞍部を目指す。もし、鞍部に見える個所が乗り越しなら
回り道が在るかもしれないと思ったから。
何とか鞍部着、前方を見てガックリ。乗り越しではなく前面も崖だった。

悔しいから何かを期待して双耳の西ピークに向う。道無しの藪を掻い潜って
ピークに達するも何も無し。樹幹にここに来た証拠の二本巻きテープを残して
憂さ晴らし。

休憩中に気付いたが付近に多数の小鳥が飛び交っている。こっちが静止していると
直ぐ目の前まで寄ってくるが、カメラを構えるため一寸でも動くと直ぐに飛び去る。
雀より遥かに小型だから、良く「オンマ谷」で望遠付きカメラで撮影している
「コマドリ」だろう。再び鞍部に戻る。ここで俄然やる気が沸いてさっきの
断崖を降りる事にした。西側から双耳の東ピークに突撃、途中に石宮の
天蓋のみが三体。

岸壁の下を慎重に観察、取り敢えず岩角を一段下がってみる。次ぎは木の根っ子に
足を掛けてもう一段、その調子で時間を掛けて下降。
最後は足掛かりが見付らず体操の吊り輪の要領で両手で木にぶら下がり
思い切ってそのまま飛び降りた。振り返ったらこんなところだが良く見ると
足掛かりはあるので登り返しには心配無し。

だが、その先は大荒れの岩稜線で僅か先に再び断崖、今度は全く
歯が立たない上に前方に露岩で掴まるところのないヤセ尾根が
見える。岩櫃山名物の岩の橋に似ている。どう見ても後期高齢者が
単独で挑戦するところではない。「村長さん」「柴犬さん」「カズさん」の
出番だろう。ここで遂に撤退を決断。

秋葉神社に戻って昼食・休憩(12.10-12.26)。
下山の途中で山百合が一株、ここなら採られないで過ごせるだろう。

駐車場所近くのお店には最近作ったらしい「OO坊」の看板多数。

さて、今度は車で33号線を榛名湖に向い、さっきの稜線と県道との交点を
探す。右の尾根を観察しながら約3K走行でそれらしき場所。
神社裏バス停の所に「榛名神社・天神峠」の道標(12.53)。


肝心の三角点位置を測定、どうやらこの造成防災壁の上だ。

上に登る階段が見付らないのでぐるっと上に廻って距離が縮まった所から
細い草を掴んで登り上げる。台地は草原状、遥かの上に白ポール発見。

草の下に三角点発見。これは国土院の「基準成果」には載っているのに
国土院地形図は勿論、地元の「榛名町全図」には載っていない不思議な
代物。點名・滝ノ平 1022.64m N-36-27-51-3 E-138-51-15-3

再びバス停に戻り一休みの後、今度は北からさっきの撤退地点まで行く
ことにする。道標に従って林間を進むと間も無く分岐、ここを右に進む。

なだらかな道を進むとコブを一つ経て最初のピーク、尾根が東南と南に
分岐しているので南を選択、榛名神社大祭記念植樹林標石を見て
調子よく進んだら地形図とは異なる下りに入り、不味いと思ったら
果して断崖上で行き止まり。

さっきの分岐が間違いと悟って戻ってやりなおし。東南路は直ぐに南に
廻りこんで今度は上手い具合に平坦稜線に乗る。やがて大きな倒木の
下を潜った辺りから巨木が目立つようになる。

大木と並んで本日の爺イの記念写真。

間も無く第二のピーク、例によって岩隗だ。だが観察すると右目に摺り跡が
あつたので這い登る。

その上から再び平坦な稜線、やがて今度は第三の岩隗、手前で途方に
くれるが、幸いにも左斜面にケモノ道のような足巾一つの踏み跡。
長い脇道を通過して稜線に戻るとやや危ないヤセ尾根だが平坦。
やがて前方に巨大トンガリ、これを越えればさっきの撤退地点まで
僅かに85mなのだが標高差が有り過ぎてこれは爺イには無理。

たしかに右脇に摺れ跡があるしリボンもあるのだが。まあ、多少インチキだが
この稜線は通過した事にしてしまおうと勝手に決めて帰路につく(13.59)。
途中でこんな珍しい苔のような物を見ながら駐車場所に帰着(14.30)。


ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

遊びの途中なのでぐっと我慢。榛名南麓中腹以上でタッチしてないのは
巌山・滝ノ平・宮沢の三点のみになったので今日はその内の二つを狙う。
設置場所は榛名神社西側を南北に走る岩稜帯の北端と南端。
通勤時間帯の渋滞を避けて榛名神社無料駐車場、第一目標の三角点・巌山の
ある筈の岩稜突端を見上げながら出発。

神社への参道途中から西の稜線ヘ登らなくてはならないので左手を注視しながら
進むと斜面に赤鳥居発見、踏み跡もある。

右手に大黒様の像や千本杉の看板のある所。

踏み跡は秋葉神社の掲額のある鳥居を潜りジグザク゛に蛇行しながら急斜面を
登っていく。
途中に石宮がひっそり、銘は「延亨五」とあるが延亨は四年までだから
「寛延元年」だろう。丁度、九代家重の時代、この三年後に吉宗が
68歳で相棒の大岡越前が75歳で亡くなっている。

更に登ると遥かの彼方にチラッと鳥居が見えた。やがて前面のコブは
終了して一登りで鳥居前の広場(9.56)。
が、社殿は無く多分これが残骸。

石宮六体が並ぶが銘は読めない。その前面に赤白ダンダラポールと三角点。

これが第一目標の四等三角点・巌山 940.28m N-36-27-20-8 E-138-50-58-3。

さて、一服の後、稜線の縦走に出発。地形図を見る限りこの尾根が県道33号線と
クロスする地点まで直線距離は僅かに1.2K程、さしたる高低差も見られない。
だが、懸念されるのは終点までに壁岩の摺り抜け2箇所、稜線が極度に狭い
所が一箇所、小ピークが五個。特に小ピークの等高線が小さな丸状で厭だ。
頂上が細長い等高線で囲まれていれば「台地」なので楽だが、小さい丸状の
ものは等高線一本でもトンガリの岩隗の事が多いから。
稜線には明瞭な踏み跡がありこんなリボンの目印や

黄色・赤色の杭が間断無く付けられている。6cm角の黄色のものは「保損調査」
とか「国調多角」、4cm角の赤杭はお馴染みの「地籍調査」

壁岩の付近はかなり厳しい急登で摺りぬけていく。

途中にこんなお化けキノコ、勿論種類などは判らない。

やがて第一ポイントの双耳ピークの東嶺に取り掛かるがいやはや凄いところ。

丁度、榛名神社本殿の西に相当するが下は樹葉が邪魔して社殿は見えず
直立した巨岩が杉林の中に微かに望めるだけ。錐の先のような頂点に
達してギョッとする。心配していた通りその先は断崖で前進不能。
回り道を探すため100㍍後退して西に見えた窪に降りそこから改めて
双耳ピークの鞍部を目指す。もし、鞍部に見える個所が乗り越しなら
回り道が在るかもしれないと思ったから。
何とか鞍部着、前方を見てガックリ。乗り越しではなく前面も崖だった。

悔しいから何かを期待して双耳の西ピークに向う。道無しの藪を掻い潜って
ピークに達するも何も無し。樹幹にここに来た証拠の二本巻きテープを残して
憂さ晴らし。

休憩中に気付いたが付近に多数の小鳥が飛び交っている。こっちが静止していると
直ぐ目の前まで寄ってくるが、カメラを構えるため一寸でも動くと直ぐに飛び去る。
雀より遥かに小型だから、良く「オンマ谷」で望遠付きカメラで撮影している
「コマドリ」だろう。再び鞍部に戻る。ここで俄然やる気が沸いてさっきの
断崖を降りる事にした。西側から双耳の東ピークに突撃、途中に石宮の
天蓋のみが三体。

岸壁の下を慎重に観察、取り敢えず岩角を一段下がってみる。次ぎは木の根っ子に
足を掛けてもう一段、その調子で時間を掛けて下降。
最後は足掛かりが見付らず体操の吊り輪の要領で両手で木にぶら下がり
思い切ってそのまま飛び降りた。振り返ったらこんなところだが良く見ると
足掛かりはあるので登り返しには心配無し。

だが、その先は大荒れの岩稜線で僅か先に再び断崖、今度は全く
歯が立たない上に前方に露岩で掴まるところのないヤセ尾根が
見える。岩櫃山名物の岩の橋に似ている。どう見ても後期高齢者が
単独で挑戦するところではない。「村長さん」「柴犬さん」「カズさん」の
出番だろう。ここで遂に撤退を決断。

秋葉神社に戻って昼食・休憩(12.10-12.26)。
下山の途中で山百合が一株、ここなら採られないで過ごせるだろう。

駐車場所近くのお店には最近作ったらしい「OO坊」の看板多数。

さて、今度は車で33号線を榛名湖に向い、さっきの稜線と県道との交点を
探す。右の尾根を観察しながら約3K走行でそれらしき場所。
神社裏バス停の所に「榛名神社・天神峠」の道標(12.53)。


肝心の三角点位置を測定、どうやらこの造成防災壁の上だ。

上に登る階段が見付らないのでぐるっと上に廻って距離が縮まった所から
細い草を掴んで登り上げる。台地は草原状、遥かの上に白ポール発見。

草の下に三角点発見。これは国土院の「基準成果」には載っているのに
国土院地形図は勿論、地元の「榛名町全図」には載っていない不思議な
代物。點名・滝ノ平 1022.64m N-36-27-51-3 E-138-51-15-3

再びバス停に戻り一休みの後、今度は北からさっきの撤退地点まで行く
ことにする。道標に従って林間を進むと間も無く分岐、ここを右に進む。

なだらかな道を進むとコブを一つ経て最初のピーク、尾根が東南と南に
分岐しているので南を選択、榛名神社大祭記念植樹林標石を見て
調子よく進んだら地形図とは異なる下りに入り、不味いと思ったら
果して断崖上で行き止まり。

さっきの分岐が間違いと悟って戻ってやりなおし。東南路は直ぐに南に
廻りこんで今度は上手い具合に平坦稜線に乗る。やがて大きな倒木の
下を潜った辺りから巨木が目立つようになる。

大木と並んで本日の爺イの記念写真。

間も無く第二のピーク、例によって岩隗だ。だが観察すると右目に摺り跡が
あつたので這い登る。

その上から再び平坦な稜線、やがて今度は第三の岩隗、手前で途方に
くれるが、幸いにも左斜面にケモノ道のような足巾一つの踏み跡。
長い脇道を通過して稜線に戻るとやや危ないヤセ尾根だが平坦。
やがて前方に巨大トンガリ、これを越えればさっきの撤退地点まで
僅かに85mなのだが標高差が有り過ぎてこれは爺イには無理。

たしかに右脇に摺れ跡があるしリボンもあるのだが。まあ、多少インチキだが
この稜線は通過した事にしてしまおうと勝手に決めて帰路につく(13.59)。
途中でこんな珍しい苔のような物を見ながら駐車場所に帰着(14.30)。


ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

















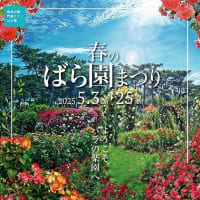



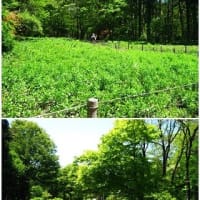






33号線を湖畔方面へ運転中のことでした、ちょうど神社裏手の藪の中から駐車場所へ到着(出現)したクタビレ殿と視線が合いました~
ちょっと急いでいたのでスルーしてしまいましたが、勇姿を拝見できて嬉しかったです!
あの場所から直ぐスタートしたので、ホンの一瞬の
遭遇ですね。
ヘアピンカーブの路線バス停専用スペースでの路傍駐車
だったので通過車両に気を付けていましたから多分、目付きも悪かったと思います。
あの後、夏の湖畔の景観を期待して榛名湖に行きましたが
霧か靄のようなものが立ち込めていて写真も撮れずに
126号線でのんびりと走って帰宅でした。