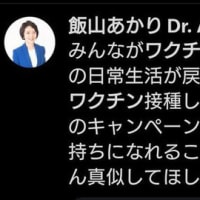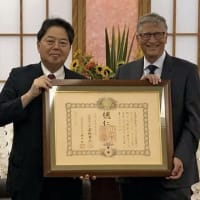学校に行けない…「不登校50年」が問い直すもの
4/22(日) 7:05配信 読売新聞(ヨミウリオンライン)
学校に行けない…「不登校50年」が問い直すもの
不登校新聞「不登校50年 証言プロジェクト」
文部省(当時)が学校基本調査で「学校嫌い」の統計を取り始めたのは1966年。日本で唯一の不登校・ひきこもり専門紙「不登校新聞」(NPO法人全国不登校新聞社)は2016年、半世紀の節目に「不登校50年 証言プロジェクト」をスタートさせた。不登校経験者、保護者、フリースクール、医師、教師、研究者ら30人を超える声を集め、今夏、連載を終える。「不登校50年」が問い直した問題は何か。このプロジェクトの統括、山下耕平氏に聞いた。(聞き手・読売新聞メディア局編集部 鈴木幸大)
◆「英語でタイは釣れん」
「だれも中学校をつくってくれと言うてない。英語を教えてくれる? 英語でタイは釣れん」
岡山県の児童相談所職員だった佐藤修策さんは、1947年(昭和22年)に中学校が義務教育化された当時のエピソードを紹介した。
瀬戸内海に面した倉敷市の漁村で、家庭訪問にまわると、中学校に行っていない生徒がゴロゴロいた。子どもに漁業を継がせたい父親は、釣りのイロハは学校では身につかないと主張した。「中学校は英語を学ぶことができるんですよ」。そう言って親を説得しようとしても、鼻で笑われた。
「子どもを学校へ通わせるのは親の義務です」。当時は、こんな立て看板があちこちにあった。「勉強がいやなら、さっさと働け」と言ってしまう教員もいた。
「学校に行かなければならない」という考え方もなく、不登校が問題になることもなかった。
◆「学校に行けない」
文部省は1950年に長期欠席者(年間30日以上の欠席者)の全国調査を初めて実施。この調査によって、49年度の長期欠席者は、小学校で約40万人(出現率4.15%)、中学校で約34万人(同7.6%)。小中合わせて約74万人いることが明らかになった。
家庭が貧しくて学校に通えない。病気がちで通学が難しい。農業や漁業などを営む家庭は幼い弟妹の面倒や家事の手伝いを優先させた。長期欠席は、経済的理由が59.6%を占めた。
ところが、60年ごろになると状況が変わった。はっきりとした理由がないのに欠席が長引く児童・生徒が現れた。
経済的に困窮しているわけでもなく、健康状態に問題があるわけでもない。にもかかわらず、精神科や児童相談所にこんな悩みを訴える子がいた。
「なぜだか分からないけれど、学校に行けない」
学校に行けないのは子どもに問題がある?
◆学校へ行こうとすると足がすくむ
精神医療の問題として議論が繰り返された。
学校に行けない――。その原因として、精神障害の一つである統合失調症、母親と離れると不調になる母子分離不安、自閉症、神経症などが疑われた。
しかし、徐々に、子どもに原因があるとする考え方に疑問符がついた。子どもではなく、学校の状況に問題があるのではないか。
国立精神衛生研究所(現・国立精神・神経医療研究センター)に勤務していた児童精神科医の中沢たえ子さんが1960年に「学校恐怖症の研究」を発表している。これが、日本で初めての不登校についてまとめられた論文とされる。
学校恐怖症は、高所恐怖症や閉所恐怖症といった状態と同じで、学校へ行くとなると思わず身構えてしまったり、足がすくんで前に進めなくなったりする体の反応だ。
◆病院内に「親の会」
不登校は、子どもの問題ではなく、解決には学校を変える必要があると訴えていたのは、元国立精神・神経センター国府台病院児童精神科医長の渡辺位さんだ。
「腐った物を食べたら下痢をする。下痢が問題なのではなく、細菌の繁殖した食べ物を摂取したのが原因であって、排出しようとするのは防衛反応。下痢の原因を見ないで、下痢だけを治そうとしてもだめ」
渡辺さんは1973年、病院の中で同じ悩みを抱える保護者が集まる「親の会」を設立した。
そこに集まった保護者らは、周囲から白い目で見られ、自責の念に悩まされていた。
「母親の育て方が悪いから、甘えた子になった」
「父親が厳しくしないから、子どもがわがままになった」
「自分の育て方が間違っていた……」
そういう見方にさらされながらも、親の会は、子どもの側に立って、学校のあり方を問い直していった。
学校に行けない…「不登校50年」が問い直すもの
「不登校新聞」の編集部(東京都北区)
当事者が語る「なぜ、学校に行けなくなったのか」
◆「自分は悪い子」と泣いた
「不登校50年」の連載には、学校に行けなくなった不登校経験者も登場する。1987年、小学4年のときに学校へ行かなくなった男性が当時の心境を打ち明けている。
「学校は絶対に行かねばならないと強く信仰していると、ちょっとの休みで、『いけないことをしてしまった。もう顔見せできない』と思って、1週間、2週間と休むようになって、それが1か月、2か月となって、どんどん行けなくなってしまう。私の場合は、そんな感じで学校に行けなくなって、『もう人生おしまいだ』と思っていました」
男性は「自分は悪い子だ」と親に訴えて泣き、物に当たり、苦しんだという。
◆「学校は行かなきゃいけない」
いじめをきっかけに不登校になったエピソードを語る当事者もいる。
高度経済成長期の1970年代に小学生だった男性だ。高等教育を満足に受けられなかった親世代が、子どもには教育を受けさせ、良い学校を出て、良い会社へという将来を望む社会の風潮があった。
進学熱が高まる一方で、放課後になると、草野球に興じる子どもたちもいる、そんな時代だった。だから、進学塾組と草野球組は対立することがあった。進学塾に行っている子たちは、テストの点数を伸ばし、偏差値を上げなきゃいけないというプレッシャーを背負わされた。自由気ままに草野球で遊ぶ同級生をねたましく思い、攻撃の対象にした。
「帰り道に隠れていて、いきなり6人がかりで蹴られたり、筆箱を隠されてしまったり、定規におしっこをかけられて、それを筆箱に入れられたり、いろいろ陰湿なことをされていました」
学校が安全な場所ではないと思った男性は、小学6年で学校に行けなくなった。それでも、「学校は行かなきゃいけないところ」「学校へ行かないことは大問題」という葛藤をずっと抱えていた。
不登校50年証言プロジェクト統括の山下さん
登校拒否は早期治療をしないと……
◆新聞記事に抗議集会
「30代まで尾引く登校拒否症 早期完治しないと無気力症に」
1988年9月、全国紙の夕刊1面に精神科医ら研究グループの見解が掲載された。登校拒否は早期に治療しないと無気力症の懸念があるとし、カウンセリングだけではなく複数の療法が必要と指摘した。
不登校や登校拒否を病気とする考え方は、本人が望まない強引な治療を招き、人権侵害につながりかねないと各地で抗議集会が開かれた。
一方で、不登校は早期発見、早期治療が必要とする考え方も根強く、学校に行きたくないという子を無理やり連れて行く保護者もいれば、家庭を訪問して子どもの部屋に押し入る教師もいた。自然豊かな専門施設で治療を求める希望者もいれば、スパルタ式の訓練施設へ子どもを送り込むようなケースもあった。
不登校を巡っては、80年代になって市民運動が活発になった。各地に親の会が設立され、全国規模の組織も発足した。居場所になるフリースクールやフリースペースなども増え、不登校の子どもたちが学校以外でも育っていることが実証されるようになった。
◆強硬策も「それでどうなの?」
不登校を取り巻く環境に変化が表れると、文部省(当時)は1992年、学校不適応対策調査研究の最終報告で「登校拒否はどの児童生徒にも起こり得る」との言葉を盛り込んだ。
さらに、文部科学省は2016年、「不登校を問題行動と判断してはならない」(16年9月14日「不登校児童生徒への支援の在り方について」)という通知を出している。
こうした行政の動きを歓迎する一方で、ソーシャルワーカーの男性は連載のインタビューでこう指摘する。
「かつては学校現場でも無理してでも行かせよう、学校復帰させるための努力をしなくちゃいけないというような空気があったように思います。いまはそうは言ってもヌカにクギみたいなもので、現実がもっと先を行っている感じはします。いま強硬策を出しても『それでどうなの?』みたいな感じになっちゃうんじゃないかなと」
統計上は毎年12万人以上が学校を休み続けている実態がある。男性の言葉は続く。
「一人ひとりはいろいろ葛藤があったとしても、不登校の数は毎年積み重なっているわけだから、その数の力というのは、無言の、無形のメッセージになっている」
かつて「希望」だった学校が、今は……
◆偏見は薄れても否定的なまなざし
当事者でさえ、不登校になった理由をはっきりと説明できないことが少なくない。朝、制服に着替えていると頭が痛くなる。玄関で靴をはいても足が前に出ない。
考えるよりも前に、体が反応する。こうなってしまったら、まず休むことが大切だ。いったんストップすることを否定してはいけない。
その後、どうするかはまた別の問題。最近では、不登校に対する偏見は薄れてきているが、平日の昼間、学校以外の場所にいる子どもたちに向けられるまなざしは、やはり否定的だ。
かつて、学校は「希望」だった。新しい知識を身につける。良い成績をとる。そして、良い学校へ合格する。「希望」が、学校の求心力になっていた。だから、ひとたび「学校に行かない」となれば、それは「絶望」を意味した。大問題だった。
しかし、ここ最近ニュースなどで話題になるブラック企業、過労自殺、老後破産といった問題を考えると、良い成績を収め、良い大学に進んだといっても、必ずしも先行きが明るいとは言えない。
学校は今、「不安」が求心力になっている。せめて高校、大学くらいは……、となってしまっている。
◆「不登校」から考える
「不登校」は、よく分からないけれど……という状況が実はあまり変わっていない。
ただ、不登校を考えることをきっかけに、精神医療や心理学が問い直されることになった。「子どもがおかしい」という考え方が変わってきた。学校に問題はないのか。教員の指導に課題はないのか。なぜ、学校に行かなければいけないのか。親たちが正しいと信じたことは、本当にそうだったのか。
「学校に行けない」。そう打ち明けた我が子を目の当たりにしたある男性は、自らの会社人生を顧みることになった。「お父さんはどうなの」。そう問いただされていると感じた。これが自分のやりたかったことなのか。このまま定年を迎えていいのか。自問を繰り返し、結局、退職に踏み切った。
学校、家族、仕事、生活……。「不登校」を巡る50年は、当たり前と思われてきた社会のあり方を問い直している。
不登校新聞プロジェクト統括 山下耕平
公立が一番の不条理、、玉石混合だ。
さらに中学になると社畜軍隊式に成る。日本人特有の硬直化した制度は変わらない。
これに感受性の高い生徒が拒否反応する。
4/22(日) 7:05配信 読売新聞(ヨミウリオンライン)
学校に行けない…「不登校50年」が問い直すもの
不登校新聞「不登校50年 証言プロジェクト」
文部省(当時)が学校基本調査で「学校嫌い」の統計を取り始めたのは1966年。日本で唯一の不登校・ひきこもり専門紙「不登校新聞」(NPO法人全国不登校新聞社)は2016年、半世紀の節目に「不登校50年 証言プロジェクト」をスタートさせた。不登校経験者、保護者、フリースクール、医師、教師、研究者ら30人を超える声を集め、今夏、連載を終える。「不登校50年」が問い直した問題は何か。このプロジェクトの統括、山下耕平氏に聞いた。(聞き手・読売新聞メディア局編集部 鈴木幸大)
◆「英語でタイは釣れん」
「だれも中学校をつくってくれと言うてない。英語を教えてくれる? 英語でタイは釣れん」
岡山県の児童相談所職員だった佐藤修策さんは、1947年(昭和22年)に中学校が義務教育化された当時のエピソードを紹介した。
瀬戸内海に面した倉敷市の漁村で、家庭訪問にまわると、中学校に行っていない生徒がゴロゴロいた。子どもに漁業を継がせたい父親は、釣りのイロハは学校では身につかないと主張した。「中学校は英語を学ぶことができるんですよ」。そう言って親を説得しようとしても、鼻で笑われた。
「子どもを学校へ通わせるのは親の義務です」。当時は、こんな立て看板があちこちにあった。「勉強がいやなら、さっさと働け」と言ってしまう教員もいた。
「学校に行かなければならない」という考え方もなく、不登校が問題になることもなかった。
◆「学校に行けない」
文部省は1950年に長期欠席者(年間30日以上の欠席者)の全国調査を初めて実施。この調査によって、49年度の長期欠席者は、小学校で約40万人(出現率4.15%)、中学校で約34万人(同7.6%)。小中合わせて約74万人いることが明らかになった。
家庭が貧しくて学校に通えない。病気がちで通学が難しい。農業や漁業などを営む家庭は幼い弟妹の面倒や家事の手伝いを優先させた。長期欠席は、経済的理由が59.6%を占めた。
ところが、60年ごろになると状況が変わった。はっきりとした理由がないのに欠席が長引く児童・生徒が現れた。
経済的に困窮しているわけでもなく、健康状態に問題があるわけでもない。にもかかわらず、精神科や児童相談所にこんな悩みを訴える子がいた。
「なぜだか分からないけれど、学校に行けない」
学校に行けないのは子どもに問題がある?
◆学校へ行こうとすると足がすくむ
精神医療の問題として議論が繰り返された。
学校に行けない――。その原因として、精神障害の一つである統合失調症、母親と離れると不調になる母子分離不安、自閉症、神経症などが疑われた。
しかし、徐々に、子どもに原因があるとする考え方に疑問符がついた。子どもではなく、学校の状況に問題があるのではないか。
国立精神衛生研究所(現・国立精神・神経医療研究センター)に勤務していた児童精神科医の中沢たえ子さんが1960年に「学校恐怖症の研究」を発表している。これが、日本で初めての不登校についてまとめられた論文とされる。
学校恐怖症は、高所恐怖症や閉所恐怖症といった状態と同じで、学校へ行くとなると思わず身構えてしまったり、足がすくんで前に進めなくなったりする体の反応だ。
◆病院内に「親の会」
不登校は、子どもの問題ではなく、解決には学校を変える必要があると訴えていたのは、元国立精神・神経センター国府台病院児童精神科医長の渡辺位さんだ。
「腐った物を食べたら下痢をする。下痢が問題なのではなく、細菌の繁殖した食べ物を摂取したのが原因であって、排出しようとするのは防衛反応。下痢の原因を見ないで、下痢だけを治そうとしてもだめ」
渡辺さんは1973年、病院の中で同じ悩みを抱える保護者が集まる「親の会」を設立した。
そこに集まった保護者らは、周囲から白い目で見られ、自責の念に悩まされていた。
「母親の育て方が悪いから、甘えた子になった」
「父親が厳しくしないから、子どもがわがままになった」
「自分の育て方が間違っていた……」
そういう見方にさらされながらも、親の会は、子どもの側に立って、学校のあり方を問い直していった。
学校に行けない…「不登校50年」が問い直すもの
「不登校新聞」の編集部(東京都北区)
当事者が語る「なぜ、学校に行けなくなったのか」
◆「自分は悪い子」と泣いた
「不登校50年」の連載には、学校に行けなくなった不登校経験者も登場する。1987年、小学4年のときに学校へ行かなくなった男性が当時の心境を打ち明けている。
「学校は絶対に行かねばならないと強く信仰していると、ちょっとの休みで、『いけないことをしてしまった。もう顔見せできない』と思って、1週間、2週間と休むようになって、それが1か月、2か月となって、どんどん行けなくなってしまう。私の場合は、そんな感じで学校に行けなくなって、『もう人生おしまいだ』と思っていました」
男性は「自分は悪い子だ」と親に訴えて泣き、物に当たり、苦しんだという。
◆「学校は行かなきゃいけない」
いじめをきっかけに不登校になったエピソードを語る当事者もいる。
高度経済成長期の1970年代に小学生だった男性だ。高等教育を満足に受けられなかった親世代が、子どもには教育を受けさせ、良い学校を出て、良い会社へという将来を望む社会の風潮があった。
進学熱が高まる一方で、放課後になると、草野球に興じる子どもたちもいる、そんな時代だった。だから、進学塾組と草野球組は対立することがあった。進学塾に行っている子たちは、テストの点数を伸ばし、偏差値を上げなきゃいけないというプレッシャーを背負わされた。自由気ままに草野球で遊ぶ同級生をねたましく思い、攻撃の対象にした。
「帰り道に隠れていて、いきなり6人がかりで蹴られたり、筆箱を隠されてしまったり、定規におしっこをかけられて、それを筆箱に入れられたり、いろいろ陰湿なことをされていました」
学校が安全な場所ではないと思った男性は、小学6年で学校に行けなくなった。それでも、「学校は行かなきゃいけないところ」「学校へ行かないことは大問題」という葛藤をずっと抱えていた。
不登校50年証言プロジェクト統括の山下さん
登校拒否は早期治療をしないと……
◆新聞記事に抗議集会
「30代まで尾引く登校拒否症 早期完治しないと無気力症に」
1988年9月、全国紙の夕刊1面に精神科医ら研究グループの見解が掲載された。登校拒否は早期に治療しないと無気力症の懸念があるとし、カウンセリングだけではなく複数の療法が必要と指摘した。
不登校や登校拒否を病気とする考え方は、本人が望まない強引な治療を招き、人権侵害につながりかねないと各地で抗議集会が開かれた。
一方で、不登校は早期発見、早期治療が必要とする考え方も根強く、学校に行きたくないという子を無理やり連れて行く保護者もいれば、家庭を訪問して子どもの部屋に押し入る教師もいた。自然豊かな専門施設で治療を求める希望者もいれば、スパルタ式の訓練施設へ子どもを送り込むようなケースもあった。
不登校を巡っては、80年代になって市民運動が活発になった。各地に親の会が設立され、全国規模の組織も発足した。居場所になるフリースクールやフリースペースなども増え、不登校の子どもたちが学校以外でも育っていることが実証されるようになった。
◆強硬策も「それでどうなの?」
不登校を取り巻く環境に変化が表れると、文部省(当時)は1992年、学校不適応対策調査研究の最終報告で「登校拒否はどの児童生徒にも起こり得る」との言葉を盛り込んだ。
さらに、文部科学省は2016年、「不登校を問題行動と判断してはならない」(16年9月14日「不登校児童生徒への支援の在り方について」)という通知を出している。
こうした行政の動きを歓迎する一方で、ソーシャルワーカーの男性は連載のインタビューでこう指摘する。
「かつては学校現場でも無理してでも行かせよう、学校復帰させるための努力をしなくちゃいけないというような空気があったように思います。いまはそうは言ってもヌカにクギみたいなもので、現実がもっと先を行っている感じはします。いま強硬策を出しても『それでどうなの?』みたいな感じになっちゃうんじゃないかなと」
統計上は毎年12万人以上が学校を休み続けている実態がある。男性の言葉は続く。
「一人ひとりはいろいろ葛藤があったとしても、不登校の数は毎年積み重なっているわけだから、その数の力というのは、無言の、無形のメッセージになっている」
かつて「希望」だった学校が、今は……
◆偏見は薄れても否定的なまなざし
当事者でさえ、不登校になった理由をはっきりと説明できないことが少なくない。朝、制服に着替えていると頭が痛くなる。玄関で靴をはいても足が前に出ない。
考えるよりも前に、体が反応する。こうなってしまったら、まず休むことが大切だ。いったんストップすることを否定してはいけない。
その後、どうするかはまた別の問題。最近では、不登校に対する偏見は薄れてきているが、平日の昼間、学校以外の場所にいる子どもたちに向けられるまなざしは、やはり否定的だ。
かつて、学校は「希望」だった。新しい知識を身につける。良い成績をとる。そして、良い学校へ合格する。「希望」が、学校の求心力になっていた。だから、ひとたび「学校に行かない」となれば、それは「絶望」を意味した。大問題だった。
しかし、ここ最近ニュースなどで話題になるブラック企業、過労自殺、老後破産といった問題を考えると、良い成績を収め、良い大学に進んだといっても、必ずしも先行きが明るいとは言えない。
学校は今、「不安」が求心力になっている。せめて高校、大学くらいは……、となってしまっている。
◆「不登校」から考える
「不登校」は、よく分からないけれど……という状況が実はあまり変わっていない。
ただ、不登校を考えることをきっかけに、精神医療や心理学が問い直されることになった。「子どもがおかしい」という考え方が変わってきた。学校に問題はないのか。教員の指導に課題はないのか。なぜ、学校に行かなければいけないのか。親たちが正しいと信じたことは、本当にそうだったのか。
「学校に行けない」。そう打ち明けた我が子を目の当たりにしたある男性は、自らの会社人生を顧みることになった。「お父さんはどうなの」。そう問いただされていると感じた。これが自分のやりたかったことなのか。このまま定年を迎えていいのか。自問を繰り返し、結局、退職に踏み切った。
学校、家族、仕事、生活……。「不登校」を巡る50年は、当たり前と思われてきた社会のあり方を問い直している。
不登校新聞プロジェクト統括 山下耕平
公立が一番の不条理、、玉石混合だ。
さらに中学になると社畜軍隊式に成る。日本人特有の硬直化した制度は変わらない。
これに感受性の高い生徒が拒否反応する。