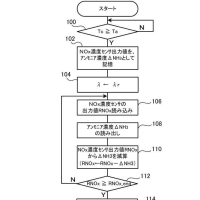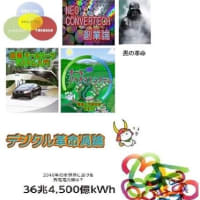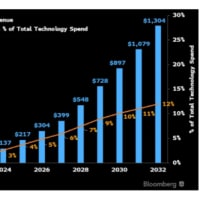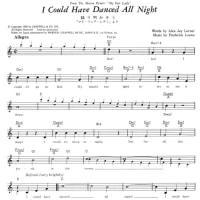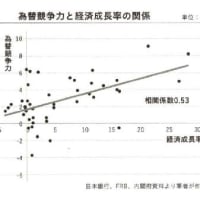知らぬまに 動き変りて 就いていけず 家庭崩壊 深層崩壊
■

【低木樹の旅 枸杞】
クコ(枸杞、学名:Lycium chinense)は、
中国原産のナス科の落葉低木。食用や
薬用に利用される。日本や朝鮮半島、
台湾などにも移入され、分布を広げて
いる外来種でもある。枝は長さ1m以上、
太さは数mm~1cmほどで、細くしなやか
で、地上部は束状で上向きに多くの枝
が伸びる。枝には2~5cm程度の葉と1~
2cm程度の棘が互生するが、枝分かれは
少ない。垂直方向以外に地上にも匍匐
茎を伸ばし、同様の株を次々と作って
繁茂する。海岸、河原、田畑の畦、空
き地の周囲など、人の手が加わりやす
く、高木が生えきれない環境によく生
える。ある程度湿り気のある水辺の砂
地を好む。性質は丈夫であり、しばし
ばハムシの一種トホシクビボソハムシ
(Lema decempunctata)の成虫や幼虫が
葉を強く食害したり、何種類かのフシ
ダニが寄生して虫癭だらけになったり
するが、それでもよく耐えて成長し、
乾燥にも比較的強い。

一旦定着すると匍匐茎を伸ばして増え
続け、数年後にはまとまった群落とな
ることが多い。開花期は夏~初秋で、
直径1cmほどの小さな薄紫色の花が咲
く。果実は長径1~1.5cmほどの楕円形
で赤く熟す。

■

【電動スクータ・バイクの実力】

2000年代頃からガソリン価格の高騰と
バッテリー性能の向上により、ガソリ
ンエンジンの代替として注目を受ける
様になった。二次電池を電源とした二
輪車が一般的だが、水素やメタノール
を用いた燃料電池、内燃機関と電動機
とのハイブリッド方式の試作車も開発
されている。
 EV-neo/ HONDA
EV-neo/ HONDAヤマハ発動機は9月1日、電動スクー
ター「EC-03」を首都圏で発売すると
いう。1回の満充電当たりの走行距離
は約43km。国内の量産車としては初め
て充電器を車両に搭載し、一般家庭で
も充電しやすくした。希望小売価格は
消費税込み25万2000円。国の補助金が
最大2万円受けられる。
 EC-03/YAMAHA
EC-03/YAMAHA高エネルギー密度の50Vリチウムイオ
ンバッテリーを新開発。1回の満充電
により30kmの定地走行で約43kwの走行
距離を実現。上り坂走行や停止などを
繰り返した場合でも航続距離は約25km
という。パワー・ユニットにダイレク
ト駆動方式を採用、低速時のトルクを
向上したほか、軽量アルミフレームの
ボディや全長1,565mmのコンパクト設計
により車両重量は56kg。同じタイプの
ガソリン車よりも3割軽い。
|
メーカ |
ヤマハ |
ホンダ |
|
型式 |
EC-03 |
EV-neo |
|
走行距離 km |
43 |
30 |
|
価格 man |
25.2 |
. |
|
最高出力 kw |
1.4 |
. |
|
最大トルク Nm/rpm |
9.6/280 |
. |
|
外形 mm |
1,565*600*990 |
1,820*693*1,066 |
|
車両重量 kg |
56 |
. |
|
バッテリ |
リチウムイオン |
リチウムイオン |
|
充電時間 hr |
6.0 |
4.0 |
バッテリーのリチウムイオンは三洋電
機製。気になるバッテリーの持ち具合
は、購入時の1回の満充電によるエネ
ルギ量を百%とすると、5百回満充電
を繰り返した場合、70%までエネルギ
量が減少する。バッテリーの交換は7
万5千円程度かかる見込み。
■
【リチウム蓄電池環境システム概論】
日本では、資源有効利用促進法により、
小形充電池(二次電池)の電池メーカ
と二次電池を使用する機器メーカおよ
びそれらの輸入事業者に、二次電池の
回収・リサイクルが義務付けられてい
る。二次電池の自主回収・再資源化は、
各企業が会員となり運営する「一般社
団法人JBRC」が構築・運営する回収シ
ステムによって行われているという。
JBRCによる二次電池の回収量は年間千
トンを超え、その回収量は年々増加し
ている。回収し処理した質量に対する
再資源化量(再資源化量=再資源化物
質量×金属元素含有率)の割合(再資
源化率)は、ニカド電池、ニッケル水
素電池で70%以上、リチウムイオン電
池で約60%を達成している。
2005年における世界のリチウムメタル
の生産量は2万1400トンであった。その
うち主要生産国はチリが8000トン、オ
ーストラリア4000トン、中国2700トン、
ロシア2200トンそしてアルゼンチンが
2000トンである。
世界のリチウム埋蔵量のうち、広大な
塩原のあるチリとボリビアで世界生産
量の7割を占める。チリ北部に位置す
るアタカマ塩原(Salar de Atakama)の
炭酸リチウムの生産量は年間5万トン。
未開発ではあるが埋蔵量ベースで世界
の30%近くはウユニ塩原(Salar de Uyuni)
にある。アタカマとウユニいずれも太
古の時代には内海が急激な造山活動で
標高3000メートル以上になり、水が永
い間かけて干上がった極めて珍しい地
形だという。
リチウムの生産方法は大きく塩湖から
塩水を汲み上げて濃縮させた後に炭酸
リチウム精製を行う方法と、鉱床から
鉱石を採掘する方法に分けられる。世
界のリチウム生産において塩水からの
生産が全体に占める割合が大きい。そ
れ以外には海水に含まれるリチウムを
直接濃縮する方法の開発が行われてい
るが実用化には時間がかかりそうだ。
また、リサイクルによるリチウムの回
収による再資源化の研究開発は盛んに
取り組まれているがこれも実用化の目
処が立つまでに至っていないという。
リサイクル実用化技術が不確定であっ
ても「原料生産→リチウム電池生産→
使用現場→回収・再資源化」の全景を
画像形成し(1)物質収支(2)エネ
ルギ収支(3)二酸化炭素量排出収支
の試算と連関図作成を急いで行う必要
がある(要調査)。
■ 絵付きダム用語解説集
絵付きダム用語解説集
【治水ダムと雨水貯蔵システム】
半世紀ぶりの集中豪雨の被害が刻々と
テレビ放送されている見ながら。故鹿
野昭三県会議員(「彦根市の市民の飲
み水を守る会々会員)のでかい眼鏡顔
が浮かんだ。「流域下水道の処理水を
ポンプアップして川上に循環放流して
はどうか」という。流域下水道は(1)
処理できない工業廃水など(法規制を
クリアを前提として)受入れるという
問題以外に(2)流域の小川や河川が
消えるという問題を抱えているという、
当時、中西準子教授などを交え喧々諤
々と議論し、馬鹿げたような話だが循
環すれば問題解決するのではという対
案が出された。
■
よくよく考えてみれば、処理水を揚水
するという「渇水対策」は、裏返せば
「洪水対策」になる。それも揚水には
位置+管抵抗分のエネルギを必要とす
るが「洪水対策」は基本的に位置エネ
ルギがそのまま利用できる。琵琶湖を
緩衝機能として限定利用できるので、
高価なダム建設は不要となり要所要所
に小規模なダムポイントをもうければ
限定的に洪水対策用下水バイパス・ネ
ットワークとして使用できではないか
と気がついた。滋賀県は、その意味で
は環境型先端技術自治体ではないかと
頬をつねり、鹿野昭三氏の供養になる
のかと思い立った。
図 東大阪トラックターミナル新管理棟の環境設備
※中沢新一『モノ的技術の復権』の補
足→「太古の哲学を復元すると人間存
在は、タマ(純粋意識)+シヰ(心理
体)+モノ(物的肉体)の三層から構
成され、この三つの層においてunit body
(個体)とcollective body(集合体)の両
方における人間解放(人類解放)を考
える必要がある」(吉見道夫)とある。
■