
京都の言葉や習慣は外から来た者には分からないところもあります。
たとえば「どんつき」。
突き当たりのことですが、最初はびっくりした言葉です。
また、「あさばて」に会議をするなどと聞いて、全然分かりませんでした。
朝からバテていたら、どうするんだろうと思いました。(笑)
朝のこと(お寺でいえば朝のお勤め)が「果てて」から、つまり朝のお勤めが終わってから、終わった直後、そのまま会議に入るということでした。
開導日扇聖人は京都生まれで京都育ち。
そして裕福な文人の家系に誕生されたのが1817年。今から191年前です。
家業については諸説ありますが、その父君に当たる大路延貞という人が「長松堂」の名で出版をしている事実がありますから、「書肆」・・出版まで行う本屋さんだったのでしょう。奈良の博物館に寛政五年(1793)に大路延貞(治郎右衛門)が序(跋)を書き、長松堂板として出版した「柳春帖」という本が所蔵されているそうです。
21日は暦の上でいちばん暑い「大暑」とか。この暑い夏、冷房していても私たち、ネをあげてしまいそうです。
温暖化などと無縁だった昔でも京都は暑かったようです。
街角でなのか、川原でなのかしりませんが、「夕涼み」しながらお酒を飲む光景が見られたのでしょう。
開導日扇聖人は
「七月の上旬のころ」と題されて
人はみな すゞみ台にて 酒をのむ われは座敷で すゞみ学文
と御教歌をよまれています。
また、
世は夏の 川原涼みの 時くれど 人のこゝろは 冬ごもり哉
というお歌もあります。
京都ではいまも、「川床」などと称して、鴨川などの川原に夕涼みをしながら食事を楽しみ、お酒を飲む人も多いようです。これを「すゞみ台」といわれているのでしょうか。
これも予約満杯で、なかなか席を取るのも大変みたい。
「すずみ学文」もキツイですね。
まぁ、どこかで夕食をいただき、その後はホテルで涼みますかね。
たとえば「どんつき」。
突き当たりのことですが、最初はびっくりした言葉です。
また、「あさばて」に会議をするなどと聞いて、全然分かりませんでした。
朝からバテていたら、どうするんだろうと思いました。(笑)
朝のこと(お寺でいえば朝のお勤め)が「果てて」から、つまり朝のお勤めが終わってから、終わった直後、そのまま会議に入るということでした。
開導日扇聖人は京都生まれで京都育ち。
そして裕福な文人の家系に誕生されたのが1817年。今から191年前です。
家業については諸説ありますが、その父君に当たる大路延貞という人が「長松堂」の名で出版をしている事実がありますから、「書肆」・・出版まで行う本屋さんだったのでしょう。奈良の博物館に寛政五年(1793)に大路延貞(治郎右衛門)が序(跋)を書き、長松堂板として出版した「柳春帖」という本が所蔵されているそうです。
21日は暦の上でいちばん暑い「大暑」とか。この暑い夏、冷房していても私たち、ネをあげてしまいそうです。
温暖化などと無縁だった昔でも京都は暑かったようです。
街角でなのか、川原でなのかしりませんが、「夕涼み」しながらお酒を飲む光景が見られたのでしょう。
開導日扇聖人は
「七月の上旬のころ」と題されて
人はみな すゞみ台にて 酒をのむ われは座敷で すゞみ学文
と御教歌をよまれています。
また、
世は夏の 川原涼みの 時くれど 人のこゝろは 冬ごもり哉
というお歌もあります。
京都ではいまも、「川床」などと称して、鴨川などの川原に夕涼みをしながら食事を楽しみ、お酒を飲む人も多いようです。これを「すゞみ台」といわれているのでしょうか。
これも予約満杯で、なかなか席を取るのも大変みたい。
「すずみ学文」もキツイですね。
まぁ、どこかで夕食をいただき、その後はホテルで涼みますかね。



















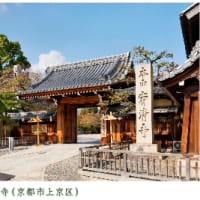






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます