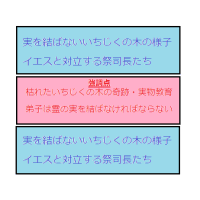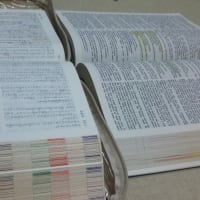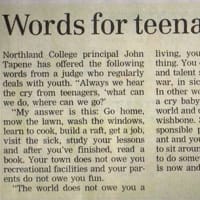実際にはもうちょっと違った目的意識を持って取り組んだものでしたので、常体の文で書き始めてしまいました。上手に整理できていないのはわかっているのですが、取り合えずアップさせていただきたいと思います。目的というのは、普通の信徒でも手順を踏んで聖書の述べている事柄の意味を整理して、その意味を確かめることができるというシミュレーションというか、モデルを示すということでした。
マルコ4章21節~25節 ぺリコーぺの意味を探る
―22節の意味を明確にする―
はじめに
この作業は、22節に関する疑問から始まった。
なんでも、隠されているもので、現れないものはなく、秘密にされているもので、明るみに出ないものはない。(口語訳聖書)
この句は、陰でこそこそ為された悪事も必ず明るみに出るということを示すために度々引用されるものの一つである。しかし、そのような引用が、テキストの元来の意味から考える時に、はたして適切であるのだろうか。
そこで、次のような手順でその部分の意味するところの確認を進めることにした。
1.該当テキストの前後関係を確認し、大きな括りを確認する。
2.該当テキストの部分の主たる意味を確認する。
3.該当テキストにおける22節の特定の意味を確認する。
1.該当テキストの前後関係を確認し、大きな括りと意味上の流れを確認する。
該当テキストの23節には「聞く耳のある者は聞くがよい」という言葉が述べられているが、それが9節にも現れている。何らかの共通のテーマを持っていると考えることができる。
9節は、4章1節~20節で一まとまりのぺリコーぺの一部である。そして、そのはじめの方に、イエスが譬を用いて多くのことを教えたということが示されている。すると、そこから続く譬は、この導入に続くまとまった譬の例示ということになる。後の方に目を転じて見ると、からし種の譬の後に、33節、34節でキリストが譬を用いて教えられた事実のまとめが述べられている。すると、該当テキストを含む大きなまとまりは、4章の1節から34節までと見ることができる。
この箇所の良い土地の譬、あかりの譬、育つ種の譬、からし種の譬の四つで構成されている。最初の二つは、先にも述べたとおり、「聞く耳のある者は聞きなさい」という言葉が共通しており、後の二つは「神の国」が共通のテーマであることが26節と30節からわかる。
この箇所のテーマを一つに絞ることができるかどうか考える。先に示したとおり、前半と後半の二部に分けられると考えることもできる。イエスの宣教は、神の国の宣教であったし、聞く耳を持つことが要求されるのは、神の教えを正しい態度で受け入れるようにという警告を含んでいることを考えると、四つの譬は「神の国」というテーマで貫かれていると言える。手元にある注解のアウトラインを確認したが、どれもが「神の国」をこの箇所のテーマとして示していた。
2.該当テキストの部分の主たる意味を確認する。
該当テキストは4章21節から25節までである。24節~25節は別の区分になるかどうかを確認したが、細かく項目立てをしている注解でも、ここを別に取り分けている例は見当たらなかった。23節の「聞く耳のある者は聞くが良い」という言葉と、24節のはじめの「聞くことがらに注意しなさい」という言葉が文脈的つながりを示していると考えられる。それが、そこまで含めてあかりの譬のまとまりであるとする伝統的理解の理由と推察できる。
ここで理解の助けになるのは、3節から20節の、よい土地の譬である。この箇所は、「聞く耳のある者は聞きなさい」という言葉が共通している上に、キリスト自身の解説が付されている。聞く耳があってきちんと聞て受け入れた者は、良い地であり、多くの実を結ぶことができる。この原則を元にして該当テキストの意味を考えていくことになる。
特に聞いて受け入れるというつながりでの理解が容易なのは、後半の24、25節である。あなたがたの量るはかりで、自分にも量り与えられるというのは、神の国の宣教をどう判断するかによって、神の国の恵みを受け取る度合いが違うということを表している。そして、きちんと神の国の福音の言葉を持っている者は、更にその恵みを受けることになり、キリストの宣教の言葉をきちんと評価しない者は、持っていると思っている神の国の恵みでさえ失うことになるのである。それが、土地の譬では様々な悪い土地に落ちた種の姿と重なる。このことを元にして21節、22節を考えると、理解できるようになってくる。
あかりを点ける時、そのあかりは当然置かれるべき位置が有る。神の国の宣教の言葉も、当然の評価を得るならば、敬意を持って受け入れられたならば、その人の心のしかるべきところに位置を占め、その者の思いを照らすことになる。反対に、神の国の宣教の言葉を受け入れなかったり、その価値を認めなかったり、無視する態度の者は、あかりを器や食卓の下に置くような行為だということになる。
今回その意味を確認しようとしている「なんでも、隠されているもので、現れないものはなく、秘密にされているもので、明るみに出ないものはない。」は、そのあかりの譬と量りのはなしに挟まれているのである。
3.該当テキストにおける22節の特定の意味を確認する。
先に確認した流れを元に隠されているもの、秘密にされているものが何であるかを考えるのだが、先に幾つかの語の意味を確認する。「隠されている」「秘密にされている」という内容の語は、元来どんな意味合いが含まれているのだろうか。以下に、ストロングスにおける定義を参照する。
「隠されている」という語はクルプトスという形容詞で、ストロングズによると、プライベートなという意味合いにおいて「隠されている、内側の、秘密」という語感である。
「秘密にされている」という語はアポクルフォスという形容詞で、大事にされている、大切にされているという示唆を伴って、「秘密にされている」という意味がある。
これらを踏まえた上で該当の箇所の意味を考える。プライベートで内側の、大事にされている事柄が、この聖書箇所の文脈から考えると神の国とその宣教の言葉であることは明らかである。しかし、それらは神の国の宣教の言葉を聞いた者の心の中のことであるから、直ぐには周囲の人にはわからないものである。それでも、本当に神の国を受け入れた者は、その行動や生活にそれが反映され、徐々に周囲の人々にも明らかになってくるものだ。それがこの箇所の意味するところであると結論付けることができると考えられる。
当時キリストの周囲には多くの人々が教えを聞きに集まったが、彼らが本当に神の国の宣教の言葉を受け入れたかどうかは、その時点では不明であった。しかし、それはいずれ明らかになる。キリストは、そのことを念頭に入れて、きちんと神の国の宣教の言葉を評価し受け入れたかは、後には明らかになるのだから、注意して聞くようにと警告したことになる。集まった者たちの中には、キリストを利用しようと考えたり、敵対心を持っていたりする者が含まれていた。そういうことも後には明らかになるということを予告する意味も含まれていたと考えられる。
まとめ
該当の聖書箇所、マルコ4章21~25節は、前後の譬が農事や植物を使ったものであるのに、そこだけあかりや量りの話しが用いられているため、異質な印象を与える。しかし、神の国という共通のテーマを持っており、植物や農作物のできは後になってわかるように、神の国を受け入れたかどうかは後になって明らかになるという点でも類似点、共通点が有るということが明らかになった。
隠されているもの、秘密にされているものが、外見からは神の国を聞いて受け入れたかはわからないということを現していることがわかったので、隠れたところで為された悪事は必ず知られるようになるということを述べるためにこの箇所を引用するのは適切ではないと判断できる。必要ならば、もっと相応しい聖書箇所を見つけて引用するべきである。他の福音書に現れる類似の表現の意味の確認、もっと引用に相応しい聖書箇所の確認については、次の機会に述べる。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。
マルコ4章21節~25節 ぺリコーぺの意味を探る
―22節の意味を明確にする―
はじめに
この作業は、22節に関する疑問から始まった。
なんでも、隠されているもので、現れないものはなく、秘密にされているもので、明るみに出ないものはない。(口語訳聖書)
この句は、陰でこそこそ為された悪事も必ず明るみに出るということを示すために度々引用されるものの一つである。しかし、そのような引用が、テキストの元来の意味から考える時に、はたして適切であるのだろうか。
そこで、次のような手順でその部分の意味するところの確認を進めることにした。
1.該当テキストの前後関係を確認し、大きな括りを確認する。
2.該当テキストの部分の主たる意味を確認する。
3.該当テキストにおける22節の特定の意味を確認する。
1.該当テキストの前後関係を確認し、大きな括りと意味上の流れを確認する。
該当テキストの23節には「聞く耳のある者は聞くがよい」という言葉が述べられているが、それが9節にも現れている。何らかの共通のテーマを持っていると考えることができる。
9節は、4章1節~20節で一まとまりのぺリコーぺの一部である。そして、そのはじめの方に、イエスが譬を用いて多くのことを教えたということが示されている。すると、そこから続く譬は、この導入に続くまとまった譬の例示ということになる。後の方に目を転じて見ると、からし種の譬の後に、33節、34節でキリストが譬を用いて教えられた事実のまとめが述べられている。すると、該当テキストを含む大きなまとまりは、4章の1節から34節までと見ることができる。
この箇所の良い土地の譬、あかりの譬、育つ種の譬、からし種の譬の四つで構成されている。最初の二つは、先にも述べたとおり、「聞く耳のある者は聞きなさい」という言葉が共通しており、後の二つは「神の国」が共通のテーマであることが26節と30節からわかる。
この箇所のテーマを一つに絞ることができるかどうか考える。先に示したとおり、前半と後半の二部に分けられると考えることもできる。イエスの宣教は、神の国の宣教であったし、聞く耳を持つことが要求されるのは、神の教えを正しい態度で受け入れるようにという警告を含んでいることを考えると、四つの譬は「神の国」というテーマで貫かれていると言える。手元にある注解のアウトラインを確認したが、どれもが「神の国」をこの箇所のテーマとして示していた。
2.該当テキストの部分の主たる意味を確認する。
該当テキストは4章21節から25節までである。24節~25節は別の区分になるかどうかを確認したが、細かく項目立てをしている注解でも、ここを別に取り分けている例は見当たらなかった。23節の「聞く耳のある者は聞くが良い」という言葉と、24節のはじめの「聞くことがらに注意しなさい」という言葉が文脈的つながりを示していると考えられる。それが、そこまで含めてあかりの譬のまとまりであるとする伝統的理解の理由と推察できる。
ここで理解の助けになるのは、3節から20節の、よい土地の譬である。この箇所は、「聞く耳のある者は聞きなさい」という言葉が共通している上に、キリスト自身の解説が付されている。聞く耳があってきちんと聞て受け入れた者は、良い地であり、多くの実を結ぶことができる。この原則を元にして該当テキストの意味を考えていくことになる。
特に聞いて受け入れるというつながりでの理解が容易なのは、後半の24、25節である。あなたがたの量るはかりで、自分にも量り与えられるというのは、神の国の宣教をどう判断するかによって、神の国の恵みを受け取る度合いが違うということを表している。そして、きちんと神の国の福音の言葉を持っている者は、更にその恵みを受けることになり、キリストの宣教の言葉をきちんと評価しない者は、持っていると思っている神の国の恵みでさえ失うことになるのである。それが、土地の譬では様々な悪い土地に落ちた種の姿と重なる。このことを元にして21節、22節を考えると、理解できるようになってくる。
あかりを点ける時、そのあかりは当然置かれるべき位置が有る。神の国の宣教の言葉も、当然の評価を得るならば、敬意を持って受け入れられたならば、その人の心のしかるべきところに位置を占め、その者の思いを照らすことになる。反対に、神の国の宣教の言葉を受け入れなかったり、その価値を認めなかったり、無視する態度の者は、あかりを器や食卓の下に置くような行為だということになる。
今回その意味を確認しようとしている「なんでも、隠されているもので、現れないものはなく、秘密にされているもので、明るみに出ないものはない。」は、そのあかりの譬と量りのはなしに挟まれているのである。
3.該当テキストにおける22節の特定の意味を確認する。
先に確認した流れを元に隠されているもの、秘密にされているものが何であるかを考えるのだが、先に幾つかの語の意味を確認する。「隠されている」「秘密にされている」という内容の語は、元来どんな意味合いが含まれているのだろうか。以下に、ストロングスにおける定義を参照する。
「隠されている」という語はクルプトスという形容詞で、ストロングズによると、プライベートなという意味合いにおいて「隠されている、内側の、秘密」という語感である。
「秘密にされている」という語はアポクルフォスという形容詞で、大事にされている、大切にされているという示唆を伴って、「秘密にされている」という意味がある。
これらを踏まえた上で該当の箇所の意味を考える。プライベートで内側の、大事にされている事柄が、この聖書箇所の文脈から考えると神の国とその宣教の言葉であることは明らかである。しかし、それらは神の国の宣教の言葉を聞いた者の心の中のことであるから、直ぐには周囲の人にはわからないものである。それでも、本当に神の国を受け入れた者は、その行動や生活にそれが反映され、徐々に周囲の人々にも明らかになってくるものだ。それがこの箇所の意味するところであると結論付けることができると考えられる。
当時キリストの周囲には多くの人々が教えを聞きに集まったが、彼らが本当に神の国の宣教の言葉を受け入れたかどうかは、その時点では不明であった。しかし、それはいずれ明らかになる。キリストは、そのことを念頭に入れて、きちんと神の国の宣教の言葉を評価し受け入れたかは、後には明らかになるのだから、注意して聞くようにと警告したことになる。集まった者たちの中には、キリストを利用しようと考えたり、敵対心を持っていたりする者が含まれていた。そういうことも後には明らかになるということを予告する意味も含まれていたと考えられる。
まとめ
該当の聖書箇所、マルコ4章21~25節は、前後の譬が農事や植物を使ったものであるのに、そこだけあかりや量りの話しが用いられているため、異質な印象を与える。しかし、神の国という共通のテーマを持っており、植物や農作物のできは後になってわかるように、神の国を受け入れたかどうかは後になって明らかになるという点でも類似点、共通点が有るということが明らかになった。
隠されているもの、秘密にされているものが、外見からは神の国を聞いて受け入れたかはわからないということを現していることがわかったので、隠れたところで為された悪事は必ず知られるようになるということを述べるためにこの箇所を引用するのは適切ではないと判断できる。必要ならば、もっと相応しい聖書箇所を見つけて引用するべきである。他の福音書に現れる類似の表現の意味の確認、もっと引用に相応しい聖書箇所の確認については、次の機会に述べる。
↑
よろしかったらクリックにご協力ください。