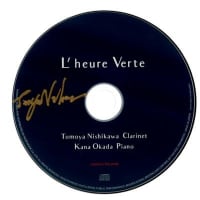岡田暁生著「音楽の聴き方」(中公新書)を読みました。2009年に発行され、本書により著者は第19回吉田秀和賞を受賞しています。

表紙
(著者について)
著者の岡田暁生(おかだ あけお)さんは、1960年、京都市生まれ、京都大学人文科学研究所教授。「オペラの運命」(サントリー学芸賞受賞)、「西洋音楽史」、「すごいジャズには理由がある」など著書多数。詳しくは下記をご覧ください。
(記載されているの内容紹介)

(大まかな目次)
第1章 音楽と共鳴するとき
相性のメカニズム、時間の共有としての音楽体験
第2章 音楽を語る言葉を探す
音楽を「する」/「聴く」/「語る」の分裂、音楽は言葉で作られる?、「わざ言語」を作り出す
第3章 音楽を読む
音楽/言語の分節規則、「音楽は国境を越える」というイデオロギー
第4章 音楽はポータブルか?
未知のものとして音楽を聴くこと
第5章 アマチュアの権利
「聴く」から「する」へ
おわりに 聴き上手へのマニュアル
他人の意見は気にしない。音楽は視なければわからない。音楽を言葉にすることを躊躇しない。
(感想など)
現代の音楽現場では、作曲する人、演奏する人、聴く人と分化し、演奏はプロに任されているのが実情ですが、聴く人は、聴いた音楽についていろいろと語るべきだというのが著者の姿勢で、この姿勢には共感しました。
もっとも、この「語る」というのがなかなか難しいのですが、『聴く型や趣味を語る言葉』を見つける努力を行うべきだとあります。例えば、指揮者のリハーサルを録画したDVDを観たり、楽器をやってみたりすることを奨めています。
著者は、『音楽も言語であって、文法と語彙を知らないと理解できない。サウンドとしての音楽はグローバルだが、言語としての音楽はローカルである。』と記し、様々な例を挙げて論証している第3章が、特に面白く記憶に残ります。
(著者略歴)
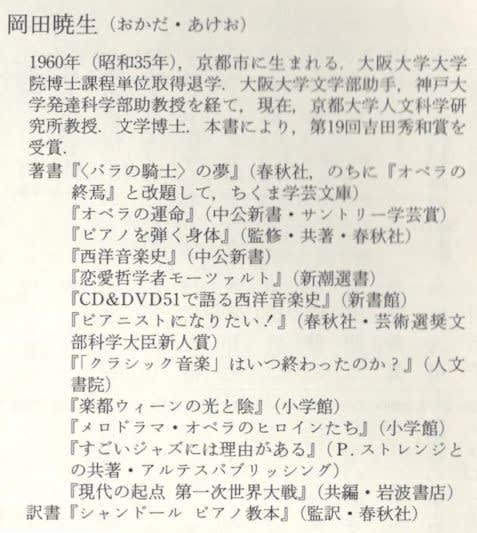
(目次の全部)


【シューベルト ピアノソナタ第17番 ニ長調 D850】
著者が村上春樹の文章を引用して、シューベルトのソナタ第17番について記しています(本書p78~p80)。同曲をリチャード・グードの演奏で聴いてみました。1966年にマイク眞木がヒットさせた「バラが咲いた」と似たフレーズが、同曲に出てくるので、『バラが咲いたソナタ』と呼ぶ人もいるようです。

リチャード・グード(p)シューベルト・ピアノ・ソナタ集(第16・17・19~21番他)(タワー・レコード発売のCD3枚組、NONESUCH原盤)
(アンドラーシュ・シェフの演奏)
**♪シューベルト:ピアノ・ソナタ第17番 ニ長調 「ガシュタイナー・ソナタ」 Op. 53, D. 850 / アンドラーシュ・シフ(ピアノ) 1992年11月 - YouTube