§23
Recht und Moral sind von einander unterschieden. Es kann, dem Rechte nach, etwas sehr wohl erlaubt sein, was die Moral verbietet. Das Recht z. B. erlaubt mir die Disposition über mein Vermögen auf ganz unbestimmte Weise, allein die Moral enthält Bestimmungen, welche dieselbe einschränken. Es kann scheinen, als ob die Moral Vieles erlaubt, was das Recht nicht erlaubt, allein die Moral fordert nicht nur die Beobachtung des Rechts gegen Andere, sondern setzt zum Recht vielmehr die Gesinnung hinzu, das Recht um des Rechtes willen zu respektieren. Die Moral fordert selbst, dass zuerst das Recht beobachtet werde und da, wo es aufhört, treten moralische Bestimmungen ein.(※1)
二十三〔法と道徳について〕
法と道徳は互いに区別される。道徳が禁じていることであっても、法律によれば許されるといったことは、よくあることである。法が、たとえば、私の財産をまったく好き勝手なやり方で処分することを認めているとしても、しかし、その同じことを道徳においてはさまざまに制限する規範があるなど。道徳は法律では許されていない多くのことを許しているように見える。しかしながら、道徳は他者に対して法の遵守を要求するのみでなく、むしろ、なおそれ以上に、法のために法を尊重する心情をもつちかうものである。道徳は自ら、まず法律の守られることを要求するが、その法律の途絶えるところに、道徳のさまざまな規定が入り込んでくるのである。
Damit eine Handlung moralischen Werth habe, ist die Einsicht notwendig, ob sie recht oder unrecht, gut oder böse sei. Was man Unschuld der Kinder oder unzivilisierter Nationen nennt, ist noch nicht Moralität. Kinder oder solche Nationen unterlassen eine Menge böser Handlungen, weil sie noch keine Vorstellung davon haben, weil überhaupt noch nicht die Verhältnisse vorhanden sind, unter welchen allein solche Handlungen möglich werden; solches Unterlassen böser Handlungen hat keinen moralischen Werth. Sie tun aber auch Handlungen, die der Moral gemäß und deswegen doch nicht gerade moralisch sind, insofern sie keine Einsicht in die Natur der Handlung haben, ob sie gut oder böse.(※2)
ある行為が道徳的な価値をもつためには、その行為が正しいか不正であるか、善であるか悪であるかについての判断力が必要である。人々が子供や未開の民族の無邪気さと呼んでいるものは、いまだなお道徳ではない。子供たちやそうした未開の民族が多くの悪しき行為をなさないのは、彼らがまだ行為についての判断力をもたないからであり、ただ一般に道徳的な行為が可能であるような状況に置かれていないからである。;悪しき行為をこのように行わないことには何ら道徳的な価値はない。しかしまた、彼らが道徳に適った行為もするし、さらにまた反対に必ずしも道徳的ではない行為も行うのも、その行為の性質が善であるのか悪であるのかどうか、彼らは判断力をもたないからである。
Der eigenen Überzeugung steht der bloße Glaube auf die Autorität Anderer entgegen. Wenn meine Handlung moralischen Werth haben soll, so muss meine Überzeugung damit verknüpft sein. Die Handlung muss im ganzen Sinn die meinige sein. Handle ich aber auf die Autorität Anderer, so ist sie nicht völlig die meinige; es handelt eine fremde Überzeugung aus mir. Es gibt aber auch Verhältnisse, in denen es die moralische Seite ist, gerade aus Gehorsam und nach Autorität Anderer zu handeln. Ursprünglich folgt der Mensch seinen natürlichen Neigungen ohne Überlegung oder mit noch einseitigen, schiefen und unrichtigen, selbst unter der Herrschaft der Sinnlichkeit stehenden Reflexionen. In diesem Zustand muss er gehorchen lernen, weil sein Wille noch nicht der vernünftige ist. Durch dies Gehorchen kommt das Negative zu Stande, dass er auf die sinnliche Begierde Verzicht tun lernt und nur durch diesen Gehorsam gelangt der Mensch zur Selbstständigkeit.(※3)
自己の確信に対立するものは、他人の権威に対する単なる信仰である。もし私の行為が道徳的な価値をもちうるとすれば、私の確信と結びついていなければならない。行為は全き意味において私のものでなければならない。しかし、私が他人の権威にもとづいて行動するなら、その行動は全く私のものではない。他人の確信が私をとおして働いているのである。しかし、従順さから、そして、他人の権威に従って行為することが、まさに道徳的な趣をもつような状況もある。そもそも生まれついて人間は思慮の欠いたその自然の傾向から、あるいは、なお一方的で歪んだ、正しくない感性に自ら隷属した反省に追従する。この状態においては、いまだなお彼の意志は理性的ではないから、彼は服従することを学ばなければならない。この服従を通して、自己否定の立場に至って、そうして彼は肉体的な欲望を抑制することを学ぶ。そうして、ただこの服従を通してのみ、人間は自立性を獲得する。
Er folgt in dieser Sphäre immer einem Anderen, ebensosehr, wenn er seinem eigenen, im Ganzen noch sinnlichen Willen, oder dem Willen eines Anderen gehorcht. Als Naturwesen steht er eines Teils unter der Herrschaft äußerlicher Dinge, andererseits aber sind diese Neigungen und Begierden etwas Unmittelbares, Beschränktes, Unfreies oder ein Anderes, als sein wahrhafter Wille.(※4)
人間はこの道徳の領域ではつねに他者に追従している。自分自身に固有の意志や、なお身体からくる欲望の意志においては完全に、まったく同じように他者の意志に追従している。自然の存在として人間は、部分的には外部の事物の支配されており、しかし、他面においては、これらの傾向や欲求は、直接的なもの、制限されたもの、不自由なものであり、あるいはまた、人間の真実の意志とは別のものである。
Der Gehorsam gegen das Gesetz der Vernunft ist Gehorsam in Beziehung auf meine unwesentliche Natur, welche unter der Herrschaft eines für sie Anderen steht. Allein auf der anderen Seite ist er selbstständige Bestimmung aus sich selbst, denn eben dieses Gesetz hat seine Wurzel in meinem Wesen. Die Gesinnung ist also bei der Moral ein wesentliches Moment. Sie besteht darin, dass man die Pflicht tut, weil es sich so gehört.
理性とは異なった他のものに支配されている私の非本質的な性向と結びついているような服従は、理性の法則に反する服従である。けれども他面において、服従には自己みずから自主独立してゆく役割がある。というのも、この原理はまさに私の本質に根拠をもっているからである。したがって心情は道徳においては本質的な要素である。人々が義務を果たすのはそれが正しいことだからというところに、心情は立脚している。
Es ist also eine unmoralische Gesinnung, etwas aus Furcht vor der Strafe oder deshalb zu tun, um bei Andern eine gute Meinung von sich zu erhalten. Dies ist ein heterogener, d. i. fremdartiger Beweggrund, denn es ist nicht der Grund der Sache selbst oder man betrachtet alsdann das Recht nicht als etwas, das an und für sich selbst ist, sondern als etwas, das von äußerlichen Bestimmungen abhängig ist.
したがって、何か刑罰への恐れからや、あるいは、自分について他人からよく思ってもらおうとして何かをするといったことは、非道徳的な心情である。これは異様な、いいかえれば、不純な動機である。というのも、それは事柄そのものを根拠とはしないからであり、あるいは、人々はそこでは法を本来的なものとして、そして、それ自体のため存在するものとは考えないからであり、むしろ、外的な状況に左右されるようなものと考えているからである。
Dennoch ist die Betrachtung, ob Strafen oder Belohnungen auf eine Handlung gesetzt sind, wenn gleich die Folgen nicht den Werth der Handlung ausmachen, von Wichtigkeit. Die Folgen einer guten Handlung können oft vieles Üble nach sich ziehen, eine böse Handlung hingegen kann unter ihren Folgen auch gute haben. — Überhaupt aber an die Folgen der Handlung zu denken, ist deswegen wichtig, weil man dadurch nicht bei dem unmittelbaren Gesichtspunkte stehen bleibt, sondern darüber hinausgeht. Durch ihre mehrseitige Betrachtung wird man auch auf die Natur der Handlungen geleitet.(※5 )
それにもかかわらず、ひとつの行為に対してどのような罰則や報償が定められているかを考えることは、たといただちに、その行為の価値をつくりだすものではなくとも、重要なことである。善い行為に結果としてしばしば多くの悪しきことがもたらされることはよくあることである。これとは反対に、悪しき行為に結果として善いことがもたらされることもまたありうる。⎯⎯ しかしそれゆえにこそ、一般的には、行為の結果を考えることは本来的に大切である。というのも、それによって人々は直接的な観点にとどまることなく、むしろ、それを克服してゆくからである。それら多くの多面的な考察を通して、人々はまた行為の本質(についての洞察)に導かれるようになる。
(※1)
前節の§22で、人間の内心、心情は法の対象とはならないことを述べて、「法」の限界が明らかにされたが、法の限界を超える領域にあるものとして、本節§23において「道徳」の意義が論じられる。道徳のモメントは心情である。
(※2)
心情の初めの段階としての「無垢」や「無邪気さ」は何ら道徳的な価値をもたない。いまだ十分な判断能力をもたない子供や未開民族の「無垢」や「無邪気」は、法や道徳の対象とはならない。
(※3)
カトリック信仰からの独立、自主を果たしたルターの信仰の独立、プロテスタントの宗教の成立という歴史的な背景がふまえられている。心情は内的な「確信」や「信念」の場ともなるが、それも自己外部の「権威」にもとづいた「単なる確信」「単なる信念」にすぎないものがある。しかし、この外部の権威に服従することにも、道徳的な意義はある。というのも人間の生まれついた身体の欲望は必ずしも理性的なものではないから、外部の権威に従うことによって、そこで人間は自己の情欲を抑制することを学ぶことになるからである。この点において道徳的な意義はあるが、それは消極的な側面である。
(※4)
生まれつきの、自然な性向や、感覚的、身体的な欲望からくる意志の領域。これらの欲求からくる意志に従うことは、たといそれが内からのものであっても、それもまた「他者」に追従することである。
新約聖書ロマ書第7章15節
「私は自分のしていることが分かっていません。自分の望んでいることを私は行わず、むしろ、私の憎んでいることを私は行っているのです。」
(※5)
心情が道徳においては本質的な契機、要素であるのは、道徳が手段ではなく目的それ自体であるから。道徳はそれ自体が目的であって、道徳はそれが守られること自体にその価値の根拠があるからである。したがって、道徳を手段と考えたり、行為の外的な事情によって、たとえば損得や名声、刑罰の有無にもとづいて行われる行為は、非道徳な行為であるといえる。
しかし、現実においては、善意の行為が必ずしもよい結果を生むとは限らず、またその逆に悪行が善い結果をもたらすということがある。
それゆえに必ずしも心情の純粋さのためだけではなく、行為の結果を洞察することによって、人間は直接的で感覚的な観点を超えて反省することが重要になってくる。
この論理を洞察する「弁証法の論理」を人々が習得しなければならない重要さもここにある。

















![ヘーゲル『哲学入門』 中級 第二段 自意識 第三十一節[自己と他者の自由について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1f/31/0d265e296c949b77fb928a0c586a5f61.jpg)
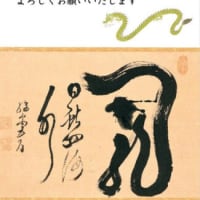










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます