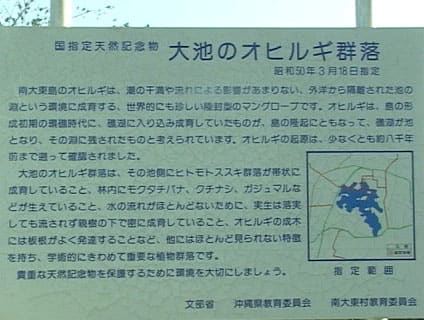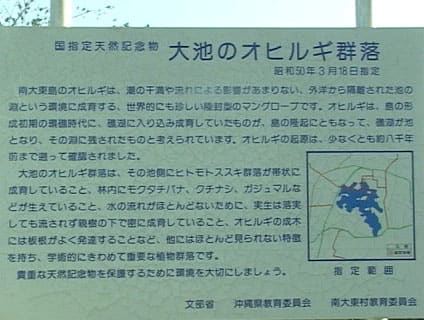今回は、少し古い島旅でありますが、思い出が多くあり、「一番印象に残っている島」の質問では、いつも「
大東諸島」と答えているので、思い出しながら投稿したいと思います。
大東諸島の概要を投稿します。
南大東島 沖縄本島の東方、那覇から海路392kmにある島。北に8kmへだてて北大東島がある。水深4,000mの海底から立ち上がった火山島の頂にサンゴ礁が堆積を続け、数度にわたって隆起した隆起珊瑚の島で、北大東島とともに世界でも十数島しか例のない特異な存在として知られている。周囲の高さは10~20mの絶壁に取り囲まれ、中央部は盆地になっており、池沼が点在する。約5,000万年前の誕生以来、大陸や日本列島と一度もつながったことがなく、さまざまな固有種が生息している。古来から大東諸島は「うふあがり島」(「大きい東の島」の意)として知られていた。島名はそのまま漢字にあてたものといわれている。17世紀半ばには欧州の地図にも登場するが、位置や島数は不正確であった。19世紀には英国海軍水路誌や欧州の地図に北・南大東島が「ボロジノ諸島」として記載されている。「ポロジノ」の名は、当時北・南大東島を発見したロシアの海軍左官ボナフディンの乗る艦名「ボロジノ」にちなむといわれている。定住は明治33年(1900)、八丈島出身の玉置右衛門が有志22人とともに開拓に着手したことに始まる。以来、サトウキビ単作栽培の島として発展し、昭和58年までサトウキビ運搬のための沖縄県唯一の軌道(総延長約30km)もあった。現在も島の面積の約60%を占める耕地面積のほとんどがサトウキビ畑になっており、また、関東・八丈島の文化と沖縄の文化が入り交じり、独特の文化環境を育んでいる。平成元年に起工したわが国でも最大規模の掘込み漁港・南大東漁港は、同23年に完成の予定だが、すでに同12年に一部供用開始された。近年、「教育立村」宣言がなされ、特異な自然環境を生かした「島まるごとミュージアム構想」が推進されている。
北大東島 沖縄本島の東方380km、隆起サンゴ礁でできた沖縄県最東端の島。まわりをすべて断崖に囲まれ、島の中央はラグーン(礁湖)の跡で盆地になっている。明治36年(1903)、南大東島と同じく八丈島出身の玉置半右衛門の会社が開発に着手、会社独占支配の下で燐鉱の採掘とサトウキビの単一栽培が進められた。燐鉱は大正8年から昭和25年まで本格的に採掘され、肥料や火薬の原料となる燐酸をはじめ、アルミの原料である高品位のアルミナ鉄など計80万トンを産出、最盛期には人口も4,000人を数えた。現在でも貯鉱場や軌道跡、積出埠頭などがかつての賑わいを今に伝えている。また、「砂糖の島」とも呼ばれるくらい一面にサトウキビ畑が広がり、沖縄県の機械化農業の先進地となっている。古来、大東諸島は「うふあがり島」(うふ=大きい、あがり=東の意)と呼ばれ、沖縄本島では海上はるかな神の国として信仰する人もいたという。
出典:(財)日本離島センター発行の「
日本の島ガイド SHIMADAS シマダス」から