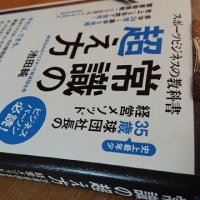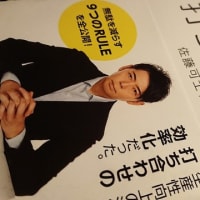この本は2001年の出版なので今の人事・賃金制度と少しずれているかもしれない。
確かコンピテンシーという言葉が日本で流行り始めた頃だったと思う。
編集した日本賃金研究センターというのは座長が楠田丘氏となっている。
楠田氏と言えば、80年代、90年代の日本の人事制度に影響を与えた人だ。それで日本の職能資格制度と成果主義にコンピテンシー評価を混合させた人事制度を提案する形になっているようだ。
人事考課に基づく職能資格制度は、能力考課と情意考課の上に成り立っている。人材の能力を期待値に比して評価するものだ。
それに比べてコンピテンシーは優秀な人材の行動特性を抽出して、それと比べることが基本だ。
潜在能力とアウトプットという違うものを合わせようとしているところに少し無理があるようにも思える。
経済成長、ポスト不足などの時代では職能資格制度がある程度機能した。しかし低成長、実力主義による報酬の分配が重視される時代には機能しなくなってきている。
コンピテンシーの考え方が出てきたのも、結果重視の行動をとることがホワイトカラーに求められる時代になったからだ。
それで楠田氏はこれまでの日本の制度にコンピテンシーを混ぜるハイブリッドな考え方になったと思える。果たしてこの考え方が日本に合っているのだろうか。
職能資格の等級をジュニア、シニア、マネジメントに分け、さらにいくつかに分ける方法は日本の企業では一般的になっているのかもしれない。
コンピテンシーモデルはコンピテンシー評価、職務基準は達成度評価、職群基準はアセスメントと評価をいくつもの基準で行うのはそれだけ労力がかかるということだ。
すべて絶対評価で行うことが原則だ。
人が人を評価するのに客観性は相対的なものになる。しかしより客観性を高めるために、職能資格の基準を細かく決めたり、いくつもの基準で面接調査したりする。
こんな風に細かく記述するのがよいのか、それとも何人かの評価者が集まって、それぞれの基準で合意ポイントに持って行くのがより客観性を求めることになるのか判断が難しいところである。
それぞれの企業の戦略に沿って、その組織をどういう組織にしたいのか。そのために求める基準は何か。その目的に沿った人事制度と評価制度は何かを考えるのが大事なのだろう。加点主義かよいのか、減点主義がよいのか、年齢や勤続年数を重視するのか、成果を重視するのか、それぞれの企業の条件によってすべて異なってくると思う。
楠田丘氏の考えたシステムなどをいかに自分の企業に適用するのかを考えるセミナーなどを見かけるが、ちょっと逆立ちした発想だと思う。
最近の傾向としては評価者訓練を重視するところや360度評価を取り入れるところも増えている。
人事制度を設計するとき、人が人を評価することの難しさ、その企業で人は何にモチベートされて働くのか、という根本的な考え方の擦り合わせも必要なのではないだろうか。
確かコンピテンシーという言葉が日本で流行り始めた頃だったと思う。
編集した日本賃金研究センターというのは座長が楠田丘氏となっている。
楠田氏と言えば、80年代、90年代の日本の人事制度に影響を与えた人だ。それで日本の職能資格制度と成果主義にコンピテンシー評価を混合させた人事制度を提案する形になっているようだ。
人事考課に基づく職能資格制度は、能力考課と情意考課の上に成り立っている。人材の能力を期待値に比して評価するものだ。
それに比べてコンピテンシーは優秀な人材の行動特性を抽出して、それと比べることが基本だ。
潜在能力とアウトプットという違うものを合わせようとしているところに少し無理があるようにも思える。
経済成長、ポスト不足などの時代では職能資格制度がある程度機能した。しかし低成長、実力主義による報酬の分配が重視される時代には機能しなくなってきている。
コンピテンシーの考え方が出てきたのも、結果重視の行動をとることがホワイトカラーに求められる時代になったからだ。
それで楠田氏はこれまでの日本の制度にコンピテンシーを混ぜるハイブリッドな考え方になったと思える。果たしてこの考え方が日本に合っているのだろうか。
職能資格の等級をジュニア、シニア、マネジメントに分け、さらにいくつかに分ける方法は日本の企業では一般的になっているのかもしれない。
コンピテンシーモデルはコンピテンシー評価、職務基準は達成度評価、職群基準はアセスメントと評価をいくつもの基準で行うのはそれだけ労力がかかるということだ。
すべて絶対評価で行うことが原則だ。
人が人を評価するのに客観性は相対的なものになる。しかしより客観性を高めるために、職能資格の基準を細かく決めたり、いくつもの基準で面接調査したりする。
こんな風に細かく記述するのがよいのか、それとも何人かの評価者が集まって、それぞれの基準で合意ポイントに持って行くのがより客観性を求めることになるのか判断が難しいところである。
それぞれの企業の戦略に沿って、その組織をどういう組織にしたいのか。そのために求める基準は何か。その目的に沿った人事制度と評価制度は何かを考えるのが大事なのだろう。加点主義かよいのか、減点主義がよいのか、年齢や勤続年数を重視するのか、成果を重視するのか、それぞれの企業の条件によってすべて異なってくると思う。
楠田丘氏の考えたシステムなどをいかに自分の企業に適用するのかを考えるセミナーなどを見かけるが、ちょっと逆立ちした発想だと思う。
最近の傾向としては評価者訓練を重視するところや360度評価を取り入れるところも増えている。
人事制度を設計するとき、人が人を評価することの難しさ、その企業で人は何にモチベートされて働くのか、という根本的な考え方の擦り合わせも必要なのではないだろうか。