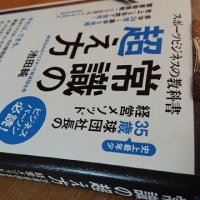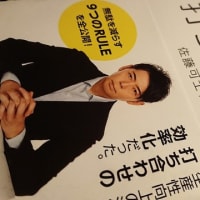インストラクショナル・デザイナーと呼ばれる専門職がある。教育の効果・効率・魅力を高めるシステム的方法論の専門家だ。アメリカやカナダ、韓国、シンガポールなどで活躍し、eラーニングの量的普及と質的向上に寄与している。英国では公的な資格になっている。その専門家を日本で、それも国立大学で育成しようとしているのが熊本大学大学院だ。この本はそのスタッフたちがインストラクショナル・デザイナーとはどういうものか。eラーニング支援者をめぐる欧米やアジアの動向、企業の社内教育におけるeラーニングなどを解説し、熊本大学はインストラクショナル・デザイナーをどうやって育成しようとしているのかを紹介している。
通学制の大学院なのに、フルオンラインでカリキュラムを編成しているのも画期的だ。カリキュラムはID(インストラクショナルデザイン)、IT(情報通信技術)、IP(知的財産権)、IM(情報マネジメント)の4つで構成されている。
この本の中ではIMの分野で江川准教授の論文がとくに興味深い。
・・・大学という組織はフラットなネットワーク組織組織であり、とくに国立大学は部局(学部、研究科等)が大学事務局機能に連邦国家のようにつながっている特徴がある。この組織は権限が機能別に分散され分担される一方、「原始民主主義」とも呼べる権限と責任を全員が平等に保持した形態か、あるいは学長・理事長など一部のマネジメントにだけ集中したオーナー集中型の形態になりやすい。そのため、一般の企業のようなシステマティックな意思決定ではなく、全員合意もしくはトップによる独断という意思決定が行われる。大学における組織マネジメントの仕組みは教育サービスを提供するという点で効率的に機能していないのが現状である。部局間平等主義や前年実績主義が根強く、実質的な意思決定がなされていない。企業型マネジメントへの全面的意向でも文部科学省による競争原理の導入でもない「第三の道」を模索していく時期だろう。・・・
教育におけるオペレーションマネジメントについても述べている。
・・・教育におけるオペレーションマネジメントはサービスの戦略構築やマーケティング立案にたいしてその実行をマネジメントすることが対象である。効果的なオペレーションを実現することで、サービスとしての教育の付加価値やコスト・パフォーマンスはアップし改善され続けていく。特にQCD(Qualitu;Cost;Delivery)と呼ばれるプロセスが重要であり、カリキュラムの品質管理、労力やコストの効率化と適切な配分、あるいはサービス提供のス
ピードやタイミングの最適化といったことが検討される。このようなオペレーション・マネジメントを実現するためには教育現場の徹底した「見える化」が不可欠。指導計画や学習者の理解度調査、アンケートなどを図やグラフ化するだけではない。それらから導かれる問題点や情報の共有化を行い、組織としての能力向上にならないといけない。今後はどうやってそれを実現するかが課題である。・・・
こういう画期的な教育プログラムが国立大学で実施できたのは、アメリカで教育を受けた日本のIDの第一人者である鈴木克明教授の存在とこの本の著者である大森不二雄教授の政治力が大きな要因だろう。
大森氏はもと文部官僚だが、ゆとり教育が推進されているときにそれを批判する本を出版して話題になった経歴の持ち主である。こういう人を受け入れるパワーが国立大学のなかにもあるのだと感心した。
通学制の大学院なのに、フルオンラインでカリキュラムを編成しているのも画期的だ。カリキュラムはID(インストラクショナルデザイン)、IT(情報通信技術)、IP(知的財産権)、IM(情報マネジメント)の4つで構成されている。
この本の中ではIMの分野で江川准教授の論文がとくに興味深い。
・・・大学という組織はフラットなネットワーク組織組織であり、とくに国立大学は部局(学部、研究科等)が大学事務局機能に連邦国家のようにつながっている特徴がある。この組織は権限が機能別に分散され分担される一方、「原始民主主義」とも呼べる権限と責任を全員が平等に保持した形態か、あるいは学長・理事長など一部のマネジメントにだけ集中したオーナー集中型の形態になりやすい。そのため、一般の企業のようなシステマティックな意思決定ではなく、全員合意もしくはトップによる独断という意思決定が行われる。大学における組織マネジメントの仕組みは教育サービスを提供するという点で効率的に機能していないのが現状である。部局間平等主義や前年実績主義が根強く、実質的な意思決定がなされていない。企業型マネジメントへの全面的意向でも文部科学省による競争原理の導入でもない「第三の道」を模索していく時期だろう。・・・
教育におけるオペレーションマネジメントについても述べている。
・・・教育におけるオペレーションマネジメントはサービスの戦略構築やマーケティング立案にたいしてその実行をマネジメントすることが対象である。効果的なオペレーションを実現することで、サービスとしての教育の付加価値やコスト・パフォーマンスはアップし改善され続けていく。特にQCD(Qualitu;Cost;Delivery)と呼ばれるプロセスが重要であり、カリキュラムの品質管理、労力やコストの効率化と適切な配分、あるいはサービス提供のス
ピードやタイミングの最適化といったことが検討される。このようなオペレーション・マネジメントを実現するためには教育現場の徹底した「見える化」が不可欠。指導計画や学習者の理解度調査、アンケートなどを図やグラフ化するだけではない。それらから導かれる問題点や情報の共有化を行い、組織としての能力向上にならないといけない。今後はどうやってそれを実現するかが課題である。・・・
こういう画期的な教育プログラムが国立大学で実施できたのは、アメリカで教育を受けた日本のIDの第一人者である鈴木克明教授の存在とこの本の著者である大森不二雄教授の政治力が大きな要因だろう。
大森氏はもと文部官僚だが、ゆとり教育が推進されているときにそれを批判する本を出版して話題になった経歴の持ち主である。こういう人を受け入れるパワーが国立大学のなかにもあるのだと感心した。