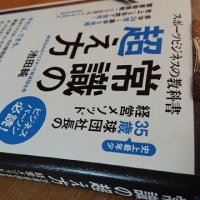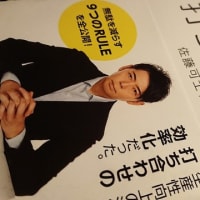これは現在のアメリカを中心とするビジネススクールへの批判の書である。批判の立脚点は、企業のマネジメントにはアート(直感)、クラフト(実務経験)、サイエンス(分析)のバランスが必要だが、ビジネススクールはサイエンスを偏重しているというミンツバーグの主張である。ビジネススクールはマネジャーの養成をする所なのに実際は計算に強く、落ち着きがなく、経営の特定分野に詳しい傲慢な専門家を育てているだけだとも言っている。
ミンツバーグはハーバードビジネススクールなどの主な教育方法であるケースメソッドについても実際の企業経営を経験したわけでもないのに経営を判断することを強要していると批判する。HPのフィオリーナのようなMBA取得者が目先の利益だけを重視した会社運営する方法も批判する。またベトナム戦争を泥沼化させたマクナマラ元国防相や政府機関で政府をビジネス化させている者などがMBA取得者であることから、MBAはビジネスにとどまらない範囲で社会に害を与えているという。
たしかにアーツ(直感)なき経営者に本当のビジョンは描けないだろうし、クラフト(実務経験)なき経営者にその業界の本質はわからない気がする。また、ビジネススクールでのケースメソッドの強引な討議方法や選抜制の高いMBAのエリート意識が傲慢さを生むというのもわかる。
後半でミンツバーグは自らが主宰しているIMPM(国際マネジメント実務修士課程)を推奨している。学位もMBAでなくMPM(マネジメント実務修士課程)と呼ぶ。MPMはMBAのアンチテーゼ的な要素で成り立っている。入学資格は現役のマネジャー。学習場所はカナダ、インド、フランス、韓国、日本など。グローバルでなくマルチカルチュラル的な国際体験と企業体験を重視する。参加者同士の実務経験年数や内容を重視し、教育内容では理論とケースのバランスを考え、マネジメントを教育の中心に置くことになる。
しかし、問題もある。学費が1000万円を越えることだ。これでは企業派遣でないと実際には参加できない。学費によって参加する層をぐっと狭めることになるだろう。修了後の離職率が低いのが自慢のようだが、逆に考えるとIMPMを修了してもエンプロイアビリティが低いとも言える。今のビジネススクールにはスクールの運営自体も問題があるだろうが、多くのビジネススクール卒業生が就職するコンサルティング会社や投資銀行などの社会的要請に対応していることも要因ではないのか。それを考えるといまのビジネススクールの仕組みがすぐには変わらないような気もする。
日本ではビジネススクールも助産師養成も一括して専門職大学院としている。教授陣のうち3分の1はその分野で5年以上の実務家でなければいけないとかの基準がある。その割に研究論文の本数とか教員審査は厳しいようだ。これらの基準の根拠はよくわからない。最近では学部なしの専門職大学院はよくないという議論が文部科学省の委員会で出ているようだ。日本らしい形式的な議論だと思う。大学が連邦や州の認可制でないアメリカでビジネススクールについて、ミンツバーグの主張のような本質的な議論がされていることはとても建設的な気がする。日本はビジネススクールの設置もその後の検討も30年以上遅れているようだ。
しかしミンツバーグは日本の企業でのマネジャー養成システムを高く評価している。これはどうしてなのだろうか。その進んだ日本がアメリカのビジネススクールを真似ようとしているという奇妙な現象をどう理解すればよいのか。
ミンツバーグはハーバードビジネススクールなどの主な教育方法であるケースメソッドについても実際の企業経営を経験したわけでもないのに経営を判断することを強要していると批判する。HPのフィオリーナのようなMBA取得者が目先の利益だけを重視した会社運営する方法も批判する。またベトナム戦争を泥沼化させたマクナマラ元国防相や政府機関で政府をビジネス化させている者などがMBA取得者であることから、MBAはビジネスにとどまらない範囲で社会に害を与えているという。
たしかにアーツ(直感)なき経営者に本当のビジョンは描けないだろうし、クラフト(実務経験)なき経営者にその業界の本質はわからない気がする。また、ビジネススクールでのケースメソッドの強引な討議方法や選抜制の高いMBAのエリート意識が傲慢さを生むというのもわかる。
後半でミンツバーグは自らが主宰しているIMPM(国際マネジメント実務修士課程)を推奨している。学位もMBAでなくMPM(マネジメント実務修士課程)と呼ぶ。MPMはMBAのアンチテーゼ的な要素で成り立っている。入学資格は現役のマネジャー。学習場所はカナダ、インド、フランス、韓国、日本など。グローバルでなくマルチカルチュラル的な国際体験と企業体験を重視する。参加者同士の実務経験年数や内容を重視し、教育内容では理論とケースのバランスを考え、マネジメントを教育の中心に置くことになる。
しかし、問題もある。学費が1000万円を越えることだ。これでは企業派遣でないと実際には参加できない。学費によって参加する層をぐっと狭めることになるだろう。修了後の離職率が低いのが自慢のようだが、逆に考えるとIMPMを修了してもエンプロイアビリティが低いとも言える。今のビジネススクールにはスクールの運営自体も問題があるだろうが、多くのビジネススクール卒業生が就職するコンサルティング会社や投資銀行などの社会的要請に対応していることも要因ではないのか。それを考えるといまのビジネススクールの仕組みがすぐには変わらないような気もする。
日本ではビジネススクールも助産師養成も一括して専門職大学院としている。教授陣のうち3分の1はその分野で5年以上の実務家でなければいけないとかの基準がある。その割に研究論文の本数とか教員審査は厳しいようだ。これらの基準の根拠はよくわからない。最近では学部なしの専門職大学院はよくないという議論が文部科学省の委員会で出ているようだ。日本らしい形式的な議論だと思う。大学が連邦や州の認可制でないアメリカでビジネススクールについて、ミンツバーグの主張のような本質的な議論がされていることはとても建設的な気がする。日本はビジネススクールの設置もその後の検討も30年以上遅れているようだ。
しかしミンツバーグは日本の企業でのマネジャー養成システムを高く評価している。これはどうしてなのだろうか。その進んだ日本がアメリカのビジネススクールを真似ようとしているという奇妙な現象をどう理解すればよいのか。