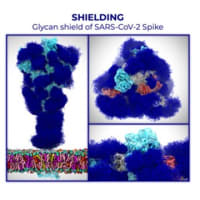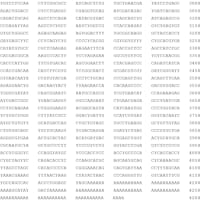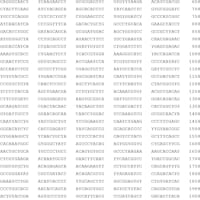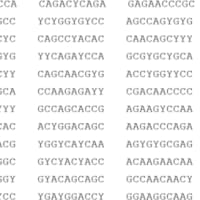先週、第四世代原子炉(Generation IV)の会議が開催された。その会議の席上、中国で液体核燃料を用いた溶融塩炉の開発を進める上海応用物理研究所のTMSR研究センター(Thorium Molten Salt Reactor)の研究者が、2020年までに本物の液体核燃料による溶融塩炉での臨界を目指すと発言し出席者に衝撃を与えた。これは中国共産党と政府の至上命令であり、日本留学組を含めた彼らにとっては、研究者人生を掛けての取組みとなる。中国は、現在、2MWthの溶融塩試験炉を今年6月中に稼働させ、10MWthの実証炉を経て、1Gweの商業炉を開発する計画であるが、今後開発スピードを速めることとなる。この動きは、中国の原子力政策が大きく変更されたことを意味しており、ロシアや米国から導入した個体核燃料による原子炉から、溶融塩炉や高温ガス炉など固有安全性を有する第四世代炉に大きくシフトすることとなる。特に、中国国内では水問題が深刻で、福島原発事故後は、沿海部での原子炉建設しか認めてこなかった経緯がある。溶融塩炉は臨界に水は必要とせず、発電の為の水以外は、基本必要がない。重要なのは今後の経済発展は内陸部であり、やはり安定した電力が発展には欠かせない。中国政府の電気自動車への取組みの背景には、溶融塩炉など小型原子炉を内陸部に分散配置し、送電網を最小限投資で、配電網を中心とした分散型電力システムを指向すると考える向きもある。モビリティの電動化の最大の課題は、その電力をどうするかであり、中国は原子力に解を見つけたと言うことが言えるかもしれない。今後、溶融塩炉は、ウィグル自治区で開発が進められる。
中国が溶融塩炉に注目するのは、大規模な原発事故に対応できなかった日本の状況を研究し、中国自身も日本同様に原子炉事故には、到底対処できないだろうとの冷徹な判断がある。従来の軽水炉は、一次系が高圧で電源喪失し除熱が出来なくなると、たちどころに炉心が溶融し、また水素ガスを発生させ爆発するリスクを回避するのは困難だ。この認識を基に、中国は、1気圧、即ち常圧で動く溶融塩炉に注目し、燃料は最初から溶融状態にあり、水が無いので水素ガス発生無い。しかも事故時には炉底部のドレインタンクに燃料塩を落下させ、自然にガラス化し、再臨界もないと言う特性を評価。
日本国内では、激しい原発アレルギーがあるが、世界は状況が異なる。即ちエネルギーセキュリティと地球環境の両方を担保する小型原子炉の開発が進められており、原子力のポテンシャルが再認識されている。原子力のRebrandである。特に溶融塩炉は、中国を始め欧米各国のベンチャーでも開発が行なわれており、米Flibe Energy、Transatomic Power、ThorCon、カナダTerrestrial Energy、英Moltex Energy、デンマークSeaborg Technologies, Copenhagen Atomicsなどがある。Terrestrial Energy社の創業者は、日本人の森さんで、彼女は現在、神戸在住である。
日本でも溶融塩炉に着目するようになっており、自由民主党の資源・エネルギー戦略調査会(会長:山本拓議員)の新型エネルギー検討委員会(委員長:原田義昭議員)において溶融塩炉の勉強会が開催され、元東京大学総長、元文部科学大臣の有馬先生などが熱弁を奮っている。また、Terrestrial Energy社のCTOが来日し、使用済み核燃料処理にも資する統合型溶融塩炉IMSR(Integral Molten Salt Reactor)に就いて説明を行った。減速材には黒鉛を使用し、最初のフェーズでは、燃料に低濃縮ウランを含有したフッ化物塩を入れ、熱交換器は炉容器内あると言う溶融塩熱中性子炉で、来年2019年後半には設計認証の審査申請を行う計画と言う。
自民党の調査会に於いては、使用済み核燃料の問題を解決しうる技術として溶融塩炉に注目しており、産業利用としては、水素製造などを行い水素社会に向けた今後20兆円規模の水素エネルギー投資にも関係する動きである。
現在、第五次エネルギー基本計画策定中であるが、2020年以降に策定される第六次エネルギー基本計画が、その後30年の日本のエネルギー政策を決める重要なもので、国内勢は、一斉に溶融塩炉や分散電力技術(デジタルグリッド)、Peer to Peerによる電力取引、ブロックチェーンなど分散台帳システム、それと水素社会に向けた大規模投資などの案件化に走り始めている。