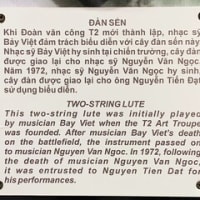私は正直言って、チャイコフスキーや「5人組」は好きだが、ハチャトゥリアン、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチ、プロコフィエフなど20世紀ソ連作曲家の作品を良いと思ったことは殆ど
無い。例外的に、プロコフィエフのヴァイオリンソナタは何度も練習したので不思議な魅力は感じたくらい。 だが、たまたま、ひと世代前のアレクサンドル・グラズノフの作品を演奏するにあたり
調べているうちに、彼が育てたというショスタコーヴィチが師グラズノフをどうみていたのか? それを知りたくなり本書を開いた。
英文タイトルは<<Testimony;The Memories of Dmitri Shostakovich>であるが、歴史の証言であり且つ、個人の回想という体裁を与えた意図が、既に告発書の狙いを匂わせている。
本書が1979年アメリカで発刊されてすぐ(証言の真贋論争)が始まり、当時のソ連では様々な対抗措置が出された。「ショスタコーヴィチ未亡人の証言」と称した偽文書キャンペーンも其のひとつ。
なんと、ソ連崩壊後まで(真贋論争)が続いたのは驚きだ。 著者ソロモン・ヴォルコフが本人の承諾を得たという原稿の信憑性及びショスタコーヴィチの自筆サインへの真偽疑惑に加え、ヴォルコフ
自身についての疑問も消えていない。分量の多さ、口述記録の編集にしては構成が整頓され過ぎている事など、穿り返せばキリはない。 だが、もう今となっては真偽を確かめるすべは無い。
かといって、全くのフィクション或は小説風伝記というには余りにも生々しい。著者の脚色が入ってるにせよ、ショスタコーヴィチが述べたという言葉が炙り出す内容自体は恐らく虚偽じゃなかろう。
ヴォルコフ(1944-)はレーニングラード音楽院の音楽史学科卒業。病床にあったショスタコーヴィチの言葉を集めたのち、死去の翌1976年、アメリカへ原稿を携え亡命した。
「自分が死んだあと、国外で刊行してくれ」との遺言にヴォルコフは従ったわけだ。本書はNYで発売された英語版ではなく、原典のロシア語版から邦訳したと水野氏は断っている。
それらの経緯を全て知ったうえで、私なりの読後感を述べる。
発表当時、欧米では極めてセンセーショナルな衝撃でうけとめられたという。何故そこまで本書は問題視されたのか? 日本ではどういう受け止め方をしたのか? (当時の私は関心がなかった)。
最たる衝撃は<スターリンが国民、そして音楽家にどう向き合ったのか>を語るショスタコーヴィチの言葉から、戦前は見えないままだが戦後は敵対することになった独裁者の姿が、初めて赤裸々に
伝わったからであろう。そこに同じ時間を生きたヴォルコフの言葉が混じっていたとしても、専制的リーダーが支配する独裁国家の姿を伝えるうえで何ら問題は無い。
因みにこの1980年頃、同じ独裁国である中国の内情、或は毛沢東の実像は(提灯記事は別にして)知られておらず、唯一スターリンの描写が共産国リーダーの典型となった。
★ 本書の構成は以下の8章建てである。各章の標題が果たしてどこまでショスタコーヴィチ自身の想いを反映したか? それは大いに疑問だが、本書全体が語らんとする方向に反してはいまい。
1.真実の音楽を求めて 2.わが人生と芸術の学校 3.ロシア革命の光と影 4.非難と呪詛と恐怖のなかで 5.私の交響曲は墓碑である 6.張り巡らされた蜘蛛の巣
7.ロシア音楽の伝統を受け継いで 8.過去と未来の狭間
ショスタコーヴィチの作品、ロシア&ソ連の音楽史に通じている方はいざ知らず、スターリン専制下及び戦後に彼が味わった苦境を知らねば、本書が訴える全容は掴みにくいだろう。
さりとて、逐一それを述べる訳にはゆかないので、いつもながら、各章ごとに私が感じた事を紡ぎながら感じて戴くしかない。 < つづく >
無い。例外的に、プロコフィエフのヴァイオリンソナタは何度も練習したので不思議な魅力は感じたくらい。 だが、たまたま、ひと世代前のアレクサンドル・グラズノフの作品を演奏するにあたり
調べているうちに、彼が育てたというショスタコーヴィチが師グラズノフをどうみていたのか? それを知りたくなり本書を開いた。
英文タイトルは<<Testimony;The Memories of Dmitri Shostakovich>であるが、歴史の証言であり且つ、個人の回想という体裁を与えた意図が、既に告発書の狙いを匂わせている。
本書が1979年アメリカで発刊されてすぐ(証言の真贋論争)が始まり、当時のソ連では様々な対抗措置が出された。「ショスタコーヴィチ未亡人の証言」と称した偽文書キャンペーンも其のひとつ。
なんと、ソ連崩壊後まで(真贋論争)が続いたのは驚きだ。 著者ソロモン・ヴォルコフが本人の承諾を得たという原稿の信憑性及びショスタコーヴィチの自筆サインへの真偽疑惑に加え、ヴォルコフ
自身についての疑問も消えていない。分量の多さ、口述記録の編集にしては構成が整頓され過ぎている事など、穿り返せばキリはない。 だが、もう今となっては真偽を確かめるすべは無い。
かといって、全くのフィクション或は小説風伝記というには余りにも生々しい。著者の脚色が入ってるにせよ、ショスタコーヴィチが述べたという言葉が炙り出す内容自体は恐らく虚偽じゃなかろう。
ヴォルコフ(1944-)はレーニングラード音楽院の音楽史学科卒業。病床にあったショスタコーヴィチの言葉を集めたのち、死去の翌1976年、アメリカへ原稿を携え亡命した。
「自分が死んだあと、国外で刊行してくれ」との遺言にヴォルコフは従ったわけだ。本書はNYで発売された英語版ではなく、原典のロシア語版から邦訳したと水野氏は断っている。
それらの経緯を全て知ったうえで、私なりの読後感を述べる。
発表当時、欧米では極めてセンセーショナルな衝撃でうけとめられたという。何故そこまで本書は問題視されたのか? 日本ではどういう受け止め方をしたのか? (当時の私は関心がなかった)。
最たる衝撃は<スターリンが国民、そして音楽家にどう向き合ったのか>を語るショスタコーヴィチの言葉から、戦前は見えないままだが戦後は敵対することになった独裁者の姿が、初めて赤裸々に
伝わったからであろう。そこに同じ時間を生きたヴォルコフの言葉が混じっていたとしても、専制的リーダーが支配する独裁国家の姿を伝えるうえで何ら問題は無い。
因みにこの1980年頃、同じ独裁国である中国の内情、或は毛沢東の実像は(提灯記事は別にして)知られておらず、唯一スターリンの描写が共産国リーダーの典型となった。
★ 本書の構成は以下の8章建てである。各章の標題が果たしてどこまでショスタコーヴィチ自身の想いを反映したか? それは大いに疑問だが、本書全体が語らんとする方向に反してはいまい。
1.真実の音楽を求めて 2.わが人生と芸術の学校 3.ロシア革命の光と影 4.非難と呪詛と恐怖のなかで 5.私の交響曲は墓碑である 6.張り巡らされた蜘蛛の巣
7.ロシア音楽の伝統を受け継いで 8.過去と未来の狭間
ショスタコーヴィチの作品、ロシア&ソ連の音楽史に通じている方はいざ知らず、スターリン専制下及び戦後に彼が味わった苦境を知らねば、本書が訴える全容は掴みにくいだろう。
さりとて、逐一それを述べる訳にはゆかないので、いつもながら、各章ごとに私が感じた事を紡ぎながら感じて戴くしかない。 < つづく >