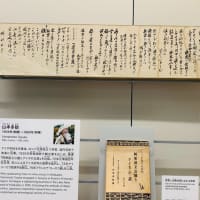検察庁法解釈変更 菅官房長官「周知必要なかった」
https://mainichi.jp/senkyo/articles/20200519/k00/00m/010/103000c?cx_fm=mailyu&cx_ml=article&cx_mdate=20200519
<菅氏は法解釈変更の周知の必要性について「国民生活への影響を踏まえ、必要に応じて周知が行われることがあるが、
一概には答えられない」と説明した上で、今回の検察庁法などの解釈変更については「周知の必要はなかった」と述べた。>
皆さん、この説明を読み・・「え? 何を言ってるの、此の人は?」と驚いたのは私だけだろうか? 勝手に変更したうえ、周知の必要もないだって?
≪そもそも法律の文章/語句は誰が呼んでも理解が異ならないよう配慮を尽くし吟味した作文であらねばならない。是は、言語/政治体制/民族文化に関係なく共通した法治国家なら自明の理だ≫と私は信じてきたからだ。
ところが日本では、今回の公務員定年に関する検察官処遇に限らず、昔から同種の(読み替え)が平然と為政者により行われている。 それが官僚作文だ。
大きなテーマでは「憲法と集団的自衛権行使容認」に関する歴代政権の解釈変更がある。
では、どうして日本ではこのような<解釈変更>自体が大手を振ってまかり通るのか? この疑問への答えは簡単。 インド・ヨーロッパ語族にくらべ厳密な論理構成には不向きな日本語の特性を悪用し、語義追求を最初からかわす意図で法令条文が作成されているからに他ならない! ← これを【融通無碍】と日本人は尊ぶ。
例えば「~等」という時の「等」。これは後から想定してなかった事物が出現しても含めるか含めないかの裁量幅を担保する為だ。 公務員の方ならご存知の筈。
こういう曖昧さをフレキシブルに使うことに慣れているのは官僚だけではなくビジネスマンにも多い。ビジネスが日本国内だけで完結していた時代は是でも何とかなったが、外国人と契約交渉にさしかった途端、お人好しにも外国人にも通じる筈と使う【融通無碍】は、曖昧さを逆手に取られるネタを外国人に与えてしまい、
不利な結果をもたらす。 或は、定義を厳格に突き詰めなかった損を負わされる始末となる。 ← 日本に居る官僚には夢にも想像できまい。
海外生産を親会社・取引先に求められ、仕方なくおっかなびっくりで出た中小企業は殆んどが此の失敗を侵し、痛い目に遭っている。
私は現役のコンサルタント時代に嫌と言うほど此の日本語弊害を目撃してきた。 美しい日本語も、文藝以外の世界では、実に哀しく脆い言語なのである。
だが、日本語の曖昧さで被る商売上の損は、まだ国家の進路を官僚作文の悪用で誤る愚かさに比べたら遥かにマシなのだ。
国民は、毎日使う日本語が秘める曖昧さの弊害を意識し(文藝以外では)言葉の定義をしつこく追い求める習慣を身に着けよう!
https://mainichi.jp/senkyo/articles/20200519/k00/00m/010/103000c?cx_fm=mailyu&cx_ml=article&cx_mdate=20200519
<菅氏は法解釈変更の周知の必要性について「国民生活への影響を踏まえ、必要に応じて周知が行われることがあるが、
一概には答えられない」と説明した上で、今回の検察庁法などの解釈変更については「周知の必要はなかった」と述べた。>
皆さん、この説明を読み・・「え? 何を言ってるの、此の人は?」と驚いたのは私だけだろうか? 勝手に変更したうえ、周知の必要もないだって?
≪そもそも法律の文章/語句は誰が呼んでも理解が異ならないよう配慮を尽くし吟味した作文であらねばならない。是は、言語/政治体制/民族文化に関係なく共通した法治国家なら自明の理だ≫と私は信じてきたからだ。
ところが日本では、今回の公務員定年に関する検察官処遇に限らず、昔から同種の(読み替え)が平然と為政者により行われている。 それが官僚作文だ。
大きなテーマでは「憲法と集団的自衛権行使容認」に関する歴代政権の解釈変更がある。
では、どうして日本ではこのような<解釈変更>自体が大手を振ってまかり通るのか? この疑問への答えは簡単。 インド・ヨーロッパ語族にくらべ厳密な論理構成には不向きな日本語の特性を悪用し、語義追求を最初からかわす意図で法令条文が作成されているからに他ならない! ← これを【融通無碍】と日本人は尊ぶ。
例えば「~等」という時の「等」。これは後から想定してなかった事物が出現しても含めるか含めないかの裁量幅を担保する為だ。 公務員の方ならご存知の筈。
こういう曖昧さをフレキシブルに使うことに慣れているのは官僚だけではなくビジネスマンにも多い。ビジネスが日本国内だけで完結していた時代は是でも何とかなったが、外国人と契約交渉にさしかった途端、お人好しにも外国人にも通じる筈と使う【融通無碍】は、曖昧さを逆手に取られるネタを外国人に与えてしまい、
不利な結果をもたらす。 或は、定義を厳格に突き詰めなかった損を負わされる始末となる。 ← 日本に居る官僚には夢にも想像できまい。
海外生産を親会社・取引先に求められ、仕方なくおっかなびっくりで出た中小企業は殆んどが此の失敗を侵し、痛い目に遭っている。
私は現役のコンサルタント時代に嫌と言うほど此の日本語弊害を目撃してきた。 美しい日本語も、文藝以外の世界では、実に哀しく脆い言語なのである。
だが、日本語の曖昧さで被る商売上の損は、まだ国家の進路を官僚作文の悪用で誤る愚かさに比べたら遥かにマシなのだ。
国民は、毎日使う日本語が秘める曖昧さの弊害を意識し(文藝以外では)言葉の定義をしつこく追い求める習慣を身に着けよう!