2019.03.20 『グリーンブック』鑑賞@TOHOシネマズ日本橋
これは見たいと思ってた! 試写会応募したけどハズレ😢 アカデミー賞作品賞受賞したことだし、ちょっと遅れを取ったけれど見に行ってきた~

 ネタバレありです! 結末にも触れています!
ネタバレありです! 結末にも触れています!
「高級クラブの用心棒トニー・リップは、クラブの改装工事で2ヶ月間失業してしまう。そんな中、紹介された仕事は黒人ピアニストのマネージャー兼運転手として、8週間のツアーに同行するというもの。2人は黒人のための宿泊ガイドグリーンブック片手に人種差別の厳しい南部を旅するが・・・」という感じの話でこれは実話ベース。これはとっても良かった! 1960年代が舞台なので今より全然人種差別が厳しい時代。もちろん人種差別もテーマではあるのだけど、おじさん2人のバディものとして描いているため、時に笑いながら見れて、そしてじんわりと利いてくる。これは素晴らしかった。
ファレリー兄弟の兄ピーター・ファレリー監督作品。ピーター・ファレリー監督といえば『メリーに首ったけ』や『愛しのローズマリー』などが有名だけどどちらも未見で、なぜかラジー賞を受賞した『ムービー43』(感想は コチラ)だけ見ているという。
コチラ)だけ見ているという。
作品について毎度の Wikipeidaから引用。『グリーンブック』(Green Book)は、ジャマイカ系アメリカ人のクラシック及びジャズピアニストであるドン"ドクター"シャーリーと、シャーリーの運転手兼ボディガードを務めたイタリア系アメリカ人の警備員トニー・ヴァレロンガによって1962年に実際に行われた、アメリカ最南部を回るコンサートツアーにインスパイアされた2018年のアメリカの伝記コメディ映画。監督はピーター・ファレリー。主演はヴィゴ・モーテンセン。共演はマハーシャラ・アリ、リンダ・カーデリーニら。第91回アカデミー賞では作品賞など三部門で受賞した。
Wikipeidaから引用。『グリーンブック』(Green Book)は、ジャマイカ系アメリカ人のクラシック及びジャズピアニストであるドン"ドクター"シャーリーと、シャーリーの運転手兼ボディガードを務めたイタリア系アメリカ人の警備員トニー・ヴァレロンガによって1962年に実際に行われた、アメリカ最南部を回るコンサートツアーにインスパイアされた2018年のアメリカの伝記コメディ映画。監督はピーター・ファレリー。主演はヴィゴ・モーテンセン。共演はマハーシャラ・アリ、リンダ・カーデリーニら。第91回アカデミー賞では作品賞など三部門で受賞した。
本作は、シャーリーとヴァレロンガに対するインタビューや、劇中にも登場したヴァレロンガの妻宛ての手紙に基づき、監督のファレルや、ヴァレロンガの息子であるニック・ヴァレロンガによって製作された。 題名は、ヴィクター・H・グリーンによって書かれたアフリカ系アメリカ人旅行者のための20世紀半ばのガイドブック「黒人ドライバーのためのグリーン・ブック」にちなんで付けられている。
本作は、2018年9月11日にトロント国際映画祭で世界初公開され、ピープルズチョイス賞を受賞した。2か月後の2018年11月16日、ユニバーサル・ピクチャーズからアメリカ合衆国で劇場公開され、世界中での興行収入は2億4200万ドル以上である。アカデミー賞の最優秀作品賞、脚本賞および助演俳優賞(アリ)を受賞し、主演男優賞(モーテンセン)および編集賞にもノミネートされた。本作は批評家から大方肯定的なレビューを受け、2人の俳優のパフォーマンスは賞賛されているが、映画内での歴史的な描写の不正確さと、いわゆる典型的な「白人の救世主」の描写について批判を集めている側面もある。
2017年5月、ヴィゴ・モーテンセンが出演するための交渉が始まった。監督はピーター・ファレリー、脚本はトニー・リップの息子、ファレリー、ニック・バレロンガ、ブライアン・ヘインズ・クリーが務めている。同年11月30日、モーテンセンの出演が正式に決定し、マハーシャラ・アリ、リンダ・カーデリーニ、イクバル・セバがキャストに加わった。同週に正式に製作が開始した。2018年1月、セバスティアン・マニスカルコがキャストに加わった。 スコア作曲家のクリス・ボウワーズは、アリに基本的なピアノ技能を指導した。また、演奏する手のクローズアップが要求されるシーンでは、アリの代役としてピアノを演奏した。
本作は批評家からおおむね称賛を受けている。Rotten Tomatoesでは映画批評家が79%の支持評価を下し、また平均評価は10点中7.28点となった。MetacriticのMetascoreは52人の批評家により、100点中69点となった。第91回アカデミー賞の作品賞では同じく有力候補として注目を集めていた『ROMA/ローマ』と並んでノミネートされ、結果、本作が受賞した。 批判の背景には、主人公であるトニー・リップの役柄が「黒人を差別から救う救済者」として誇張された伝統的すぎるキャラクターだったこと、また、シャーリーの遺族から「この映画が伝説のピアニストと家族の関係について観客に誤解を与えるような解釈をしている」との抗議も受けていたことがあるのでないかと指摘されている。とのこと😌
映画は高級クラブから始まる。主人公のトニー・リップ(ヴィゴ・モーテンセン)はフロア係兼用心棒として働いているらしい。客同士のもめごとがあれば、暴力でこれを制するというやり方は、現代では通用しないと思うけれど、1962年当時は当たり前だったのかな? 粗野ではあるけれど、マフィア(?)の大物が大切にしている帽子をわざと隠し、自身の手柄にでっち上げて取り入るなど悪知恵も働く様子。しかし、勤め先のコパカバーナが改装工事のため2ヶ月間仕事がなくなってしまう。トニーの雇用形態が不明なのだけど、店を開けないとなるとその間無給なのね? なかなかキビシイ😱
リップというのは通称名で、本名はヴァレロンガというイタリア系移民。妻のドロレス(リンダ・カーデリーニ)と2人の子供との4人暮らし。子どもたちが幼いこともあるけど、同じ部屋で4人で寝ているような状態で、決して裕福ではない感じ。でも妻は美人で明るく、親戚や友人の多い陽気なイタリア人家庭という印象。水道工事に来た黒人作業員2人に分け隔てない態度で接し、コップで水を進めるドロレス。一方、トニーは彼らが使ったコップを捨ててしまう。ゴミ箱にコップが捨てられていることに気づいたドロレスは、やれやれという感じでそれを拾い元に戻す。ドロレスには全く人種差別はなく、トニーにはあるということ。そういうのをさりげなく見せるの上手い。
トニーは大食い競争などで小銭を稼いで来るものの、仕事がなければ生活できず困った状況に。そんな中、ドクター・シャーリーという人物が運転手を探しているという情報が入る。早速、面接に向かうとそこはカーネギーホール。依頼人はなんとカーネギーホールの上に住んでいるのだった。インド人執事?に導かれて部屋に入ると、まるでどこかの王室かのような内装。現れたのはこれまたエジプトの王族のようないでたちの黒人男性が現れる。やや気取った動作でこれまた玉座のような椅子に座る。この登場はインパクトがあった。マハーシャラ・アリの立ち居振る舞いが素晴らしい
ドクターというから白人の医者だと思い込んでいたトニーは驚きを隠せない。ドクター・シャーリー(マハーシャラ・アリ)は8週間の南部へのコンサートツアーを計画しており、そのツアーに同行するマネージャー兼運転手として雇いたい。荷物の運搬や雑用などもやって欲しいとのこと。用心棒としてのプライドか、人種差別もあってかそんな雑用などやる気はないと断ってしまう。いくらお金のためとはいえ、この申し出はなかなか条件が厳しい。とくに人種差別の激しい時代になかなか受ける人はいないかも?🤔
しかし翌朝、ドクターから電話がかかって来る。ドクターはドロレスに変わって欲しいとのこと。そして、8週間トニーが不在でも大丈夫かと尋ねる。要するに面接の結果は合格ということ。雑用係の部分についてはドクターが譲歩したんだっけ? とにかく2人はツアーに出ることになる。出てくれないと困るんだけどね😅
出発の朝ドクターの所属のレコード会社の人から時間厳守の注意を受ける。時間を守れなければ給料を払わないというのはなかなかキビシイ。イヤ、もちろん時間厳守はプロだから当然だけど、車移動の場合はどんなアクシデントがあるか分からないからね。とはいえ、ドクターの荷物をトランクに積み込むのをインド人執事に押し付けるなどトニーもちゃっかりしている。ちょこちょここういうトニーの粗野だけど憎めないところを見せつつ笑いをとるのが上手い。
レコード会社の社員はまたトニーに1冊の本を手渡す。グリーンブックと呼ばれるそれは、黒人用のガイドブック。と言えば聞こえがいいけど、要するに当時は黒人が泊まれるホテルが限られていたということ。成功をおさめ優雅な暮らしをしているドクター・シャーリーですら、どのホテルにも泊まれるというわけではないということ。人種差別問題を描いた映画は何本も見ているので、ホワイトオンリーについてはいろいろ見たつもりだけど、このガイドブックのことは知らなかった。
ツアーには他に2名のバンドマンマンが同行。1人はドイツ人で1人はユダヤ人だったかな? 2人とも白人ではあるけれど、基本的にドクター・シャーリーを尊敬している様子。この2人は別の車で行動するため、基本道中はトニーとドクター・シャーリーのみ。
ドクター・シャーリーはトニーの服装がコンサート会場である上流階級の家などにそぐわないと考え、服をあつらえようとしたり、本名であるヴァレロンガは発音しにくいので簡略化した呼び方にしようと提案するけれど、型にはめられることを嫌い、プライドもあるトニーとしてはこれを断る。その服装では会場内に入れないと言われるけれど、他の運転手たちと同様に外で待っているから構わないと言う。以前、英会話教室に通っていたことがあって、それぞれあだ名をつけましょう的なことになった。自分の英語名は忘れてしまったし、この場合はお遊び的な要素もあるので、特に何も思わなかったけれど、例え発音が難しいからといって人に名前を変えろというのは失礼な気がする。アメリカでヒットした「上を向いて歩こう」を"SUKIYAKI"というタイトルにされたことは、差別とまでは言わないけれどバカにされたような気がしている。文化も違うし、あくまで個人的な感想😌
そんなわけでトニーは屋敷内でのコンサート会場には入れなかった。しかし、外に漏れてきたドクター・シャーリーのピアノの音に魅了されてしまう。粗野な態度でおしゃべりでドクター・シャーリーをうんざりさせていたトニーだけれど、美しいものを美しいと感じる素直な心があるということ。とはいえ、コンサートが終わるころには、他の運転手たちと賭け事をしていたりするのだけど😅
えーと。見てから一ヶ月以上経ってしまって、ちょっと記憶があいまいになってきた。記憶に残っているエピソードを書いていくけど順番が入れ違っているかも?💦
今作で一番重要なのはやっぱり2人のおじさんの友情。おじさんが友達になるにはそれなりの相互理解が必要になる。上品でいつもきちんとしているドクター・シャーリーと、粗野でおしゃべり好きなトニーの珍道中は最初はぎくしゃくしているけれど、主にトニーが黒人差別の現実を知って憤りを感じ、少なくともドクター・シャーリーは差別されるべき人ではないと考えたことが大きかったのかなと思う。一方で、屈託がなく本能のままに突き進むけれど、実は繊細な優しさも持ち合わせているトニーが、ドクター・シャーリーの殻を破っていったということもあると思う。トニーは全く意識していないと思うけれど。
まだ2人の間に信頼関係が気付けていない頃、休憩で立ち寄った店で地面に落ちていた石のキーホルダー的なものをトニーがカゴに戻さずポケットに入れてしまったことがあった。たまたまそれをバンド仲間が見ていて、ドクター・シャーリーに言ったらしい。ドクター・シャーリーはトニーに店に返してくるように言う。その上で自分がトニーに買ってあげようと申し出る。トニーはそれを断り戻しに行く。これ戻したように見えたけれど、後にトニーの部屋で見かけたような? このエピソードはトニーのチャッカリさとドクター・シャーリーの正しさを示すために入れたのかな? 実話ベースだから、各エピソードなども本当にあったことのようだけれど、これも本当にあったのかな?
トニーはドロレスから手紙を書いて欲しい言われており、食事の時などに彼なりに必死に書いている。おそらくあまり学がないであろうトニーだけど、不器用ながら率直な手紙でそれはそれで好感がもてた。でも、ドクター・シャーリーはせっかくラブレターを書くのだから、もう少し詩的にした方がいいと手紙の内容を口述してくれる。トニーはそれを書き記しドロレスに送る。ドロレスは喜び、親戚や仲間たちの間でも話題になる。この手紙の共同作業は結構信頼関係ができてからだったと思うけれど、思い出したので入れておく。この手紙のエピソードはラストにニヤリな展開が待っている。
えーと。スタンウェイのピアノが用意されておらず、係の男性にトニーが文句を言ったのは結構早めだったよね? 契約書にコンサートにはスタンウェイのピアノを用意することと書かれているので、主催者はもちろんトニーとしてもそれを守らなければならない。でも、用意されていたピアノはスタンウェイではなく、粗末なものだった。舞台の準備をしていた男性にトニーが契約と違うと声をかけると、男性は面倒くさそうにピアノなんてどれも同じだろうと言う。この男性にも黒人差別的な気持ちはあると思うけれど、それよりは芸術など興味がないというような、粗野な人物に思えた。とはいえ、バカにした態度であることに変わりはなく、とにーは激怒しピアノを用意させる。こういう人もいるよね。でも、プロとしてあり得ないこと! 例え今回限りの雇われ仕事であっても、仕事は仕事だからね。
前述したとおりドクター・シャーリーは黒人なので、泊まれるホテルが限られている。例え高級ホテルがコンサート会場であっても、そのホテルに泊まることはできない。後に白人運転手と黒人の主人という構図を複雑な表情で見つめる黒人労働者たちのシーンが入る。これは後のドクター・シャーリーのセリフの伏線でもあるのだけど、どうやらドクター・シャーリーは黒人たちの中でも異端者なようで、気品があり紳士然としたドクター・シャーリーは黒人ホテルになじめない様子。中庭で1人お酒を飲んでいたけれど、そのうちどこかへ出かけてしまう。
その後、トニーのもとにバンド仲間から連絡が入る。ドクター・シャーリーがバーで白人たちに絡まれているとのこと。黒人が来る場所ではないと4~5人の男たちがドクター・シャーリーを殴っていた。トニーは止めに入るけれど彼らは激高してやめる気配がない。トニーはピストルを持っていることを匂わせる。明らかに怯えているものの、引くに引けない白人たち。すると店主が割って入り、トニーたちに店から出ていくように言う。どう見ても白人たちの方がおかしいわけだけれど、この当時は黒人しか入れない店が存在していたわけで、この店がそうだったかは別として、白人たちにとっては黒人を追い出すことが正義なんだよね。差別とは感じていない。そうい無自覚の差別が一番たちが悪い😫
ある日、トニーの勧めでスーツを作ろうと洋品店に入るも、そこの店主にもドクター・シャーリーに売る服はないという主旨のことを、丁寧な口調で言われてしまう場面がある。相手の態度が無礼であろうが、丁寧であろうが黒人に対する扱いは同じということ。暴力的なシーンは視覚的にも辛いけれど、こういう差別がじわじわとみている側にも効いてくる。
別の夜、豪邸のコンサートは大盛況。観客も拍手喝采だし、主人は大喜び。ドクター・シャーリーに対して感謝を述べてとても良い雰囲気。この人ならば差別しないではないかという気すらする。そんな思いがドクター・シャーリーの中にもあったのかもしれない。トイレを使いたいと申し出る。すると主人は庭の小屋を指さし、あちらですと普通に答える。この家の黒人使用人たち専用のトイレ。イヤ、普通のトイレを使いたいと言うと、それは無理だと答える。にこやかで高圧的な態度ではないけれど、当然いい気分ではない。ならばホテルに戻って用を足すしかなく、戻って来るのに20分以上かかると言うと、待ちますと答える。この主人の中にも差別意識があることは間違いないけれど、招待客の手前ということもあるのかなという気もする。たった1人の勇気が多くの意識を変えることもあるけれど、その勇気を持つことは難しい🤔
えーと、ある夜警察からトニーが呼び出されたのはどの順番だったかな? たしかYMCAの施設とかそんな感じだったように思うけれど、ドクター・シャーリーは裸で、裸の青年と一緒に捕まっていた。ドクター・シャーリーは拒否するけれど、トニーは賄賂を払い釈放してもらう。ハッキリと語られてはいないけれど、要するにドクター・シャーリーはゲイということだよね。この時代は同性愛も違法だったんだっけ? アメリカは州によって法律が違ったりするので正確なところは分からないけれど、とにかくこの時代に黒人でLGBTというのはかなり大変だったのではないかと思う。
さらに辛い話が続く。ある夜車を走らせているとパトカーが追ってきて止まるように指示する。どうやら夜間に黒人が外出するのは法律で禁じられているらしい。これは何故? トニーは道を間違えてしまって時間がかかってしまったと言うけれど、それが反抗的と受け取られたのか2人は連行されてしまう。トニーの態度が悪く逮捕されたのに、どうして自分まで牢に入れられるのかと抗議するドクター・シャーリー。ここはちょっと笑える感じ。でも、そんな彼に差別的な態度を取る警官。若い相棒はそこまで差別的ではないけれど、この少し年長の警官は本当に嫌な感じ😠
ドクター・シャーリーは電話をかけさせてくれるよう頼むけど、差別的な警官は拒否。でも、若い警官がそれはまずいと言う。弁護士の同席を求める権利があるとかそういうことだよね? ドクター・シャーリーは手帳をめくり1本電話を掛ける。そして電話を代わってくれるように署長に言う。横柄な態度で電話に出たのに、急に態度を変える署長。まるで浅見光彦シリーズのような豹変ぶりだけど、この電話の相手がすごかった! なんとロバート・ケネディ😲 どうやらこれも本当にあった話だったらしい? 改めてドクター・シャーリーの大物ぶりが分かる。
無事、釈放された2人。ドクター・シャーリーと同じホテルにトニーが泊まったのはこの夜だったかな? 2人並んで粗末なベッドで寝る。具体的にどんな話をしてたか忘れてしまったけれど、この夜で2人の距離がぐっと縮まったことは間違いない。ロードムービーにありがちな展開ではあるけれど、やっぱりこういう過程を経て人は心を許し打ち解けていくものかもしれない。
最後の公演地は豪華なホテルでのディナーショー。白人のマネージャーはやり過ぎな感じがするくらい丁寧な態度でドクター・シャーリーを歓迎する。でも、案内した控室は厨房内の物置。後にそれを知ったトニーがマネージャーに抗議するけどドクター・シャーリーはそれを止める。トニーは一緒に食事をしようと誘うと、自分は入れないと断る。でも、トニーたちが食事をしていると、タキシードに身を包んだドクター・シャーリーが現れる。
しかし、マネージャーは彼を止める。黒人は入れないというのだった。毅然とした態度で自分もここで食事をすると主張するドクター・シャーリー。もちろんトニーも加勢するけれど、ドクター・シャーリーが今回はあまりに強硬なので宥めようする。それくらい意志が固かった。結局、レストランで食事をすることはできなかったのだけど、それならば演奏はしないと言い、慌てるマネージャーを置いて去ってしまう。マネージャー氏には災難だけど、これまでの差別の数々にとうとう堪忍袋の緒が切れたのでしょうかね。契約があるから正しいこととは言えないかもしれないけれど、見ている側としても胸のすく思い😀
2人は黒人が集まる店に行き、そこのカウンターで飲み始める。ここでの2人の会話には何か素敵な言葉があったかもしれないけれど忘れてしまった😣 その店にはちょっとしたステージがあって、ピアノも置いてあった。ドクター・シャーリーはそこで演奏をする。これはタキシード着てたので、職業を聞かれて店の人に弾いてみろと言われてた気がする。ドクター・シャーリーがピアノを弾き始めると、人々は彼の演奏に引き付けられ、ギターなどの楽器を演奏し始める人も現れて、セッションとなる。
この演奏は見ている側もとっても楽しかったけど、とりわけドクター・シャーリーにとって楽しく幸せなひと時となった。白人社会からも黒人社会からもはみ出した存在と感じていたけれど、受け入れられたという思い。高いと思っていたハードルは、そんなに高くはなかった。もしかしたら自ら異端者になっていってしまった部分はあるかもしれない。自分には黒人音楽が理解できないとか、それが理解できない自分は受け入れてもらえないとか、そういう思い込みがあったのかも。このシーンは見ている側も楽しかった。
ドクター・シャーリーが無防備に大金を持っていることを見せてしまったため、車のそばに3人組の男たちが待ち伏せしていた。トニーは銃を取り出して空へ向けて発砲。3人組は逃げて行った。バーでドクター・シャーリーが絡まれた際に、銃は持っていないと言っていたのに実は持っていたというオチ。トニーのチャッカリした感じがおもしろい。と、同時にやっぱりアメリカって銃社会なのだなと思ったりする。まぁ、トニー自身はマフィアというわけではないようだけれど、かなり近いところにいるのかなと思ったりもする。
さて、全日程を終えたドクター・シャーリーとトニーは岐路につくことになる。本来ならば1泊して翌日立つ計画だったけれど、トニーがクリスマスを家族で過ごしたいと希望しため、そのまま帰ることに。暗い道を走っていると、後ろからパトカーが。またか黒人だからという理由で止められるのかとうんざりする2人。ところが現れた警官は、タイヤがパンクしていることを知らせてくれて、タイヤの交換まで付き添ってくれた挙句、さらに途中まで先導してくれた。もちろん、ドクター・シャーリーが乗っていることも承知の上で、まったく自然な対応だった。2人はことさらに感動したり過剰反応してはいなかったけれど、きっと"普通"の対応に感動していたはず。
今作で描かれていた差別は、例えば『デトロイト』などで見た暴力的な描写は少なかったし、白人の依頼主もマネージャー氏も差別はしているものの、一応丁寧な態度をとってはいた。だけどやっぱり理不尽は理不尽。見ている側としてもストレスがたまっていたようで、この警官の"普通"の対応に感動して泣いてしまった😭 よいシーンは他にもたくさんあったのだけど、泣いてしまったのはここだけで自分でもビックリしたけど、もしかしたらそれが狙いなのかもしれない。
さて、夜道を必死で走るトニーだけど、疲れが限界に達してしまう。すると、なんと代わりにドクター・シャーリーが運転をする。運転できるんだね。ここで重要なのは主従が変わったということではなくて、ドクター・シャーリーが友人としてトニーを助けたいと思ったということ。執事以外に友人がいなかったドクター・シャーリーにとって、はじめこそ人種差別を持っていたトニーが、旅を通してドクター・シャーリー=黒人に対する理不尽な出来事に接し、さらにドクター・シャーリーと友情が芽生えたことにより、偏見をなくしていく過程を見ていると、未来にほんの少しでも希望が持てたのかもしれない。そして単純にトニーに友情を感じたのでしょう。
車は雪が積もったニューヨークに到着する。ドクター・シャーリーがトニーを起こすと、彼はドクター・シャーリーに家に寄っていくように誘う。ドクター・シャーリーは遠慮して帰っていく。この時は2人握手してたかな? トニーが帰宅すると家には親戚などが集まっており、トニーを温かくやや乱暴に迎える。シェイクスピア(だったかな?)が帰ってきたと言ってたの笑った。トニーが詩的な手紙を送っていたからだよね。食事中、誰かが黒人に対して失礼な発言をすると、トニーが嗜めるシーンがある。ここでも、トニーの偏見がなくなったことを表している。差別は偏見が生み出しているのであって、それを捨て去ることは誰でもできるというメッセージなのだと思う。
しばらくするとドアベルが鳴る。トニーがドアを開けるとドクター・シャーリーが立っていた。ニッコリ笑ってハグするトニー。そして、優しく迎え入れる。ドロレスがドクター・シャーリーをハグして「手紙をありがとう」と言うシーンで映画は終わる。
この終わり方はとっても素敵だった。途中ドロレスが嬉しそうに詩的な手紙を皆に見せているシーンがあったけれど、彼女は本当は誰が書いていたのかちゃんと分かっていたということ。それはドロレスがトニーという人物のことをよく理解しているからでもあるし、ドクター・シャーリーに対して全く偏見がないことを表している。少しコミカルでありながら、しっかり意図を伝える脚本と演出が素晴らしい!
エンドロールでトニーはその後クラブに戻ったこと、ドクター・シャーリーとの友情はドクター・シャーリーが亡くなるまで続いたことが知らされる。エンドロールでだったか、何かの記事でだったか忘れたけど、トニーはドクター・シャーリーの死後数ヶ月で亡くなったのじゃなかったかな? 偶然かもしれないけれど、なんだか2人の絆を感じるエピソード。トニーは映画に出演したことがあったんだっけ? たしか映画に関わる仕事をしていたはず。その影響かな? 息子さんのニック・ヴァレロンガはプロデューサーになったということだよね? 今作のプロデュースを担当しているけれど、息子さんの視線が入っているからか、粗野だけど優しいトニーが魅力的。
2人芝居の部分が多いけれど、キャストはみな良かった。ドロレスのリンダ・カーデリーニが良かった。しっかり者で手綱をしっかりつかんでいるのに女性らしさを失わず、かわいらしい。男くさい映画に華を添えていた。ドクター・シャーリーのマハーシャラ・アリが素晴らしい! この役でアカデミー賞助演男優賞を受賞したのも納得の演技。品があって知的で優雅。でも、それは傷つかないためのバリアでもある。黒人からも白人からも疎外された孤独をまとって痛々しい。トニーに少しずつ心を開いていく過程もしっかり伝わってきた。いつも上手いけど、これはさすがの演技
そして、なんと言ってもトニーのヴィゴ・モーテンセンがスゴイ! 役作りのために体重増やしたりしたそうだけれど、そういう外的アプローチはもちろん、がさつで品がないけれど憎めない人物を好演。トニーは悪い人ではないけど、品行方正というわけでもない。結構チャッカリしてる部分もあったりする。でも、根本的な部分で曲がったことはしない。そのさじ加減が絶妙。例えばフライドチキンにはしゃぐ姿などがかわいく、それがトニーを魅力的な人物にしている。素晴らしい
とにかくおじさん2人の旅がおもしろい。何気ない会話で違いを見せつつ、友情を育む過程を自然に描いている。2人の道中は差別にあったりと辛いことも多いけれど、例えばケンタッキーでケンタッキーフライドチキンを食べてる!とトニーがはしゃいだり、嫌がるドクター・シャーリーに無理やりそれを食べさせて意外にも気に入ったり、調子にのったトニーが骨を窓から投げ捨てた直後、車を止めて拾わされたりとコミカルなシーンを入れつつ見せる。コミカルシーンもわざとらしさやあざとさがなく楽しめた。感動シーンもあるけど、全体的におしつけがましくない。でも、しっかり心に響いてくる。
ニューヨークの風景や、トニーたちが暮らす界隈の感じ、ドクター・シャーリーの豪華な部屋や、南部の豪邸、そして南部の景色など映像も良かった。これ自分的年間ベスト10入り確実。しかもかなり上位じゃないかな? 現時点では1位。
公開から3ヶ月、見てからも2ヶ月以上経ってしまったけど、まだ上映している映画館あるみたい! 派手なアクションや特殊な視覚効果があるわけではないけど、これは是非映画館で見て欲しい作品。マハーシャラ・アリ好きな方是非! ヴィゴ・モーテンセン好きな方必見! 見て!!
 『グリーンブック』公式サイト
『グリーンブック』公式サイト

 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿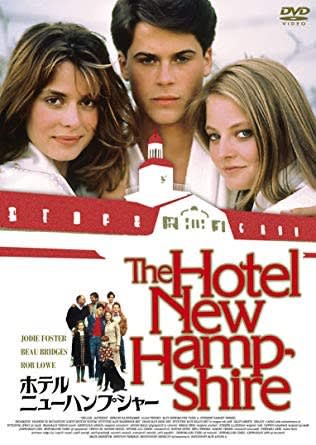
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿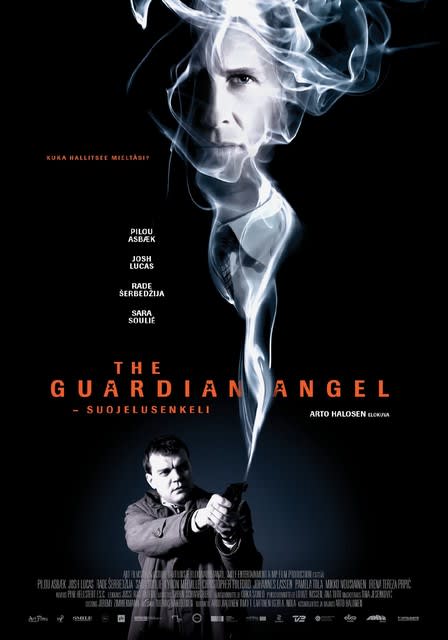
 Twitter投稿
Twitter投稿

 coco投稿
coco投稿
 coco投稿
coco投稿









 【tv】100分de名著「平家物語」(第3回)
【tv】100分de名著「平家物語」(第3回)

 平敦盛の最期に注目
平敦盛の最期に注目 戻って来た武将をなんなく組み伏せた熊谷次郎直実。武将の顔を見ると薄化粧をした若く美しい少年だった。直実は自分の息子小二郎を思い出してしまう。
戻って来た武将をなんなく組み伏せた熊谷次郎直実。武将の顔を見ると薄化粧をした若く美しい少年だった。直実は自分の息子小二郎を思い出してしまう。 伊集院光氏:いいシーン。当時の死の価値観が伝わる。助け舟に乗ろうとしている姿を罵倒された。そんなことを言われて生きるよりはということ。その後の2人の心の複雑な・・・
伊集院光氏:いいシーン。当時の死の価値観が伝わる。助け舟に乗ろうとしている姿を罵倒された。そんなことを言われて生きるよりはということ。その後の2人の心の複雑な・・・ 平敦盛のシーンは有名だよね。結果、討たれてしまうけれど、ズッコケぶりが続いていた平家の男たちの中ではしっかりした若者な気がする。美少年であるというのも悲劇を倍増している。とはいえ、戦に薄化粧して行くのは当時の習わしなのかしら? これも貴族化を表現しているのかな?
平敦盛のシーンは有名だよね。結果、討たれてしまうけれど、ズッコケぶりが続いていた平家の男たちの中ではしっかりした若者な気がする。美少年であるというのも悲劇を倍増している。とはいえ、戦に薄化粧して行くのは当時の習わしなのかしら? これも貴族化を表現しているのかな?





 南都焼討(
南都焼討(

















