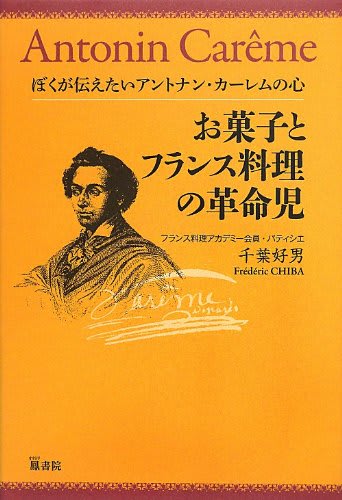著 者 内館 牧子
出版社 講談社
終業20分前、63歳定年で社を去る主人公・田代壮介の描写からはじまる。
大手銀行の出世争いに敗れて、最後は子会社の社員40名の専務として終わる。
右肩上がりの時代を戦い続けてきた団塊の世代の”その後”が舞台。

著者が同世代の生態を、心象の襞や生活の格差などを書き入れリアルに表現した現在小説。
この世代の男の心の揺れ、人情、寂しさ、戸惑い、気負い、疎外感、誇り、あきらめ、焦り etc。
気味悪いくらいに全部思い当たる。女性ながらによくも描いたものだ。ここまで見通したように書かれると、ちょっと困る。
高校時代にトップを争った二宮。東大、商社と進んだが48歳で退社、今はボクシングのレフェリーで稼いでいる。30年振りの邂逅でこう言う。「人は死ぬまで、誇りを持って生きられる道を見つけるべきだと・・・あの時。骨身に染みた」
対する田代。「俺はこの齢になって二宮に負けたとわかった。生きている限り、勝負は動くし、何よりも、人生は勝ち負けで測れるものではない。だが、今の暮らしぶりを考えると、二宮の方がずっと充実し、楽しみ、他から必要とされている。それでも人生に勝ち負けはない、と言う人はあろうが、それは違う。負けだよ、負け。そう思った」
著者は”あとがき”で 『六十代というのは、男女ともにまだ生々しい年代である。いまだ心技体とも枯れておらず、自信も自負もある。なのに、社会に「お引き取り下さい」と言われるのだ』と書き、『アンチ・エイジング至上の現代日本において、まだ若い者には負けないとする《終わった人》に、坂本義一が英国を論じた「重要なのは品格のある衰退」は大きな示唆である』と述懐する。
女たちは、ドライでクール。田代の妻はこう言う。『私ね、老夫婦が貧しい食卓で向かい合う毎日って、決していいこととは思えない。そんな毎日じゃ、「お互いに齢とったよな」くらいしか考えないでしょ。年齢ばかり考えていることが、人を齢取らせるのよ』
娘の道子が、巻末で両親に意見する正論の激しいこと。これもその一つ。「仕事を離れて、スーツにふさわしい息をしていない男には、、スーツは似合わなくなるのよ」 スーツが死んで、息をしなくなるということか。全部実感している。
右肩上がりのド真ん中を走り続けてきた畏友・親友・悪友に大いに奨めようと思う。
さて、この物語は、やがて映画になるに違いない。で、遊びに配役を試みた。
田代壮介 渡辺謙
妻・千草 池上季美子
娘・道子 中越典子
久里 井川遥
トシ リリー・フランキー
二宮 高橋克己
南校OB 生瀬勝久、 村田雄浩、 柳葉敏郎、 岸谷 五朗、ピエール瀧。
監督は、是枝裕和 or 岩井俊二 or 河瀬直美というところでどうか。