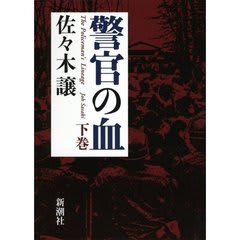尊敬するジャーナリストが句集を上梓した。
日々のツイッターへの投稿を、一冊にまとめたもの。句の脇に著者自身が書き込んだメモに、何ともいえない味がある。門外漢には句の理解の手助けになる。

いわば自費出版。ある夜の集まりでご本人より戴く。
確かに句造りは、老いにいい。しかし難しい。
作者は、あの田中角栄の逮捕のスクープをものした過去を持つ。ここにその面影はない。優しさと気遣いと温かさ。このように齢を重ねたい。
尊敬するジャーナリストが句集を上梓した。
日々のツイッターへの投稿を、一冊にまとめたもの。句の脇に著者自身が書き込んだメモに、何ともいえない味がある。門外漢には句の理解の手助けになる。

いわば自費出版。ある夜の集まりでご本人より戴く。
確かに句造りは、老いにいい。しかし難しい。
作者は、あの田中角栄の逮捕のスクープをものした過去を持つ。ここにその面影はない。優しさと気遣いと温かさ。このように齢を重ねたい。
1974年から約10年間、創価学会青年部は『戦争を知らない世代へ』シリーズ全80巻を出版した。これは、文字通り戦争を知らない世代が、父母、祖父母の世代を訪ね、一人ひとりの戦争体験を聞き書きしたもので、その範囲は全都道府県に及んだ。
その作業は、時代の流れとの戦いであったし、重い口を開かせる粘り強い根気の要る作業だったという。まさに昭和の反戦万葉集と呼ぶに相応しい壮大な歴史的事業であったと言える。
あれからさらに40年を経、今ここに上梓されたのは、その男たちの原爆の証言集である。当時12歳から18歳の子供たちが身を置いた地獄の姿が堰を切るごとく語られている。冷静に語られている。その模様は、映像よりもはるかに雄弁かつ衝撃的である。

裏表紙からは、同じ内容が英語で綴られている。日本語と英語が背中合わせに一冊の本を構成しているのが特徴だ。
ヒロシマ、ナガサキ、そしてフクシマ。三度の被爆国日本。原発がなし崩しに稼働されようとしている日本。この本が問う物はとてつもなく深くて大きい。
司馬遼太郎、講談社文庫、全4巻。

放送中の大河ドラマ『 軍師官兵衛 』に刺激され読む気になる。
官兵衛もさることながら、秀吉、信長のひととなりや思想・性格・行動が、ともに生きていた如くに活写されている。また、戦国大名たちの一時の興亡のさまがよく判る。
しかしながら、東野圭吾、誉田哲也、池井戸潤など、今日の人気作家に比べると、運びが如何にもまだるっこい。周到微細な取材の上に作者の縦横な想像力が駆使されてるのだから当然か。 重厚さは圧倒的だ。
つい最近まで司馬遼太郎は同時代の作家だった。が時を経、今は私にとって、大仏次郎や山岡荘八のような存在になっている。司馬遼は歴史になってしまった。
さて、来年の大河ドラマは『花燃ゆ』。松陰の妹の文がヒロインとか。今度は『世に棲む日々』を読むことになるか。
『龍馬伝』では『龍馬がゆく』を読んだように。もう4年も前になるのか。
著 者 矢吹 孝男
発行元 幻冬舎
定 価 1200円+税

著者とは同じ年の生まれである。彼が綴る半生の時代は、私と重なる。
叙述される背景や雰囲気は、まるで自分のことのよう。それはディテイルに及ぶ。
私も御三家(橋幸夫、舟木一夫、西郷輝彦)よりも松島アキラの『湖愁』を好んでいた。バイクが青春の一頁。東海道新幹線の開通。第4次中東戦争。”日本鋼管”とは、これまた懐かしい。共感・共有、まだまだ、上げればきりがない。
会社倒産の末の関西への逃避行。途中一泊の名古屋が、その後の事業の主舞台になろうとは・・。
著者の生命力には圧倒される。しかも世のため人のためが身上。見事としか言いようがない。
こうした半生記、悪戦苦闘の末の成功譚に共通するのは、" 主人公 "の揺るぎない信念と飽くなき意欲、それに出会いだろう。読む進むうちに、そのドラマに泪し悔悟し高笑いする。人生は波乱万丈だから面白いのだ。
著者は、間違いなく日本の国の介護システムのパイオニアの一人であろう。
それにしても、政治のなんと遅いことか。規制どころか障害と言うに相応しいほどだ。民間活力とは片腹痛し。
話題書で眩い幻冬舎が、この種の出版に注力しているとは知らなかった。見直した。
著者 ヤマザキマリ
発行 文芸春秋 文春新書

実に小気味のいい本である。著者が、映画『テルマエ・ロマエ』の原作者であることを知らずにいた。
大体が、テレビで流れる映画『テルマエ・ロマエ』のCMカットは、何やら騒々しく、俳優の阿部寛を好きでなかったこともあり、さらには原作がマンガと知るに及んで、関心外ではあった。
しかしながら、この自身に満ちた論述に触れて、タダモノでない気配を感じるに至る。類例の少ない日本人女流作家ではなかろうか。
終章の、興業収入58億円の映画『テルマエ・ロマエ』の原作使用料が100万円という騒動の下りの当事者の言い分は、興味を惹かれる。あまり知られていない業界の遣り口を世に曝したという点において功績大である。
藻谷浩介/NHK広島取材班
角川oneテーマ21

なるほど刺激的な本である。
高度成長経済の右肩上がりの時代に青春を過ごしてきた世代には、というより私には文明感が一変するルポが続く。どれも合点がいく。いちいちに「やっぱりそうか」「エッ、そんなに進んでいるのか」と納得するばかり。
自分から出来そうなこともありそうだ。しかし、ならば「やるか」とはならない自分が情けない。でも一人でも多くの人がこの本を読めば、やがて時代が目に見えて変わっていくのではなかろうか。
著者藻谷浩介は、減速する経済の主因が減り続ける人口にあることを分析・表出して広く世に知られるが、たまに観る報道番組での健在振りは頼もしい限りである。また、同チーム取材班のNHK広島:井上恭介、夜久恭裕両氏の”安心の原理”を志向する意思と情熱は素晴らしい。籾井某の騒動には振り回されず、いい仕事を続けて貰いたい。切に願う。
主婦の友新書
著者 いつか
定価 820円

”なくなる日”は、主婦友新書の意欲シリーズ。
著者32冊目となる新著。男論、女論、恋愛論、結婚論、別れ論、仕事論、まだまだある。江戸物、旅物、エトセトラエトセトラ。テーマが多彩。人脈はマルボーからキョウジュまでと果てがない。
初めての出会いの時、肩書は《コピーライター》。「中いつか(五日)休みで、仕事をするのは週二日というのが私の名前」とのたもうた。その後10年振りで目の前に現れた時は《エッセイスト》。変幻自在である。
エネルギッシュな会話と軽いフットワークで紡ぎだした文章は実に読み易い。自身の実体験だから説得力がある。
年齢からもキャリアからもそろそろライフワークを望みたいところだ。
豊富な人脈を精査して選んだ男との対談集。勿論女でもいい。コメントではなく語り。地味な仕事、陽の当らない生涯、一途な生き方、なぜこの男(女)はこの道を選んだのか。その生きざまを掘り下げる。そんな仕事はどうだろうか。10人ほどを1冊で。
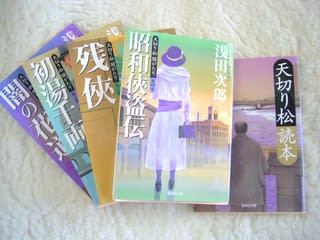
親分の安吉(目細の安)、寅弥(説教寅)、おこん(振袖おこん)栄治(黄不動の栄治)、常次郎(書生常)、最後に主人公の松蔵(天切り松)。