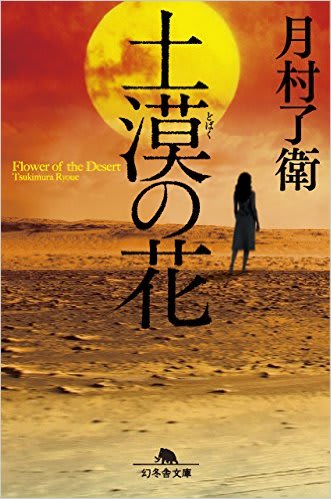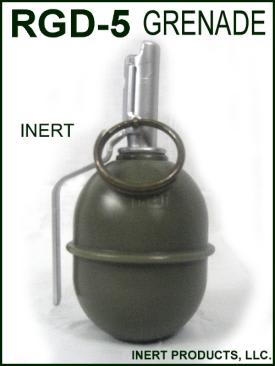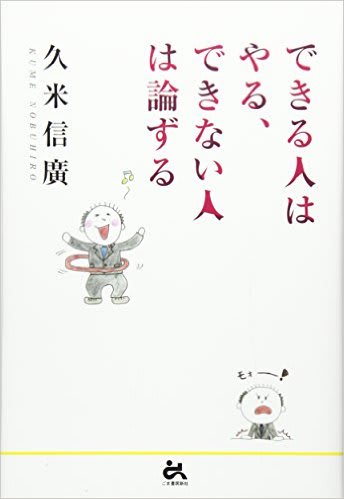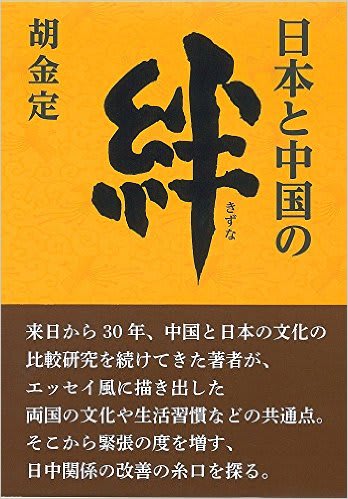著 者 松村友視
出版社 河出書房新社

手にするにはちょっと抵抗感があった書名。赤瀬川源平の『老人力』より先に読むことになった。
77歳の著者が、中央公論社の雑誌編集長時代、自ら取材やインタビューをした人たちとの出会いを通して、見て聞いた老人たちの生き方、生きざま、姿を書き下ろしで一人一章(5頁~6頁)で纏めたもの。
有名雑誌の編集長ゆえ、相手は誰もが知る著名人が多い。伊丹十三、西岡常一、武田泰淳、田辺茂一、古波蔵保好、藤村俊二、幸田文等等。
とりわけ森繁久彌の下りは秀逸で印象が強い。映画『座頭市』シリーズに老渡世人約で友情出演した森繁久彌が今わの際に市の腕の中で虫の息で歌う ”ぼうふらが 人を刺すよな蚊になるまでは 泥水飲み飲み 浮き沈み”。
この章著者はこう結ぶ。「それにしてもあの ”ぼうふらが・・・は、森繁好みだったのか、森繁作だったのか、勝新作だったのか・・・答えはあるのだろうが、謎のままにしておこう。だが、あのシーンに、すでに大御所となった森繁久彌という稀台の役者が身銭を切ってくりだす、比類ないテイストがあらわれていたのは、遊び人の後輩たる勝新太郎監督の、大いなる手柄というものであろう。
そして巻末にはこう記す。「老人の域に達した人々から滲み出る、地味、旨味、妙味、風味、香味、珍味、苦味、佳味などのテイストが入りまじって人間味として仕立て上げられ、その味わいが私の贅沢すぎる財産となって生きている。(中略)つみかさねた年齢を一気にたどり直したあげくに、あらためて奇妙な力を与えられたというのもまた、たしかなる実感なのだ。ならばその実感を道連れに、いましばらく幻を求める道中をこなしてみようというのが、目下のところの私なりの気分なのである」