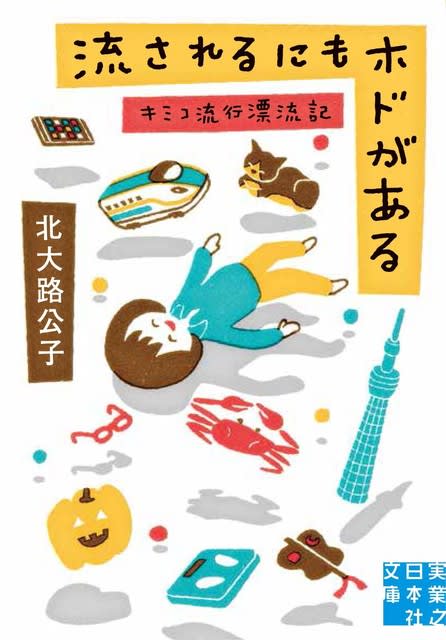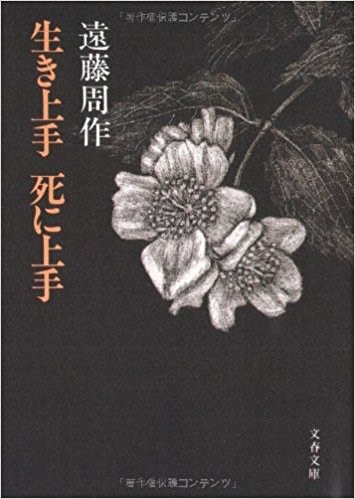著者 山本周五郎
出版 新潮文庫
頁数 上巻550頁 下巻555頁
版 平成18年5月3日第66冊
値段 上巻 18円下巻1円(アマゾン)

山本周五郎、重厚ですね。人間を見つめる眼が透徹している。「生きるとは何か」を問い、示す。
本は読む側の環境によって、興趣が違ってくる。
絶望と孤独の中で覚悟の戦いに突き進む主人公三浦主水正の生き方は、世代によって共感や実感は大きな差があるだろう。例えばこの小説の場合、青年は「こういう生き方もあるのか、私ならこうする」、壮年 「そうだ、この通りだ。俺も負けない」、熟年「我ながらよくやった」と。
中でも、企業で言えば、中間管理職には辛い読み物であろう。と同時に自らを鼓舞する、勇気と元気の本でもある。
以下、部分の抜粋。
《心を労することのない生活に慣れた人たちに特有の、無気力さと、消極的な自己主張がよくあらわれていた》
《攻める力はいつも、守る力に先行する。攻め口がわかるまでは、守る手段も立てられえない。いまどこがどのように攻められているか、敵の力がどれほどのものか、それを知ることができたらと思い、主水正は溜息をついた。山に近づくにしたがって、雪の降りかたはますます激しくなった。彼はそのまっ白なとばりの中で、絶望的な孤独感におそわれた》
《条件によって生活を支配される者と、どんな条件の中でも自分の生活を作ってゆく者とがある。大きく分けてその二つの生きかたがあり、そしてそのどちらも人間の生きかたなのだ、と彼は思った》
《彼はまざまざと、時の足音を聞くように思った。(中略) これらのほかにも老いたり死んだりした人は少なくないだろう。時は休みなく過ぎ去ってゆき、人はその時の経過からは逭れられない》
《そうだ、人間が自分の好ましいように生きられることは稀だし、平安な一生に恵まれることも極めて少ない。(中略) しかし仕事はこれからだ、始末を見届けるまで死ぬことはできない》
《石を運び、土を掘る人足たちと少しも違いはない。一文菓子を売り、馬子、駕籠かきをしても、人間が生きてゆくには、それぞれの苦しみやよろこびがある。そのありかたはいちようではないし、どっちが重くどっちが軽いという差別も評価もでききない》
奥野健男は解説で、次のように述べている。
『ながい坂』の主水正の生き方は、山本周五郎の作家、売文業者として生き方、処世術の自叙伝だと思う。こういう細心な生き方をしながら、ついに裏街や挫折から浮かび上がることのできない貧しい庶民のあきらめに似た哀感を、絶品ともいうべき短編にうたいあげている。そういうことを描くためには、文学者はこういうふうにながい坂を辛抱強く、ずるく生きなければならない、その舞台裏を書きながらそれを感動ある長編小説に昇華した作者の小説家根性は、見事であり、余人の追随を許さないものがある。
”逃げるな、真正面から挑め!” この本から汲んだ。