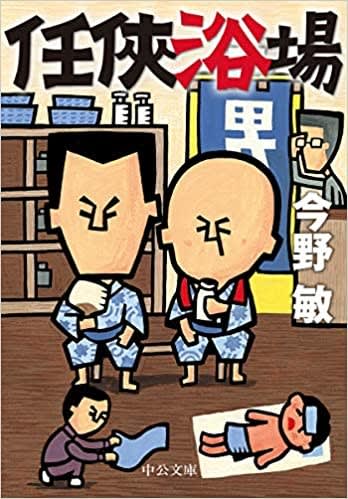著者 寺田 寅彦
出版 角川ソフィア文庫
碩学とは、これほど深く物ごとを考えるものか。専門の物理学を離れて、というより斯界と異なる場だからこそ、専門の理詰めの志向方法を駆使しての自由な発想・発展ができるのだろうか。
時代と社会を考察し、実に鮮やかに病巣を摘出する。そして治療の方途について自らの考えを述べる。しかし語り口は極めて柔らかい。その硬軟が特徴か。

残念なり。今頃読んでる自分が残念なり。我が高校生の時代、岡潔は読んでいたのに。
以下は、往時、評判になった随想の抜粋である。ジャーナリズムのあり方についての考察。あれから100年。益々狂風の募るメディアの昨今。思うところ多し。
「発明発見、その他科学者の業績に関する記事の特権は、たった一日経過しただけで、新聞記事としての価値を喪失するという事実がある。この事実もまたジャーナリズムのその日その日主義を証拠立てる資料となるであろう。学者の仕事は決して一日に成るものでなく、それを発表した日で消失するものでもないのであるが、新聞ニュースとしては一日過ぎれば価値はなくなる。しかも記者が始めて聞き込んだその日を一日過ぎるとニュースでなくなるのである。それで、誤ってジャーナリズムの擒となった学者はそのつかまった日一日だけどうにかして遁れさえすればそれでもう永久に遁げ了せることができるのは周知の事実である。
こういう実に不思議な現象の原因の一つは新聞社間の種取り競争に関連して発生するものらしく思われる。その日の種にしなければどこか他の新聞に出し抜かれているという心配がある。しかし翌日の新聞をことごとく点検する暇などはない。そうして翌日は翌日の仕事が山積しているのである。
このようなただ一日を争う競争はまたジャーナリズムの不正確不真実を助長させるに有効であることもよく知られた事実である。他社を出し抜くためにあらゆる犠牲が払われ、結局は肝心の真実そのものまでが犠牲にされて惜しいとも思われないようである。事実の競争から出発して結果が嘘較べになるのは実に興味ある現象と云わなければならない。
新聞社の種取り競争が生み出す悲喜劇はこれに止まらない。甲社の特種に鼻を明かされて乙社がこれに匹敵するだけの価値のある特種を捜すのに「涙ぐましい」努力を払うというのは当然である。嘘か真かは保証できないが、ある国でこんなことがあった。すなわち「あったこと」のニュースが見つからない場合に、面倒な脚色と演出によって最もセンセーショナルな社会面記事に値いするような活劇的事件を実際にもちあがらせそれがために可愛相な犠牲者を幾人も出したことさえ昔はあったという噂を聞いたことがある。ジャーナリストの側から云わせると、これも読者側からの強い要求によって代表された時代の要求に適応するためかもしれないのである。
昔はまたよく甲社で例えば「象の行列」を催して、その記事で全紙の大部分を埋め、そのほとんど無意味な出来事が天下の一大事であるかのごとき印象を与えると、乙社で負けていないで、直ちに「河馬の舞踏会」を開催してこれに酬ゆるといったような現象の流行した国もあったようである。
またある「小新聞」である独創的で有益な記事欄を設け、それがある読者サークルに歓迎されたような場合に、それを「大新聞」でも採用するようにと切望するものがかなりに多数あっても、大新聞では決してそれはしないという話である。これも人の噂で事実は慥かでないが、しかし至極もっともありそうな話である。これも強者の悲哀の一例であろう。
こういういろいろの不思議な現象は、新聞社間の生命がけの生存競争の結果として必然に生起するものであって、ジャーナリズムが営利機関の手にある間はどうにも致し方のないことであろうと思われる。
ジャーナリズムのあらゆる長所と便益とを保存してしかもその短所と弊害を除去する方法として考えられる一つの可能性は、少なくとも主要な新聞を私人経営になる営利的団体の手から離して、国民全体を代表する公共機関の手に移すということである。それが急には実行できないとすれば、せめて、そういう理想にすこしでも近づくようにという希望だけでも多数の国民が根気よくもち続けるよりほかに途はないであろう。
現在のジャーナリズムに不満を抱く人はかなりに多いようであるが結局みんなあきらめるよりほかはないようである。雨や風や地震でさえ自由に制御することのできない人間の力では、この人文的自然現象をどうすることもできないのである。この狂風が自分で自分の勢力を消尽した後に自然に凪ぎ和らいで、人世を住みよくする駘蕩の春風に変わる日の来るのを待つよりほかはないであろう。
それにしても毎日毎夕類型的な新聞記事ばかりを読み、不正確な報道ばかりに眼を曝していたら、人間の頭脳は次第に変質退化(デジェネレート)していくのではないかと気づかわれる。昔のギリシア人やローマ人は仕合せなことに新聞というものをもたなくて、その代わりにプラトーンやキケロのようなものだけをもっていた、そのおかげであんなに利口であったのではないかという気がしてくるのである。
ひと月に何度かは今でも三原山投身者の記事が出る。いったいいつまでこのおさだまりの記事をつづけるつもりであるのかその根気のよさには誰も感心するばかりであろう。こんな事件よりも毎朝太陽が東天に現れることが遥かに重大なようにも思われる。もう大概で打切りにしてもよさそうに思われるのに、そうしないのは、やはりジグスとマギーのような「定型」の永久性を要求する大衆の嘱望によりものであろう。しかし、たまには三原山記事を割愛したその代わりに思切って『古事記』か『源氏物語』か『西鶴』の一節でも掲載した方がかえって清新の趣を添えることになるかも知れない。毎月繰返される三原山型の記事にはとうの昔に黴が生えているが、たまに目を曝す古典には千年を経ても常に新しいニュースを読者に提供するようなものがあるような気もする。昨日の嘘は今日はもう死んで腐っている。それよりは百年前の真の方がいつも新しく動いているのである」
寺田 寅彦