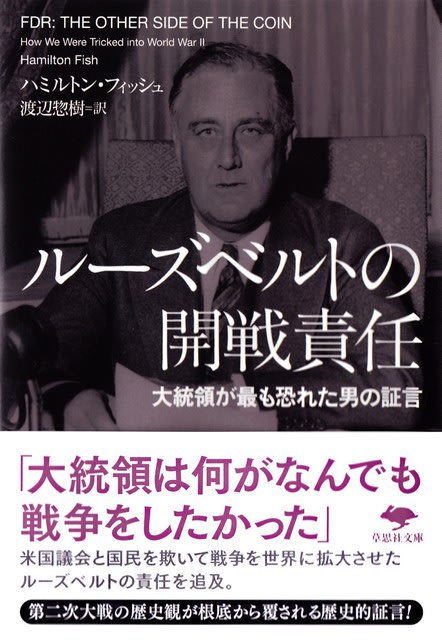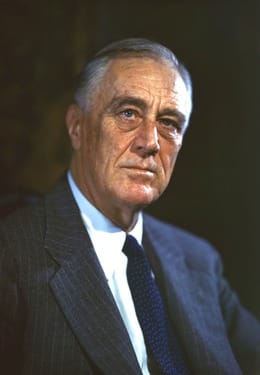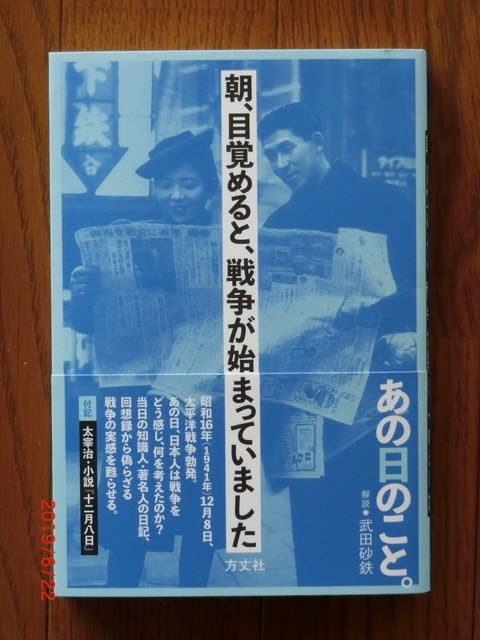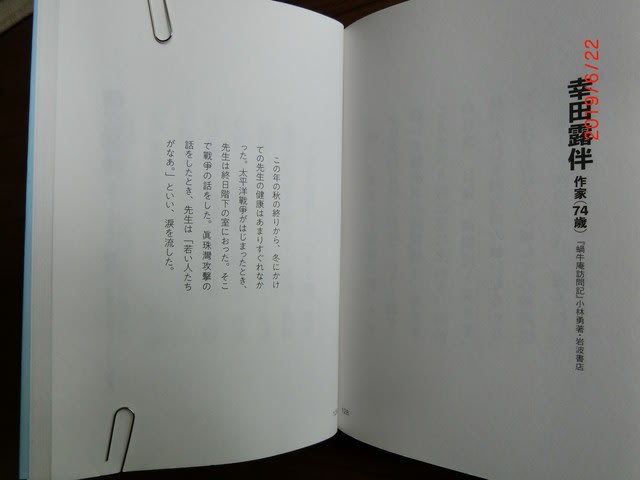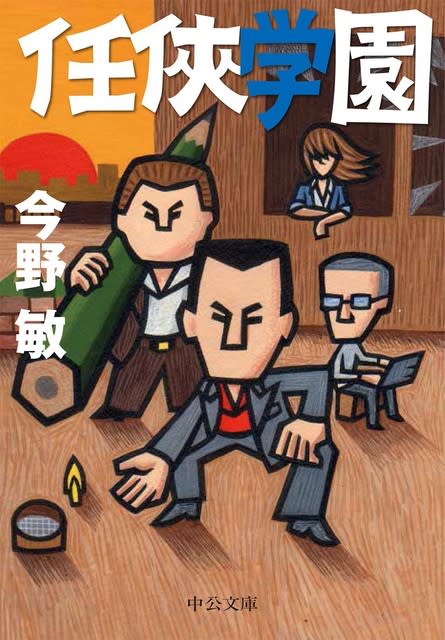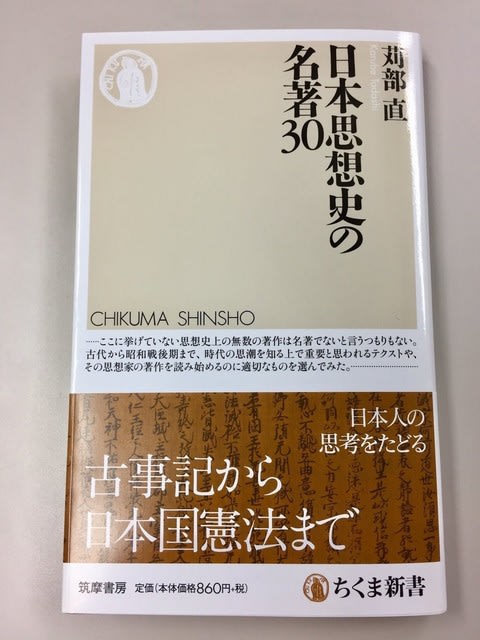著 者 原 武史
出 版 岩波新書
264頁

読もうと思ってから早4年も経っていたとは。改元を前にしていい勉強になった。
『実録』は、皇室の研究者や専門の学者にとっては、自身の研究の検証や正誤の確認作業をする上で最高の資料であり、その結果が我が国の正史となる。
宮中祭祀の多さには驚くばかり。平たく言えば神への祈りと報告と感謝が宮中祭祀。その多さには驚くばかり。これにかかる労力たるや半端ではない。知るに付け高齢では土台無理と理解できた。
敗戦か継続か、決断をめぐる逼迫した時系列は、生半可なドキュメントより生々しい。
現在日本の最大の平和勢力は天皇(皇室)と認識している。果たして安倍政権への思いは如何なるものか。20年後に次天皇の実録を読んでみたいものだ。
そうそう、読み進むうちに、小学生の頃、街道筋に並んで天皇の車列に日の丸の小旗を振ったことを思いだした。懐かしい。
今さらと無知を晒すことにはなるが、学んだ点或いは初めて知って吃驚の内容は、次の如くになる。




序論
丸山眞男は、西洋や中国の政治では権力は上から下へという構造になっているが、日本は真逆で下から上への『奉仕』あるいは『献上』の関係にあり、昭和天皇を見るとき、その図式が当てはまる。
第1講
明治天皇の子どもは男子が五人、女子が十人。すべて側室から生まれている。生き残ったのは男子が一人、女子が四人。他は満二歳までに夭折。
宮中が一夫多妻的な世界であることをいつ知ったのか。裕仁は訪欧後女官制度の改革に乗り出す。人数の大幅削減、源氏名廃止、通勤可、家庭持ち可などである。
裕仁はどこか女性的なところがある。甲高い声や話し方、なで肩や猫背のなどだ。それは四人の内親王、養育係担当など「女」に囲まれた環境で生まれ育ったことによるのではないか。
学習院初等科時代、華族女学校(後の学習院女学部)助教の野口幽香との面会が多く見られる。彼女はキリスト教徒。香淳皇后には戦時中に12回にわたり聖書の講義をしている。また、裕仁は07年のクリスマスには両親からクリスマス・プレゼントを貰うなどしており、この時から宮中にキリスト教の風習が入っていたことがわかる。



第2講
皇室の正統の帝を証するのが三種の神器。草薙剣(在熱田神宮)、八尺瓊勾玉(在伊勢神宮内宮)、八咫鏡(在伊勢神宮内宮)をいう。14歳初の行啓で三種の神器にまつわる重要な神社に参拝した。
宮中三殿の賢所は外陣・内陣・内内陣からなる。外陣は外側、内陣は中に入ったところ。さらに御簾で隔てた奥が内内陣で神鏡(八咫鏡の分身)が奉安されている。
成年式を迎えるまでは宮中祭祀に出てはならい決まりになっている点について、筆者は、高松宮日記における宮の言い分を取り上げ、「成年になって突然宮中祭祀に出たところで、それまで全く宗教的な教育を受けていないのに、急に信仰心が生まれ心から神の存在を信じることなどできるかどうか、出来るわけがない」と紹介している。若い皇族のさまが伝わってきて面白い。
新嘗祭は夕方から未明までかかる重要な祭祀。しかも夕の儀と暁の儀がある。同じ事を2回行う。この間、天皇と皇太子は正座で臨む。
福岡の香椎宮と大分の宇佐神宮は、勅祭社といい、天皇の勅使が派遣される特別な神社。他に埼玉県大宮の氷川神社、靖国神社、出雲大社も勅祭社となっている。
二十歳の初訪欧。ローマ法王ベネディクト15世とは20分に渡り話す。急遽の実現は山本御用掛(山本信次郎海軍大佐:熱心なカトリック信者で法王と篤い信頼関係があった)によるもの。裕仁は、カトリックとプロテスタントの違い、カトリックが日本の国体を変更することはあり得ないこと、将来カトリックと日本国が提携することもあり得る暗示をうけるなど、法王が念入りに準備して待っていたような中身の濃い対話だった。
‘21年、摂政になったのを機に、洋館の東宮仮御所での日常は西洋風に改まった。洋服しか着ない、ベッドで眠り、テーブルで執務をし、洋食を食べるという具合に。
久邇宮良子との結婚は‘24年1月26日、宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)で執り行われた。三殿は1888年建設以来修繕を繰り返し、今も当時の姿を整えている。この年の8月には猪苗代湖畔の高松宮別邸に滞在、いわゆる新婚旅行生活。夕食後、二人でモーターボートに乗り、ベランダで月を見、良子がピアノで歌を歌い、裕仁の手綱で馬車の散歩をしたりした。
三韓征伐をした神功皇后(199~269執政)を天皇に加えるべきかどうかは長らく論議されてきたが、正式に外れることが決まったのは昭和改元の二か月前だった。これで初代神武から大正まで123代の歴代天皇が確定した。

第3講
1926年(大正15年)に大正天皇が死去、皇太子裕仁は天皇となるが、‘27~’29年にかけて天皇への直訴が頻発する。中でも‘28年などは毎月のように起こる。何故か。大正天皇が見えなくなった”天皇なき時代”が5年続いていた。それが終わりをつげ正真正銘の天皇が現れたという背景が一番の理由。二番目が政治に対する不信。立憲政友会と立憲民生党の二大政党にはなったが、女性と植民地には参政権は与えられず、労働者代表の無産政党は数議席しかなく、改正された治安維持法により一層追い込まれ、政治から疎外された人たちの声が反映されないということがあった。
天皇になって以降、地方行幸は更に大掛かりになってゆく。一例、①玉座着御②敬礼③君が代④参加各員の分裂行進⑤挙手答礼⑥奉迎歌(女子奉唱隊)
天皇は選挙結果に大きな関心を示した。侍従に候補者一覧に赤・青の印をつけさせ、夜はラジオの選挙成績結果放送を聴取された。これは、無産階級がどれだけ進出するかを見るにあった。社会民衆党や日本労農党など無産者のための政党が躍進することが望ましいと考えていたよう。
元老西園寺公望は、皇太后が敬神の念が強く政治に口出しをすることが多いことに強い警戒感を抱いていた。日中戦争が行き詰まり政権を投げ出そうとした近衛文麿が皇太后に激励されたとたんに舞い上がったが、これを西園寺は厳しく叱咤したいう。
天皇は映画好き。'32~34年に皇后や内親王などと鑑賞した映画の一例。パラマウント・ニュース、人情劇「奇跡の人」、漫画「我らは狩りに行く」、「赤頭巾さん」、紅の国の兎さん」、文部省製作「皇国の栄」、ニュース映画、東郷元帥に関する映画など。大戦中には「マレー戦記・進撃の記録」「ハワイ・マレー沖海戦」「シンガポール総攻撃」など。宮中では最も調子のよかった時の映画を見続けていたになる。戦局を見誤らせたことにならなかったろうか。
第4講、第5講は割愛。



以下二編は当ブログの天皇関連物。
「終戦のエンペラー」
「畏るべき昭和天皇」
平成31年3月14日付「朝日新聞」が『昭和天皇実録』に5000カ所の誤りがあると報じた。日付、地名、人名などで、史実に大きな影響を与えるミスではないが、今後正誤表を作成すると宮内庁。驚くべきは、完成2年後の2014年10月に、昭和天皇の御製について詠んだ情景が違うことを今上天皇が指摘されたこと。
【雑学エピソ―ド】
アップ間際に下記のメールが飛び込んできた。これも参考に。
☆リンカーンとダーウィン。同じ誕生日の二人の胸像が、昭和天皇の書斎に戦前から飾られていた。昭和天皇は生物学の研究者でダーウィンの「進化論」は愛読書だったが、二人の誕生日が同じだと知っていたのかは不明。共に1809年2月12日生まれ。
(進化論→昭和天皇)
───────────────────────────────────
☆かつてのお正月の定番、染之助染太郎は80年代末に「お染めブラザース」と呼ばれ人気があった。実はその時『おめでとうございます』と言う曲を発表!しかしその直後昭和天皇が倒れ半年後に崩御したので人前で歌えず終わった。
(昭和天皇→定番)
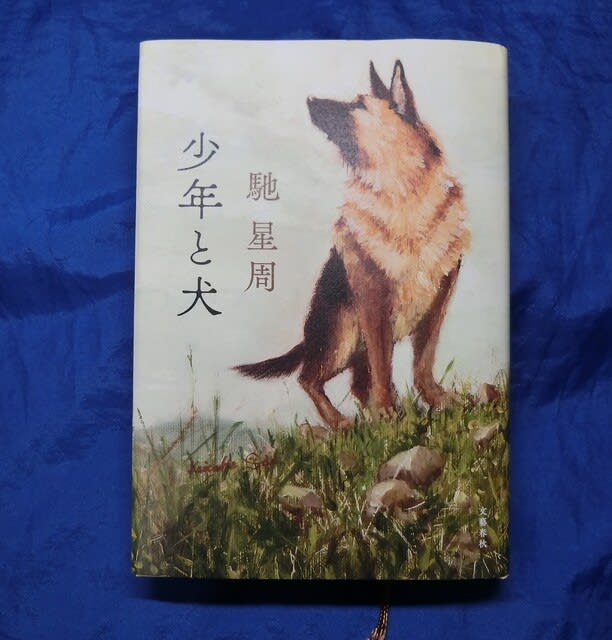











 google
google