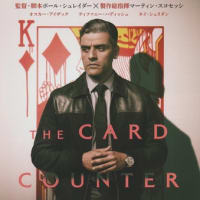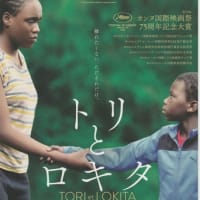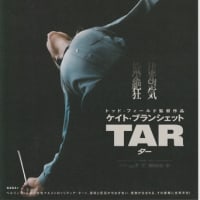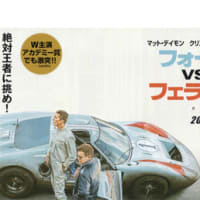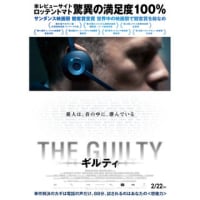これまで,トニー・スコットとの相性は最悪だった。古くは大ヒットした「トップガン」や「ビバリーヒルズ・コップ2」から,近年では「デジャヴ」や「サブウェイ123」まで,記憶にある限り思わず膝を打つという瞬間は,ついぞ訪れたことはなかった。好意的な評者からは「スタイリッシュ」と見なされてきた,アクションシーンにおける大量のカットは,私にはどう見ても物語を支える力を欠いた,フィルムの浪費としか思えなかったのだ。
唯一,物語自体がその映像スタイルを追い越すスピードを獲得していた「トゥルー・ロマンス」は,完全に脚本を書いたクエンティン・タランティーノの作品だったし,66歳という年齢を考えると,そりの合わない,縁のない監督で終わるのだろうなと思っていたのだが,これがとんだ見当違いだった。
黒澤明が映画化を熱望しながら果たせず,結局よりによって何故?という人選となったアンドレイ・コンチャロフスキーが撮った「暴走機関車」が,本来持つべきだった活劇としてのエッセンスが,ここにぎっしりと詰まっている。
既に勧奨退職が決まっている初老の機関手(デンゼル・ワシントン)と,コネで職を得たらしい経験の浅い車掌(クリス・パイン)が乗った貨物列車が,無人のまま暴走した別の貨物列車と衝突しそうになる。機関手の機転で難を逃れた二人は,今度は無人の貨物車をどうにか止めるべく,その後を追いかける。
二人の家族が物語の背景として簡単にスケッチされはするが,二人の乗った機関車と,それをオペレートする女性がいる司令室,そして無人の貨物列車とそれを追いかけるマスコミ,という3つのシークエンスが,どっぷりハリウッド・テイストながらも職人的な滑らかさで組み合わされ,正攻法で観客の心拍数を上げるべく,スクリーン上で輝いている。
確かに細部を見ていけば,ラストで機関車に飛び移るのは別に車掌でなくてもよかったのではないかとか,列車が脱線して炎上するかもしれない危険なカーブに集まってきた野次馬が何故放置されているのかとか,話の展開には相変わらずのご都合主義が目立つ。ひとつひとつのショットにも,大見得を切るような構図が目立ち,考え抜かれた短いショットが繊細に紡がれて,大きな絵を描く,という風情がある訳でもない。
しかしアクション映画,とりわけトニー・スコット作品においては作品の心臓部となってきた,撃ち合いも殴り合いもないのに,極めて高いレベルの躍動感と緊張感が1時間39分の間,見事に持続する。ひたすら暴走し続ける列車と,徒手空拳ながらもどうにかしてそれを止めようともがく男の姿という,絵的にはどう見ても躍動感とは程遠いショットが,それを成し遂げるのを見守る観客は,驚き越えるものを確かに体験するはずだ。
決して脳天気なヒーローものが駄目だったと言っている訳ではないのだが,くたびれた初老の機関手が経験を頼りに,本能的な職業倫理観から発した責任を果たそうと汗を流す姿は実に美しい。二人が乗る機関車が,無人の列車を捉えるべく追いかけるのが,走る方向の関係で最後まで「後ろ向き」という脚本上の仕掛けが,トニー・スコットが辿り着いた境地を象徴して,見事だ。
★★★★☆
(★★★★★が最高)
唯一,物語自体がその映像スタイルを追い越すスピードを獲得していた「トゥルー・ロマンス」は,完全に脚本を書いたクエンティン・タランティーノの作品だったし,66歳という年齢を考えると,そりの合わない,縁のない監督で終わるのだろうなと思っていたのだが,これがとんだ見当違いだった。
黒澤明が映画化を熱望しながら果たせず,結局よりによって何故?という人選となったアンドレイ・コンチャロフスキーが撮った「暴走機関車」が,本来持つべきだった活劇としてのエッセンスが,ここにぎっしりと詰まっている。
既に勧奨退職が決まっている初老の機関手(デンゼル・ワシントン)と,コネで職を得たらしい経験の浅い車掌(クリス・パイン)が乗った貨物列車が,無人のまま暴走した別の貨物列車と衝突しそうになる。機関手の機転で難を逃れた二人は,今度は無人の貨物車をどうにか止めるべく,その後を追いかける。
二人の家族が物語の背景として簡単にスケッチされはするが,二人の乗った機関車と,それをオペレートする女性がいる司令室,そして無人の貨物列車とそれを追いかけるマスコミ,という3つのシークエンスが,どっぷりハリウッド・テイストながらも職人的な滑らかさで組み合わされ,正攻法で観客の心拍数を上げるべく,スクリーン上で輝いている。
確かに細部を見ていけば,ラストで機関車に飛び移るのは別に車掌でなくてもよかったのではないかとか,列車が脱線して炎上するかもしれない危険なカーブに集まってきた野次馬が何故放置されているのかとか,話の展開には相変わらずのご都合主義が目立つ。ひとつひとつのショットにも,大見得を切るような構図が目立ち,考え抜かれた短いショットが繊細に紡がれて,大きな絵を描く,という風情がある訳でもない。
しかしアクション映画,とりわけトニー・スコット作品においては作品の心臓部となってきた,撃ち合いも殴り合いもないのに,極めて高いレベルの躍動感と緊張感が1時間39分の間,見事に持続する。ひたすら暴走し続ける列車と,徒手空拳ながらもどうにかしてそれを止めようともがく男の姿という,絵的にはどう見ても躍動感とは程遠いショットが,それを成し遂げるのを見守る観客は,驚き越えるものを確かに体験するはずだ。
決して脳天気なヒーローものが駄目だったと言っている訳ではないのだが,くたびれた初老の機関手が経験を頼りに,本能的な職業倫理観から発した責任を果たそうと汗を流す姿は実に美しい。二人が乗る機関車が,無人の列車を捉えるべく追いかけるのが,走る方向の関係で最後まで「後ろ向き」という脚本上の仕掛けが,トニー・スコットが辿り着いた境地を象徴して,見事だ。
★★★★☆
(★★★★★が最高)