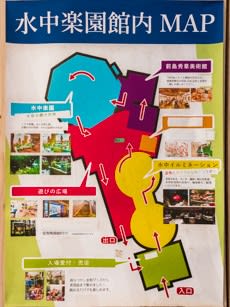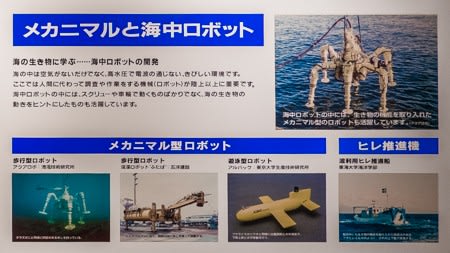水中イルミネーション前編エリア、最後はコメットの仲間。
コメットは、アメリカから輸入された品種。基本的に金魚は
人間の手によって品種を存続させなければ先祖返りをおこし
徐々にフナへと戻ってしまう。そんな先祖返りした個体から
誕生したのが、このコメットという品種の金魚というわけだ。
コメットの元となったのは琉金だったそうで、尾ビレに
その特色を残していたりするが、体型的には和金に近い。


中には先祖返りが進んで、フナ型の尾ビレをもった個体もいる。
このゴールデンコメットは体の色素が少なくなった白変種かな。
今回このエリアでは、計6種類のコメットが展示されていたが
その半数は、イエローコメットを始めとした黄色い品種だった。


イエロー紅葉コメットは、もみじと名についている透明鱗を有した種。
キラキラは、キラキラコメットと記されている水槽もあったけれど
これも青文魚と同じように同一種で表記が異なっているだけだろう。


部屋の中央にある大盃。1度目の訪問では、コメットと朱文金が泳いでいたが
再来した際には、イエローコメットと更紗コメットへと展示が変更されていた。
最後は、ちょっと変わった品種を2種。紅葉出目金と
オランダ獅子頭を交配させて作られたという、輝竜。


そして、もう1種類が鳳凰。こちらは、まだ新しい品種なのか
詳細がよく分からず。なんにせよ大層な名がつけられた2種だ。
これにて水中楽園最初の展示エリアにいた金魚は全てとなる。
しかし水中イルミネーションは、まだ後半エリアがあるのだ。
①和金・朱文金へ戻る ②琉金・玉サバへ戻る
④オランダ・ランチュウへ戻る 水中イルミネーション後編へ進む
コメットは、アメリカから輸入された品種。基本的に金魚は
人間の手によって品種を存続させなければ先祖返りをおこし
徐々にフナへと戻ってしまう。そんな先祖返りした個体から
誕生したのが、このコメットという品種の金魚というわけだ。
コメットの元となったのは琉金だったそうで、尾ビレに
その特色を残していたりするが、体型的には和金に近い。


中には先祖返りが進んで、フナ型の尾ビレをもった個体もいる。
このゴールデンコメットは体の色素が少なくなった白変種かな。
今回このエリアでは、計6種類のコメットが展示されていたが
その半数は、イエローコメットを始めとした黄色い品種だった。


イエロー紅葉コメットは、もみじと名についている透明鱗を有した種。
キラキラは、キラキラコメットと記されている水槽もあったけれど
これも青文魚と同じように同一種で表記が異なっているだけだろう。


部屋の中央にある大盃。1度目の訪問では、コメットと朱文金が泳いでいたが
再来した際には、イエローコメットと更紗コメットへと展示が変更されていた。
最後は、ちょっと変わった品種を2種。紅葉出目金と
オランダ獅子頭を交配させて作られたという、輝竜。


そして、もう1種類が鳳凰。こちらは、まだ新しい品種なのか
詳細がよく分からず。なんにせよ大層な名がつけられた2種だ。
これにて水中楽園最初の展示エリアにいた金魚は全てとなる。
しかし水中イルミネーションは、まだ後半エリアがあるのだ。
①和金・朱文金へ戻る ②琉金・玉サバへ戻る
④オランダ・ランチュウへ戻る 水中イルミネーション後編へ進む